※本記事にはアフィリエイト広告を利用しています。商品リンクを経由して購入された場合、当サイトに収益が発生することがあります。
1. タクロリムス(プロトピック®︎)軟膏とは?
タクロリムス軟膏は、ステロイド外用薬以外で初めて、本格的にアトピー性皮膚炎の標準治療薬として登場した“元祖的存在”です。1999年(0.03%小児用は2003年)に日本で世界に先駆けて承認、発売されて以来、長期にわたりアトピー治療の柱として使われ続けています。
それ以前にもNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)の外用薬は存在しましたが、アトピー性皮膚炎のような強い炎症には十分な効果を示すものではありませんでした。その点、タクロリムス軟膏は強力な免疫抑制作用を外用形態で実現した画期的な薬として、1999年発売以降も“非ステロイド外用薬の代表格”として位置づけられています。
さらに、日本皮膚科学会・日本アレルギー学会によるアトピー性皮膚炎診療最新ガイドラインでも、タクロリムス軟膏は引き続き外用治療の基本的選択肢として位置づけられており、その重要性が改めて確認されています。
2. タクロリムス軟膏の特徴
2-1. タクロリムスは「炎症スイッチ」を止める薬
タクロリムス軟膏は、カルシニューリン阻害薬と呼ばれるタイプの薬です。
カルシニューリン(以下CN)は、免疫細胞の中で働く“スイッチのような酵素”で、体に細菌やアレルゲンなどの異物が入ったときに活性化します。CNが働くことで免疫の司令役となる物質が作られ、T細胞の活性化やサイトカインの産生が進み、免疫応答が強まります。
ただし、このCNの働きが過剰になると、IL-2などの炎症性サイトカインが過剰に分泌され、かゆみや炎症が強くなることがあります。
ここで登場するのがタクロリムスです。皮膚の免疫細胞にはFKBP12というたんぱく質があり、これはちょうど「スイッチ役」のような存在です。 タクロリムスがFKBP12に結びつくことで、CNの働きを止める仕組みが働き、炎症とかゆみの悪循環を抑えることができるのです。
2-2. ステロイドとの相違点
ステロイド外用薬は炎症を抑える力は非常に強力ですが、タクロリムスとは働き方が異なります。 ステロイドはより広い範囲に作用し、NF-κBやAP-1といった炎症の“司令塔”を直接抑えることで、即効性に優れているのが特徴です。
ただし、長期間使い続けると、皮膚が薄くなったり、毛細血管が広がるなどの副作用が出やすくなるため、使用には注意が必要です。
一方、タクロリムスはピンポイントでカルシニューリンを止める薬です。そのため効力はやや劣るものの、皮膚萎縮などの副作用が起こりにくいという利点があり、顔や首など皮膚の薄い部位にも長期で使いやすい特徴があります。
2-3. 高頻度の副作用
タクロリムス軟膏は、現在使用できるアトピー性皮膚炎の外用薬の中でも副作用の発現頻度が高い薬です。特に、ヒリヒリ感・ほてり感およびかゆみの一時的な増悪などが代表的で、多くの方が経験します。
あらかじめこうした副作用の特徴を理解しておかないと、「自分には合わない薬だ」と思って途中でやめてしまい、せっかく有用な薬を遠ざけてしまう可能性もあります。
このようなことにならないためにも、以下の項でしっかり対策を学び予習しておくと良いでしょう。
3. 基本的事項
3-1. 効能・効果
タクロリムス軟膏の適応症は、「アトピー性皮膚炎」ひhです。
添付文書上では、既存の治療法(ステロイド外用薬など)で効果が不十分な場合、あるいは副作用などの理由でステロイドを使用できない場合に、本剤を用いることが適切とされています。つまり、承認上は「ステロイドに次ぐ選択肢」として位置づけられています。
しかし実際の医療現場では、顔や首など皮膚が薄く副作用リスクが高い部位や、小児など長期に治療が必要なケースでは、より積極的にタクロリムスが使われています。
3-2. 用法・用量
通常は1日1〜2回、適量を患部に塗布します。1回に使用できる最大量は5g(チューブ1本分)です。
インタビューフォームによれば、十分な効果を得るためには基本的には1日2回の使用が望ましいとされています。ただし、臨床試験の結果からは、4週間を超えて使用した場合には、1日1回と2回の効果差はほとんど認められないことが報告されています。
これはすなわち、炎症が落ち着いてきた軽症例や寛解維持期には、1日1回の使用でも効果を期待できることを示唆しています。
一方で、皮疹が強くバリア機能が大きく損なわれている場合には、薬剤が過剰に吸収され血中濃度が高くなり、全身性の副作用が生じるリスクがあります。そのため、1回の使用量が5g以内に制限されており、また2週間以内に改善が見られない場合には中止を検討する必要があります。
3-3. 併用禁忌
タクロリムス軟膏の使用中は、PUVA療法などの紫外線療法を併用は不可となっています。
PUVA療法とは、ソラレン(オクソラレン®︎)という光感受性物質を投与した後に、長波長紫外線(UVA)を照射する治療法で、主に尋常性白斑や乾癬などに用いられます。
併用が禁じられている理由は、動物実験で皮膚腫瘍のリスク増加が報告されたためです。具体的には、40週間にわたりUVAおよびUVBを照射し、その後12週間観察するという実験で、タクロリムス軟膏と紫外線を併用した群では皮膚腫瘍の発生が早まったとされています。この結果から、紫外線療法とタクロリムスの併用は発がんリスクを高める可能性があると判断され、併用禁忌とされています。
3-4. 副作用
3-4-1. 高頻度および特徴的な副作用
タクロリムス軟膏は、非常に高頻度で副作用が起こる薬です。使用を始める際には、あらかじめ副作用が出る前提であることを理解し、その対策も知っておくことが大切です。ここでは、添付文書や臨床報告に基づき、頻度が高いものや代表的なものを示します。
- 灼熱感・ほてり感:約44%
- ヒリヒリ感・疼痛感:約24%
- 搔痒感(かゆみ)
- 細菌性感染症(毛嚢炎、とびひ など)
- ウイルス性感染症(単純疱疹、カポジ水痘様発疹症 など)
- 真菌性感染症(白癬 など)
- ざ瘡(にきび様皮疹)
この中でも特に灼熱感やヒリヒリ感は使用開始時に多くの患者さんが経験する副作用であり、治療を続ける上で最大の課題とも言えます。これについては次章「4. 灼熱感や刺激感の正体」で詳しく解説します。
3-4-2. やっかいなかゆみの一時増悪
灼熱感や刺激感のほかに、もう一つ注意すべき副作用がかゆみの一時的な増悪です。「かゆみを抑える薬なのに、なぜ悪化するの?」と驚かれるかもしれませんが、これは特に治療開始直後や炎症が強い急性期に起こりやすい症状です。あらかじめ説明していても、実際に強いかゆみを感じて中止してしまう患者さんも少なくありません。
一時的な対策としては、以下のようなことが挙げられます。
- ぬるめのシャワーで洗い流すなど一時的に刺激を和らげる工夫
- まずステロイド外用薬で炎症を抑えてからタクロリムスに切り替える(詳細は「4-3-3. ステロイド外用薬での先行治療」参照)
3-5. 発がん性
タクロリムス軟膏に関しては、発売から数年後に発がん性の可能性が話題になった経緯があります。当時は「使用を控えるべきではないか」といった議論もありましたが、その後の詳細な検証の結果、通常の使用において発がんリスクが高まることはないとされ、現在でも安全性の高い薬として広く用いられています。
3-5-1. 発端となった動物実験
0.1%製剤が登場し、その後0.03%小児用の承認を検討する段階で、マウスを用いた発がん性試験が行われました。
- マウスの体表の約40%に、0.03〜1%タクロリムス軟膏を1日1回、2年間塗布。
- その結果、0.3%以上の濃度では全身毒性による死亡が増加。
- 評価対象とされた0.03%および0.1%群では、皮膚に発がん性は認められなかった。
- 一部で高濃度群においてリンパ腫の増加が報告されたが、その特徴は自然発生のリンパ腫と同等であり、因果関係は不明確とされている。
3-5-2. 現在の評価
これらの結果を踏まえ、「通常の使用量を守り、適切に使っている限り、発がん性のリスクは問題ない」と結論づけられています。
実臨床でも20年以上にわたり広く使用されてきた中で、タクロリムス外用による発がんリスクが顕著に高まるといった報告は確認されていません。
4. 灼熱感や刺激感の正体
タクロリムス軟膏の最大の弱点としては、かなり高い割合で灼熱感や刺激感を感じてしまうことです。これらの症状は、しばらくすると軽減したり消失するとの記載はありますが、継続する上での弊害になる恐れがあります。
ただし、この「灼熱感」は本当に悪いことなのでしょうか?
4-1. 灼熱感や刺激感のメカニズム
タクロリムスは、皮膚の神経に存在するTRPV1チャネルを一時的に活性化させることが知られています。TRPV1は熱や痛みに反応する“スイッチ”のような役割を持ち、唐辛子に含まれるカプサイシンの刺激を感じるのもこのTRPV1によるものです。
このチャネルが刺激されると、サブスタンスPなどの神経ペプチドが放出され、神経を興奮させて「ヒリヒリ」「灼熱感」といった感覚を引き起こすと考えられています[1]。
一方で、タクロリムスの使用を続けることでTRPV1が脱感作(徐々に感覚が慣れて鈍くなること)を起こし、こうした副作用が少しずつ軽くなっていく傾向が報告されています
4-2 灼熱感や刺激感の悪化要因
灼熱感やヒリヒリは「起きやすい条件」を外すだけでも体感がかなり変わります。以下悪化しやすい要因はいくつか記述するので、避けられるものであれば避け発生率を減らすことに努めましょう。
- 皮膚バリアの破綻
タクロリムス軟膏は、皮膚のバリアが壊れている部位ほど吸収されやすいという特性があります。そのため、強くかきむしってびらんができていたり、湿疹が悪化している部位では、ヒリヒリや灼熱感が強く出やすい傾向があります。
一方で、これは裏を返すと、健康な皮膚からはほとんど吸収されないということでもあります。つまり、炎症がある部位だけに選択的に効きやすい性質があるのです。この特徴は、副作用として「刺激感」をもたらす一方で、正常皮膚に不必要な影響を与えにくいという臨床的メリットにもつながっています。
タクロリムス軟膏の特性として、皮膚バリアが破損している部位からより吸収されやすいことがあがられます。したがって、ひどくかきむしってしまったり、湿疹がひどい部位にヒリヒリ感などが出やすい傾向があります。また、それは言い換えると、正常な皮膚からはほとんど吸収されない特性であるとも言えます。 - 熱・温度差・紫外線
タクロリムスで問題になる灼熱感は、熱刺激によって悪化しやすい傾向があります。皮膚の知覚神経にある TRPV1 、熱や唐辛子成分(カプサイシン)などに反応する“痛み・熱さのセンサー”であり、これが刺激されることでヒリヒリ感が増幅すると考えられています。
特に塗りはじめの数日間は、皮膚が敏感になっているため、熱いシャワーや湯船に浸かると、一時的に強い痛みや灼熱感が出ることがあります。
4-3. 灼熱感や刺激感の軽減法
タクロリムス軟膏の代表的な副作用である灼熱感や刺激感は、使い始めや継続中に大きなハードルとなることがあります。ここでは、実際に報告されているいくつかの工夫や方法を紹介します。少しでも症状を和らげることで、治療を続けやすくなる助けになるかもしれません。
4-3-1. タクロリムスの希釈
対策の一つとして、他の薬剤と混ぜて濃度を下げる方法が報告されています。実際に、保湿剤と混ぜて使ったことで「ヒリヒリ感が軽くなり継続できた」という例もあります。具体的には、ワセリンと同程度で混ぜて塗布する方法が臨床現場で用いられることがあります(注1)。
また、タクロリムスには小児用(0.03%)があり、成人用(0.1%)に比べて濃度が約1/3に設定されています。刺激感がどうしても強い場合、こちらを試すのも一つの方法です。ただし、成人に小児用を処方することは本来の適応外となるため、原則は保険適用外です(実際には保険で処方されているケースもあるようですが、医療機関の判断によります)。
希釈する際には、医療現場でも広く使われている「白色ワセリン」を用いるのが一般的です。白色ワセリンは不純物が少なく、肌にやさしいため、他の外用薬との混合や希釈の基材としてだけでなく、そのまま皮膚保護剤として塗布したり、ガーゼに伸ばして乾燥や刺激から守る用途にも活用できます。
👉日本薬局方 白色ワセリン 500g
(注1)タクロリムス軟膏は基本的に他剤との混合は安定性の面から推奨されていません。そのため混合する場合は、同じ軟膏基剤であるワセリンと、使用直前に手のひらなどで混ぜてすぐに塗布するのが望ましいとされています。あくまで医師と相談の上で行うべき補助的な方法であり、自己判断ではしないようにしましょう。
4-3-2-. 悪化要因を避ける
タクロリムス軟膏の刺激感は、熱刺激や紫外線などの外的要因で悪化しやすいことが知られています。したがって、日常生活でこうした刺激をできるだけ避けることが、副作用を和らげる一助になります。
- 使用タイミングを工夫する
タクロリムス軟膏は、紫外線や気温差、発汗などの外的刺激によって刺激感が増強されることがあります。特に朝に塗布して外出すると、これらの環境因子の影響を受けやすくなるため、外的刺激の少ない夜間の使用が推奨されます。
なお、タクロリムス軟膏の通常の使用頻度は1日2回とされていますが、寛解期や軽症例では1日1回の使用でも十分なことがあります。そのため、軽症時には夜間のみの使用も選択肢となりますが、急性期や炎症が強い場合には、後述するステロイド外用薬による先行治療を併用する方が現実的かつ効果的です - 熱刺激を避ける
入浴やシャワー時には、38℃前後のぬるま湯を使用することで、皮膚への負担を軽減できます。とくに治療開始初期は、熱い湯によるヒリヒリ感が強く出ることがあるため注意が必要です。 - 紫外線を避ける
紫外線は、タクロリムス軟膏の副作用を悪化させるだけでなく、皮膚炎症の増悪因子にもなります。したがって、直射日光の回避、患部の衣類による遮蔽などが有効です。必要に応じて、低刺激性の日焼け止めの併用も検討されます。
4-3-3. ステロイド外用薬での先行治療
灼熱感や刺激感の悪化要因のひとつに、皮膚バリアの破綻があるために、まず数日間はステロイド外用薬で炎症を抑え、皮膚をある程度落ち着かせてからタクロリムスに切り替えることで、刺激感を軽減できることが知られています。
さらに、アトピー性皮膚炎の治療戦略としてもこの方法には理があります。タクロリムス軟膏の抗炎症作用はステロイドに比べると中等度の強さとされており、強い炎症には十分な効果を発揮しにくいのが実際です。そこで、「急性期はステロイドで抑える → 維持期はタクロリムスで安全にコントロールする」という流れでの治療も推奨されます。
4-4. 刺激感は効果の裏返し?
タクロリムス軟膏を使用した際に感じる灼熱感や刺激感は、多くの患者にとって「不快な副作用」として認識されがちです。しかし一部の専門家は、これを薬剤の薬理作用が発現しているサインと捉えることもあります。
興味深いことに、これらの神経ペプチドは繰り返し刺激されることで枯渇し、結果としてかゆみや炎症が軽減されるという臨床的な報告もあります。この現象は、神経性炎症の制御という観点から、タクロリムスの作用機序の一部と考えられています。
ただし重要なのは、刺激感が必ずしも「効いている証拠」ではないという点です。刺激感は個人差が大きく、皮膚バリアの状態や塗布部位、使用時の環境要因によっても左右されます。長期にわたって刺激感が続く場合や、日常生活に支障をきたすほど強い場合には、無理をせず医師や薬剤師に相談することが重要です。
5. タクロリムス軟膏の独自の強み
5-1. 長期の実績
タクロリムス軟膏は1999年に登場し、新しい治療選択肢として注目され、特にアトピー性皮膚炎の長期管理において重要な役割を果たしてきました。
これらは、比較的新しく登場したコレクチム®(JAK阻害薬)、モイゼルト®(PDE4阻害薬)、ブイタマー®(AhR調整薬)などが、まだ長期的な安全性や使用経験の蓄積が少ない点と対照的です。新薬が持つ革新性に対して、タクロリムス軟膏は「実績」という確かな土台を持つことが、治療選択における大きなアドバンテージとなります。
5-2. 寛解維持の確立されたエビデンス
タクロリムス軟膏は、寛解導入後に週2回塗布を継続すると再燃を減らせることが複数の研究で示されています[2]。
アトピー性皮膚炎は特に小児に多い疾患であり、この時期にいかに炎症を繰り返さず皮膚状態を安定させるかが、その後の生活の質や成長発達にもつながります。
そうした背景から、タクロリムスは「早期から長期にわたって安心して使える寛解維持薬」としての位置づけを確立してきました。
5-3. 抗マラセチア作用
タクロリムス軟膏には、マラセチア属真菌に対して弱いながらも抗真菌作用を示すという報告があります[3]。
これは、マラセチア過剰が炎症の悪化因子とされる「頭頸部優勢型アトピー」において、臨床的に意味を持つ可能性があります。
通常、炎症性サイトカインを抑える薬(ステロイドや他の非ステロイド外用薬)は、細菌や真菌感染を悪化させやすいため、マラセチア関連の皮疹には直接的な効果は期待できません。
その中で、タクロリムスが例外的に抗マラセチア作用を持つ点は特徴的であり、マラセチアを併発しやすい方にとっては薬を選択する際の後押しになる要素と考えられます。
5-4. ジェネリックの存在
タクロリムス軟膏は発売から20年以上が経過しているため、すでにジェネリック医薬品が登場しています。
アトピー性皮膚炎の治療は短期間で終わることは少なく、多くの患者さんにとって長期にわたって薬を使い続ける必要があるのが現実です。そのため、薬剤費の負担は決して軽くありません。
ジェネリック医薬品の存在は、治療を続ける上での経済的な安心感につながります。アトピー性皮膚炎に塗料において、「薬を切らさずに継続できること」が症状の安定化に直結します。
一方で、次に市場に登場した非ステロイド外用薬であるコレクチム軟膏(デルゴシチニブ)などは、まだ新しい薬であり、ジェネリックが出るまでには数年はかかること見込まれます。つまり、現時点では長期治療のコスト面においても、タクロリムス軟膏に優位性があると言えるでしょう。
6. 薬剤師および患者の観点からの経験談
私自身も幼少期からアトピー性皮膚炎と付き合っており、プロトピック軟膏が発売された当初から継続的に使用してきました。ここでは、薬剤師としての知識に加え、患者として20年近く使用してきた実体験を簡単にご紹介します。
- 主な使用部位:顔面および首(体躯にはほぼ効果を感じられない)
- 重症度:中等症(休職中は軽症)
- 使用頻度:週3〜5回程度
かゆみや湿疹が強いときに使用すると、ヒリヒリ感・ほてり感・かゆみの一時的な増悪が顕著に出ることがありました。その状態で無理に続けても、症状の改善をあまり実感できないことが多いです。
そうした場合にはステロイド外用薬を併用するのですが、中等度ランクのステロイドでは数日塗っても効果が乏しく、強いランクのステロイドを使うと1〜2日で明らかな改善を感じることができました。
また、他の非ステロイド外用薬(コレクチム、モイゼルト、ブイタマー)とも比較したところ、あくまで私個人の印象としては以下の順でした:
強いランクのステロイド > タクロリムス > コレクチム ≒ モイゼルト > ブイタマー ≒ 中等度ランクのステロイド
もちろん、これはあくまで私個人の感想であり、効果の感じ方には個人差がある点にご留意ください。
経験から言えるのは、症状が強いときにはまず強めのステロイドで炎症を抑え、その後タクロリムスに切り替えて寛解維持を行うのが最も安定した使い方だということです。かかりつけ皮膚科医からは「顔や首には強ランクのステロイドはできるだけ避けるように」と指導されますが、実際には効果が乏しいランクのステロイドを継続することも良いことではないとの考えもあり、短期間だけ強いステロイドを使い、その後にタクロリムスで維持するのが妥当だと感じています。
※注記(補足)
ステロイド外用薬には強さのランクがあり:
- 最も強い(strongest)
- 非常に強い(very strong)
- 強い(strong)
- 中くらい(medium)
- 弱い(weak)
顔や首は吸収率が高いため、通常は成人でありば中ランク(medium)が推奨されています。
7. まとめ
アトピー性皮膚炎の基本的な外用治療は、今もなおステロイド外用薬が第一選択です。炎症が強い時期にはまずステロイドで鎮め、その後に非ステロイド薬で維持するのが標準的な流れです。
その中で、タクロリムス軟膏は20年以上にわたり使われ続けてきた実績があり、
- プロアクティブ療法による寛解維持効果が確立していること
- 顔や首などデリケートな部位でも長期に安全に使えること
- マラセチアを抑える可能性があること
- ジェネリックがあり経済的負担を軽減できること
といった独自の強みがあります。
一方で、強い灼熱感や刺激感という不便さがあり、使い続ける上での壁になることもあります。近年はコレクチム軟膏、モイゼルト軟膏、ブイタマークリームなど新しい薬も登場し、患者さんに合った薬を選べる時代になってきました。
大切なのは、「どの薬が一番強いか」ではなく、個人差や生活背景に合った薬を医師と相談しながら選ぶことです。その中でも、タクロリムス軟膏は豊富な実績と独自の利点を持ち、今なお治療の主力として活躍している薬と言えるでしょう。
【参考文献】
- Ständer S, et al. Topical calcineurin inhibitors inhibit TRPV1 activation and neuropeptide release in sensory neurons. J Invest Dermatol. 2010;130(12):332–341. PubMed PMID: 20302583 ↩︎
- Thaçi D, et al. Proactive disease management with 0.03% tacrolimus ointment for children with atopic dermatitis: results of a randomized, multicentre, comparative study. Br J Dermatol. 2008;159(6):1348–1356. ↩︎
- Tacrolimus exhibits antifungal activity against Malassezia species. Dermatology and Therapy. 2025;15:1045–1062. ↩︎

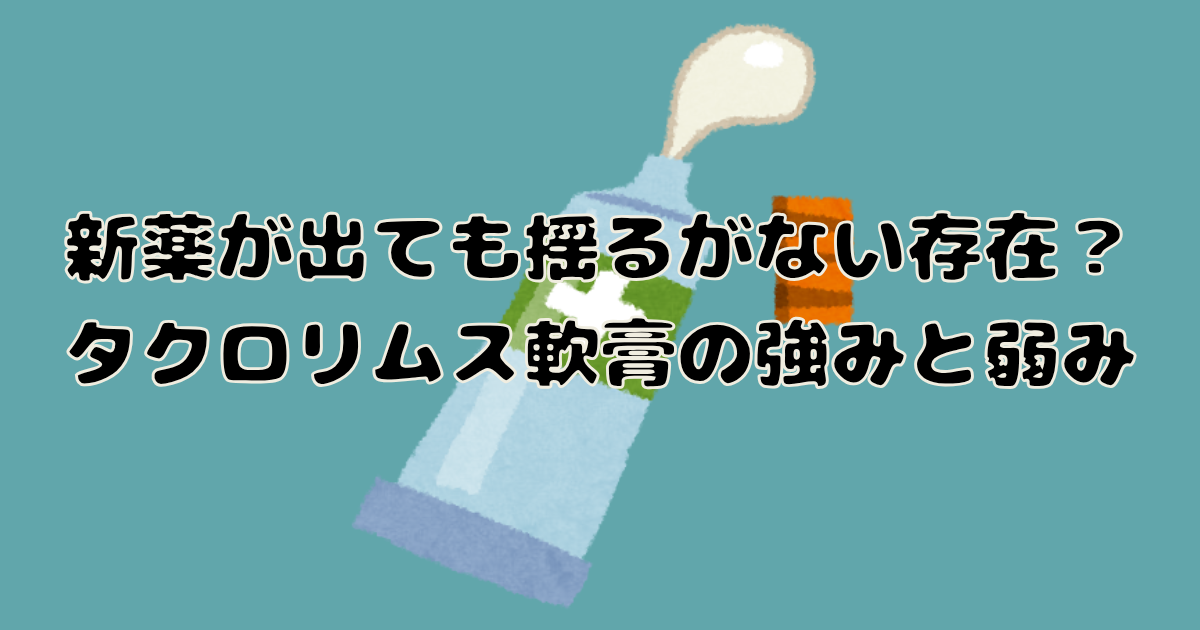
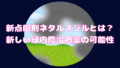
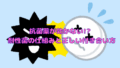
コメント