※当記事にはアフィリエイト広告を含みます。商品リンクを経由して購入された場合、当サイトに収益が発生することがあります。
1. はじめに
「漢方薬って、じっくり時間をかけて体質から整えるもの」
そんなイメージを持っている方は少なくないと思います。実際、多くの漢方薬は長期間の服用で効果を発揮する処方です。
ですが、すべての漢方が“ゆっくり効く”わけではありません。なかには数分〜十数分で効果を感じられる、いわゆる“即効性のある漢方”も存在します。
その代表格が今回ご紹介する 「芍薬甘草湯」 です。
特に「夜中に足がつって目が覚めた」「運動中に突然こむら返りが起きた」――そんな急な筋肉のけいれんに対して、この漢方が「すぐ効いた!」という声がSNS上でもちらほら見られます。
本記事では、芍薬甘草湯の特徴を“なぜこんなに早く効くのか?”という視点から解説していきます。
単なる体験談や一般論ではなく、漢方薬の構成と成分、そして作用のメカニズムに基づいた内容を、薬剤師としての視点からわかりやすくお伝えします。
2. 「漢方は時間がかかる」は本当か?
2-1. 漢方薬の治療原則
「漢方は時間がかかる」と言われる理由の一つに、西洋医学とのアプローチの違いがあります。
西洋医学は、発熱や炎症、痛みといった“目に見える症状”に対して直接アプローチする「対症療法」が主流です。たとえば、熱を下げる薬、痛みを抑える薬といった具合に、症状そのものを速やかに取り除くことを目的としています。
一方で、漢方医学は“症状の背景にある体質”や“全身のバランスの乱れ”に注目します。その人の体質や生活習慣、体の状態を見ながら、偏った状態(=未病)を整えることで、本来備わっている自然治癒力やホメオスタシス(恒常性)を引き出し、結果として症状を改善しようとするのが特徴です。
このように、漢方薬は「ヒト全体」に働きかける治療哲学をもとにしているため、どうしても“時間をかけて体質から整える薬”というイメージが先行しやすいのです。
2-2. 漢方薬には即効性もある
「漢方薬はゆっくり効くもの」というイメージを持つ方は多いかもしれませんが、実は、急性の症状に対して即効的に使われる処方も少なくありません。
たとえば、風邪のひきはじめによく使われる葛根湯。首筋のこわばりや寒気といった初期症状に対して、服用後すぐに発汗を促し、熱の進行を防ぐことを目的とします。発症初期であれば、数時間以内に効果を実感できることもあります。
さらには、鼻炎であったり頭痛であったりにも比較的即効性を示すものもあります。(ただし、著しい症状を示すものに対しては西洋医学の薬に分があったり、やはり得意不得意分野はあり)。
さらに、今回のテーマである芍薬甘草湯も、こむら返りや筋けいれんといった“今すぐなんとかしたい”急性症状に対して、数分〜十数分で効き始めることがある点で、非常に特徴的な漢方薬です。
このように、漢方薬には「時間をかけて体質改善を目指す処方」だけでなく、「急に起こる症状に素早く対応できる処方」も存在します。
つまり、漢方=長期戦というイメージだけでなく、状況に応じて使い分けられる“即効漢方”もあるという視点を持つことが大切です。
2-3. 漢方の効果は一方的なものではない
今回のテーマからは少し離れますが、漢方薬の特徴として、効果が一方向に偏らず、全体のバランスを調整するという性質もあります。これも漢方が“即効性”や“単純な薬効”だけでは語れない奥深さを持つ理由のひとつです。
代表的な例が「五苓散」です。この薬は“水毒”(水分代謝の乱れ)を改善する漢方として知られ、むくみや気圧の変化による頭痛、二日酔いなどで用いられます。そのため、「余分な水分を外に出す=利水作用がある漢方」と理解されることが多いでしょう。
ところが実際には、五苓散は風邪などによる脱水症状の初期にも使われる処方です。ここで、「水を排出する薬なのに、脱水に使うの?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。
この一見矛盾するような使い方の背景には、近年の研究によって一部メカニズムが解明されつつあります。五苓散には、「アクアポリン」と呼ばれる水の通り道に作用し、体にとって不適切な水分移動を抑制する効果があることがわかってきました。つまり、“出す”というよりも“調整する”という方向で働いており、西洋医学の「利尿剤」とは全く異なった作用をしていると言えます。
このように、漢方薬には「利水」「補水」といった単純な二元論では語れない柔軟な作用が存在します。そしてこの調整機能こそが、個々の体質や症状にきめ細かく対応できる漢方の強みでもあります。
まだ科学的に完全に説明がついていない作用もありますが、今後の研究の進展により、漢方の効果の裏付けがさらに進むことで、医療現場での活用が広がっていくことが期待されています。
3. こむら返りとは?
芍薬甘草湯に関しての説明をする前に、まずその治療対象の病態であるこむら返りに関し簡単におさらいしておきましょう。
3-1. 概要
「こむら返り」とは、ふくらはぎ(腓腹筋)を中心とした筋肉が突然強く縮こまり、激しい痛みをともなう状態のことをいいます。夜中に突然足がつって目が覚める――そんな経験がある方も多いのではないでしょうか。医学的には「有痛性筋痙攣」と呼ばれています。
こむら返りには、運動に伴い生じるものと、はっきりとした原因疾患がないまま夜間などに繰り返し起こるタイプがあります。本記事では、芍薬甘草湯の効果が期待される後者、すなわち「夜間こむら返り」や突発的な筋肉けいれんに焦点をあてて解説していきます。
3-2. 原因
こむら返りの詳しい原因は、実はまだ完全には解明されていません。ただし、いくつかの要因が関係していると考えられています。
その一つとして、筋肉が縮みすぎたり伸びすぎたりしないよう、普段から微調整をしている“筋肉調整システム”があります。ところが、何らかの要因でこの調整システムがエラーを起こしてしまうことにより、本来不要なタイミングで筋肉が急に収縮してしまうことが、こむら返りの主な原因の一つと考えられています。
そのエラーの原因としては、以下のような状況が誘因となることがあります
- 長時間の立ち仕事や運動による筋肉の疲労
- 睡眠中の脱水や血行不良
- 電解質(カリウム・マグネシウムなど)のバランスの乱れ
3-3. 症状
代表的な発症部位としては、ふくらはぎに突然強い痛みを伴う収縮が起き、足の裏や太もも、足の指に起こることもあります。
発作が起こると、筋肉が勝手にギュッと縮まり、足がつま先立ちのような状態(=足首が下に反る)になったり、足の指が丸まって内側に曲がるような形になることが多いです。これは、発作時の典型的な動きであり、医学的には「足の底屈」や「足趾の屈曲」と呼ばれています。
発作は数秒〜数分で自然に治まりますが、再発することもあり、治まったあとに筋肉痛のような鈍い痛みや張り感が残る場合もあります。
3-4. 予防・対策法
こむら返りが起きたときは、縮こまった筋肉をゆっくり伸ばすストレッチが基本です。ふくらはぎの場合、つま先を手前に引き寄せるようにすると、筋肉が伸びて痛みが和らぎます。
また、こむら返りの発症予防としては、以下のような対策が主に取られます
- 長時間同じ姿勢を取らないようにし、血行不良を防ぐ
- 就寝前に軽くストレッチをする
- 水分・電解質(特にマグネシウムやカリウム)を意識して摂取する
- 足を温めて血流を良くする
4. 芍薬甘草湯の構成と即効性
芍薬甘草湯は、わずか2種類の生薬――芍薬と甘草――のみで構成されている非常にシンプルな漢方薬です。
このような“構成が簡潔な処方”は、臨床現場においては「即効性がある」と評価されることがあり、芍薬甘草湯はその代表格といえるでしょう。特に、こむら返り(筋痙攣)などの急性症状に対し、「服用後数分程度で効果を感じた」という報告もしばしば見られます。
なぜ、芍薬甘草湯はここまで速やかに作用するのでしょうか。まだ明確にそのメカニズムが解明されてはいませんが、考えられる理由の一つとして、「生薬の数が少ないことによる薬物動態の単純さ」が挙げられます。
漢方薬では、生薬の種類が多くなるほど、それぞれの成分が体内で吸収・代謝される過程が複雑になり、成分同士が酵素や輸送担体を奪い合ったり、互いに作用を妨げ合ったりする可能性が高まります。このような相互作用によって、結果的に薬効成分の吸収が遅れる、あるいは作用発現が不安定になることも報告されています[1]。その点、芍薬甘草湯のように構成がシンプルな処方では、生薬間の競合が少ない分、各成分がよりスムーズに吸収・作用しやすいと考えられます。
さらに、即効性には芍薬に含まれる有効成分「ペオニフロリン」が大きな鍵を握っている可能性があります。その理由については、次の章で詳しく説明します。
5. 芍薬 〜筋肉をゆるめる中核成分〜
芍薬(シャクヤク)は、ボタン科の植物の根を乾燥させた生薬で、古くから多くの漢方薬に配合されてきました。「立てば芍薬、座れば牡丹…」という言葉の通り、女性のたとえとしても使われるように、芍薬はとくに婦人薬としての用途が多く、緊張やイライラなど、“気が立っている”状態に効果があるとされています。
しかし芍薬の価値は、そのイメージだけではありません。とくに注目すべきなのは、筋肉の異常な収縮やけいれんを和らげる薬理作用です。これに深く関与するのが、有効成分ペオニフロリン(paeoniflorin)です。
ラットを用いた薬物動態試験では、ペオニフロリンは投与後わずか5分で血中の最高濃度に達したとされています[2]。この極めて早い吸収スピードが、芍薬甘草湯の「即効性」を裏付けていると考えられます。
さらに、ペオニフロリンは腸内細菌により代謝されてペオニメタボリンⅠへと変化し、こちらも強い薬理作用を持つことがわかっています。この代謝産物は、最高濃度に達するまでに逆に長時間を要し、即効性だけでなく持続性にも寄与している可能性があります。
芍薬は、こうした“速効性+持続性”の両面を持ち合わせた、生薬として非常に優れた特性を持つ存在なのです。
6. 甘草の働き 〜痛みの感覚と炎症をなだめる〜
甘草(カンゾウ)は、マメ科カンゾウ属植物の根や根茎を乾燥させたもので、その名の通り強い甘みを有しています。私たちがよく口にするお菓子などの食べ物にもよく使用されます。
甘草の効能効果としては、その甘みを司る成分「グリチルリチン」に由来し、それが痛みや炎症を抑える効果として期待できます。
動物を用いた研究では、グリチルリチンを内服または注射した群で、化学物質による痛み反応が有意に減少したことが報告されています。
これは、痛み信号を伝える神経に働きかけることで、「痛みを感じにくくする」効果があるためで、こむら返りのような筋肉けいれんによる鋭い痛みの初期緩和に有効と考えられます。
さらにグリチルリチンは、炎症の原因となる物質(TNF‑α、IL‑6、COX‑2など)の生成を抑制する作用が示されています。また、細胞や組織の炎症反応を誘導する酵素やシグナル伝達経路(例えばNF‑κB経路)もブロックすることが報告されています。このため、筋肉が収縮した後の“炎症性のズキズキ感”や“組織の腫れ”を和らげる働きが期待できます。
7. 芍薬甘草湯の正しい使い方
7-1. 使用してはいけない人
以下のような状態にある方は、芍薬甘草湯の服用により症状を悪化させるおそれがあるため、使用は禁忌とされています。それぞれの理由については、次項「注意事項」で詳しく解説します。
- アルドステロン症の患者
- ミオパチーのある患者
- 低カリウム血症のある患者
7-2. 効能効果
漢方薬では一般に、「証」と呼ばれる体質やその時の体調などを重視して処方を選択しますが、芍薬甘草湯は急性の症状に対して使われることが多く、症状が適合していれば比較的多くの人に効果が期待できる処方です。
具体的には芍薬甘草湯は、以下のような急激に発症する筋肉のけいれんや痛みに対して用いられる漢方薬です。
- 筋肉のけいれんを伴う急な疼痛
- 筋肉痛・関節痛
- 胃痛・腹痛
また注目すべき点として、芍薬甘草湯は筋肉のけいれんに限らず、胃痛や腹痛など、消化管に由来する痛みにも効果があるという点が挙げられます。
西洋医学における鎮痛薬としては、ロキソニン®︎などのNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)が代表的ですが、これらは消化管の痛みには基本的に使用されません。むしろNSAIDsは胃粘膜障害のリスクがあり、胃痛を悪化させることもあります。そのため、消化管の痛みに対しては、主にブスコパン®︎などの鎮痙薬が用いられます。これらは腸管平滑筋の異常な収縮を抑えることで、けいれん性の腹痛を和らげます。
こうした背景を踏まえると、芍薬甘草湯が筋肉・関節の痛みに加えて、消化管の痛みにも対応できる点は大きな特長であり、“万能型の痛み止め”としての一面を持つ処方といえるかもしれません。
7-3. 応用的な使用法
芍薬甘草湯は、単なる筋肉痛やおなかの痛みだけでなく、医療現場で以下のような症例にも応用されることがあります
- 透析中や肝機能障害を有する方のこむら返り
- しゃっくり(横隔膜のけいれん抑制)
- 月経痛※1、神経痛、坐骨神経痛
- 尿路結石の発作
7-4. 用法用量
7-4-1. 一般的な用法用量
芍薬甘草湯の一般的な服用法は、1回1包(約2.5g)を1日2〜3回、空腹時(食前や食間など)に服用します。
なお、医療機関で処方される漢方薬と、市販(OTC)で販売されている漢方薬では、生薬の含有量に差があります。多くの場合、OTC漢方薬は処方薬の「半量」であることが多く、芍薬甘草湯においても市販薬では1回分に約1.25gのエキスが含まれている製品が主流です。
ただし、市販品のなかには「満量処方」といって、医療用と同等量のエキスを含む製品もあります。例としては葛根湯などが挙げられます。用量にこだわる時は、製品の成分表示をしっかり確認しましょう。
7-4-2. こむら返りに対する用法用量
今回のテーマである「こむら返り」に対して服用する時は、大きく分けて2パターンあります。寝る前にあらかじめ飲む場合と、発作時またはその予兆があった際にすぐ飲む頓服の場合です。
- 就寝前にあらかじめ服用する場合(予防的使用)
こむら返りは、夜間や早朝などの睡眠中に起こることが多いため、「寝る前に予防的に服用する」という方法がしばしばとられています。芍薬甘草湯の持続時間はおよそ4〜6時間と言われており、就寝前に1包を服用することで、睡眠中の発作を予防する狙いがあります。
また、漢方薬は白湯で服用することが基本とされており、服用時の(夜間の排尿が増えないように適量)水分補給が、こむら返りの一因とされる軽度の脱水状態を改善するという点でも、理にかなった使い方といえます。
ただし、この使用法に対する明確なエビデンス(予防効果を示す臨床研究など)は現時点で調べた限りでは乏しいようであり、効果を実感できないケースもあるかもしれません。特に早朝に発作が集中する場合には、薬効が持続しない可能性も考えられます。 - 発作時またはその前兆があった際に飲む場合(頓服)
芍薬甘草湯は漢方薬の中でも比較的「即効性」が期待できる処方として知られており、こむら返りが起きた際、あるいは違和感など前兆があったタイミングで服用する、いわゆる「頓服的な使い方」が実際の医療現場でも広く行われています。
特に夜間に発作が起こりやすい場合には、枕元に薬と飲料水(白湯など)を準備しておき、症状が出たらすぐに服用できるようにしておくと安心です。
なお、予防的に寝る前に服用しても効果が不十分な場合は、医師と相談のうえ、頓服での使用方法に切り替えることも選択肢として検討されます。
8. 芍薬甘草湯の注意事項
漢方薬は自然由来であることから「副作用がない」「安心して飲める」といったイメージを持たれがちですが、必ずしもそうとは限りません。特に芍薬甘草湯に含まれる「甘草」は、ある特有の副作用に注意が必要です。
8-1. 偽アルドステロン症
甘草に含まれるグリチルリチンという成分は、体内でステロイド様の作用を示すことがあり、血圧上昇やむくみ、低カリウム血症などを引き起こす『偽アルドステロン症』を誘発することがあります。
この副作用は、一般的には甘草の摂取量が多いほど発症リスクが高くなる「用量依存性」があるとされており、1日2gを超えるような処方では注意が必要です。また、4gを超えるとリスクはさらに高まり、6gでは10%以上の頻度で発症する可能性も報告されています[3]。
しかし一方で、少量でも発症する例があり、これは個人の体質や高齢・便秘・栄養状態など複数の因子が影響していると考えられています。そのため、「少ない量だから大丈夫」とは限らず、服用中に「血圧が急に上がった」「倦怠感が強い」「むくみやすい」などの症状があれば、早めに医師や薬剤師に相談することが大切です。
8-2. 低カリウム血症
甘草によるもう一つの重大な副作用として、「低カリウム血症」が挙げられます。これは、甘草に含まれるグリチルリチンという成分が、体内のホルモンに影響を与え、カリウムが体の外に出やすくなることで起こります。結果として、血液中のカリウム濃度が下がってしまうのです。
主な症状としては、筋力の低下(いわゆるミオパチー)、手足のしびれや麻痺、さらには不整脈などが挙げられます。カリウムが少し足りない程度では自覚症状がないことも多いですが、逆に言えば、何らかの症状が出た段階ではすでに重篤な状態である可能性があると考えたほうがよいでしょう。
グリチルリチンに関しては、一般的に1日100mg(甘草換算で2.5g)が安全な上限量の目安[4]とされており、これを超えての長期使用はリスクが高まります。また、甘草を含む漢方薬は数多くあり、複数の漢方を併用している場合は知らないうちにグリチルリチンの摂取量が増えている恐れがあり、特に注意が必要です。
また、カリウムを排出しやすいタイプの利尿剤(フロセミドなど)併用時も、低カリウムになりやすいため、念のために医師や薬剤師と相談した方が良いでしょう。
9. ネットでの購入も可能
芍薬甘草湯をはじめとする多くの漢方薬は「第2類医薬品」に分類されており、平成26年の制度改正以降、インターネットでも購入できるようになりました。忙しくて薬局に行く時間がない方や、近隣にドラッグストアがない地域の方でも、現在ではAmazonなどの通販を通じて比較的容易に手に入れることが可能です。
ただし、市販されている漢方薬は一部を除き「半量処方」が基本であり、医療用製剤と比べると含有成分量は半分に設定されています。このため、効果を期待する際にはその点を理解しておくことが大切です。
他の市販漢方薬と同様に(1日の総量に換算し)半量処方ですが、1日の服用回数が医療用では3回であるのに対し、本剤では2回に設定されています。結果として1包あたりの有効成分量は医療用の約7割に相当し、半量処方でありながら市販薬でも比較的しっかりとした設計になっています。
10. さいごに
「漢方はゆっくり効くもの」——そうしたイメージを持つ方は少なくありません。
けれども、今回ご紹介した芍薬甘草湯のように、“すぐに実感できる漢方”も確かに存在します。
シンプルな構成と、筋肉の異常収縮に働きかける有効成分。
そして、数分程度で効果を感じることがあるという、漢方としては少し意外な即効性。
もちろん、漢方薬であっても副作用や相互作用のリスクはゼロではありません。甘草による低カリウム血症や偽アルドステロン症など、体質や併用薬によっては注意すべき点もあります。
だからこそ、漢方も「自然のものだから安心」と思い込まず、薬剤としての側面にも目を向けて正しく使うことが大切です。メカニズムからしても、しっかりとした科学的な根拠があって効いているのです。
芍薬甘草湯は、「足がつったときにすぐ効いた」という経験から漢方に興味を持つきっかけになることも多い処方です。
今回の解説が、そんな“気になる漢方薬”の背景を少しでも深く知る手助けになれば幸いです。
【参考資料・文献】
- Sun X, et al. Influence Factors of the Pharmacokinetics of Herbal Resourced Compounds. Curr Drug Metab. 2019. ↩︎
- 医薬品インタビューフォーム「ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)」 ↩︎
- 萬谷直樹, 山口康三, 鈴木堅二. 甘草の使用量と偽アルドステロン症の頻度に関する文献的調査. 日本東洋医学雑誌. 2015;66(3):197–202. ↩︎
- 「Liquorice – Side effects and interactions」. Prescriber Update, Vol.40(4), December 2019. ↩︎

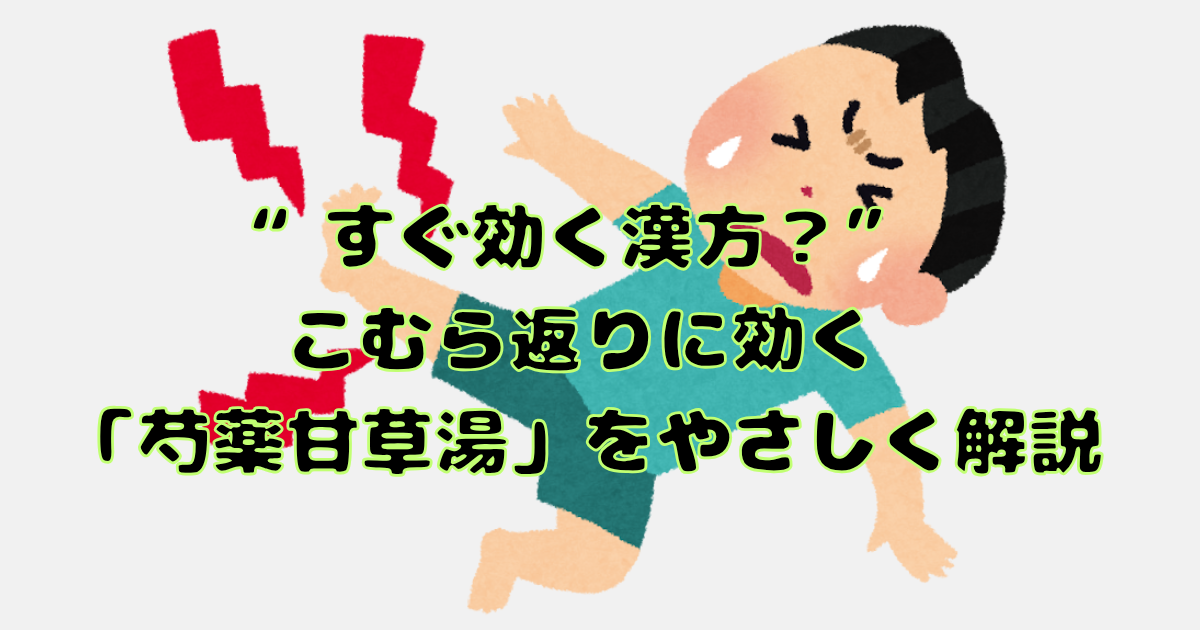
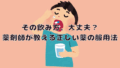
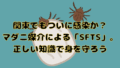
コメント