7. 追記(2025年12月20日)
1. はじめに
2025年5月、財政制度等審議会において、いわゆる「OTC類似薬」を医療保険の対象から外すという提案がなされ、医療現場を中心に大きな注目を集めています。
OTC類似薬とは、市販薬(OTC薬)と同一または類似の有効成分や効能を持つ処方薬のことを指し、例えばアレルギー薬のフェキソフェナジン(アレグラ®︎)や、痛み止めのロキソプロフェン(ロキソニン®︎)、(漢方薬も?)などが該当します。これらは、医師の処方に基づいて現在も保険適用となっており、多くの患者が1〜3割負担等で利用しています。
これらの薬に関する費用の全額または一部を、現在適用している健康保険から外すことで、任意の患者が10割負担をすることになります。
このような見直しの動きは、突如として出てきたものではなく、以前から医療費の適正化や軽症患者の自己負担の在り方をめぐって繰り返し議論されてきた経緯があります。今回の提案は、そうした過去の議論を踏まえて、ついに具体的な制度改正の方向性が文章として示された形といえるでしょう。
次章では、財務省が提案した具体的な制度変更の内容と、その背後にある狙いについて整理していきます。
2. 財務省の提案内容とその狙い
2025年5月、財政制度等審議会において財務省が示した提案では、保険診療の対象となっているOTC類似薬の取り扱いを見直し、原則として保険給付の対象から除外するという方針が示されました。
この提案には、2つの具体案があります。
2-1. 2つの具体案
この両案について、現実的な制度設計としては、「選定療養」の枠組みを用いてOTC類似薬に限定的な自己負担を求める形(案②)が、有力な選択肢と推測されます。案①に関しては、本来の目的である「医療の平等性」といった観点からしても、現実にはかえって不合理な状況を生むためです。
① 全面自己負担案(保険給付除外)
OTC類似薬を処方された場合、その薬剤費だけでなく、調剤基本料や技術料といったすべての費用が自己負担になるという案です。この場合、保険診療の枠組みから完全に外れることになります。
同案の根底には「混合診療の原則禁止」というルールがあり、保険適用の薬と適用外の薬を同時に処方できないという制度上の制約が、この全面自己負担の考え方につながっています。このルールは、診療の質を保ち、医師と患者との情報格差によって不必要な自由診療が行われるリスクを防ぐために設けられています。
② 保険外併用療養費制度の活用案(選定療養化)
もう一つの案は、OTC類似薬を「選定療養」として扱う方法です。これは、「薬剤費」部分のみを患者が全額負担し、診察料や調剤料などその他の費用は保険適用のまま残すという考え方です。
選定療養は、差額ベッド代や時間外診療と同じように、特定の条件下で混合診療を認める制度であり、患者負担を軽減しつつ制度の柔軟性を確保する目的があります。
2-2. 財務省の狙い
「OTC類似薬の保険適用除外」は、単なる医療費の削減策と思われがちですが、その背景にはもっと大きな目的があります。
財務省は、「国民皆保険制度を未来にわたって維持していくためには、軽い症状には自分で対処する“セルフケア”を進めるべきだ」との方針を示しています。つまり、「軽症の人も重症の人も平等に税金を使う」これまでのやり方を見直し、「本当に医療が必要な人にこそ保険を集中させよう」という考え方です。
そのためには、薬局で買えるような市販薬と似た効果のある薬にまで保険を適用するのではなく、そうした軽症の治療は患者自身の負担で対応してもらおう、というわけです。いわば、「自助・共助・公助のバランスをとる」という思想に基づいた提案なのです。
さらにもう一つ、財務省は「創薬イノベーション(新薬開発の促進)」も重要視しています。限られた医療財源を、すでに市販薬で代用できる薬ではなく、がんや難病など“今まさに新しい治療が求められている分野”に回したいという狙いもあるのです。今後は「費用に見合った効果がある薬しか保険で使えなくなる」方向性(費用対効果評価の本格導入)も視野に入っており、今後ますます“保険が使える薬”の範囲は厳密に見直されていく可能性があります。
3. 医療業界の反応
2025年5月に財務省が示した「OTC類似薬の保険適用除外」案は、医療現場に大きな波紋を広げています。これに対して、医師会や薬剤師会などの医療関係団体からは「患者の負担が増えすぎるのでは」「必要な医療が受けられなくなるのでは」といった声が上がっています。
また、ネット上でも「財政再建は必要だが、やり方が乱暴では?」という懸念から、「軽い症状は自費でいいのでは?」という肯定的な意見まで、さまざまな声が見られます。
ここでは、特に現場で患者と向き合う医師や薬剤師がどのように受け止めているのか、その反応を見ていきます。
3-1. 医師会の意見
財務省による「OTC類似薬の保険適用除外」案に対して、日本医師会は慎重な姿勢を示しています。背景には、日本が世界に誇る「国民皆保険制度」の理念──すべての国民が必要な医療を公平に受けられる仕組み──を揺るがしかねないという強い危機感があります。
- 受診控えによる健康被害:軽微な症状でも医師の診断を受けることで、重大な病気の早期発見につながる場合があります。保険適用が除外されると、患者が自己判断で市販薬を使用し、適切な治療を受けられずに重篤化する可能性があります。
- 経済的負担の増加:保険適用が除外されることで、患者の自己負担が増加し、特に経済的に厳しい状況にある人々が医療を受けにくくなる懸念があります。
- 薬の適正使用の難しさ:医師の指導なしに市販薬を使用することで、薬の誤用や副作用のリスクが高まる可能性があります。
一方で、医師の中には、軽微な症状に対する医療資源の集中を避け、重症患者への対応を強化するために、一定の保険適用除外が必要と考える意見もあります。
3-2. 薬剤師会の意見
日本薬剤師会は、OTC類似薬の保険適用除外に対して慎重な姿勢をとっています。岩月進会長は2025年5月の会見で、「金額ありきでの議論はあまりに乱暴であり、医療アクセスや患者の安全性を軽視するものだ」と強く懸念を示しました。また、4月には「保険外しの議論は専門家の意見をないがしろにしている」とも発言しており、医療現場の実態を無視した制度改正への警戒感がうかがえます。
薬剤師会としては、医療費の適正化は必要としつつも、拙速な保険給付の見直しではなく、患者の安全や医薬品アクセスの確保を第一に考えるべきという立場を取っています。
4. 患者への影響
4-1. 患者負担額増の可能性
今回の保険適用除外の方針により、これまで通り医療機関を受診して“OTC類似薬”を処方薬として受け取る場合、患者の自己負担は確実に増加します。診察料に加えて、調剤料や薬剤服用歴管理指導料などが発生するため、今までよりもコストは高くなり、通常の患者にとっては負担増は制度上避けられません。
そのため、「症状が軽いもしくは変わらないなら病院に行かず薬局で直接買えばいい」と考える人が増えるのは自然な流れです。OTC医薬品として購入する場合は、医療機関や調剤薬局で発生していた各種手数料がかからず、総支出を幾分か抑えることはできます。
さらに、継続的に使用しなくてはいけない薬において、医療用の薬価と市販薬の価格差が大きい場合は相当な負担が考えられます。例えばアトピー性皮膚炎患者に際しては、ヘパリン類似物質などの保湿とステロイド外用薬は欠かせないものです。これらの中でも、特にステロイド外用薬の一つベタメタゾン吉草酸エステル(リンデロンV®︎など)に関しては、症状によっては大量にかつ長期使用するケースもあり、その場合は相当な負担となるでしょう。
4-2. 助成対象者への影響と今後の課題
なお、今回の制度変更が仮に生活保護受給者や医療費助成の対象となる高校生以下にも適用された場合、これらの方々も対象医薬品の購入費用を全額自己負担することとなり、OTCとしての購入を余儀なくされる可能性があります。経済的に余裕のない世帯や、子育て中の家庭、1割負担の後期高齢者等にとっては深刻な打撃となりかねず、生活に直接的な影響を及ぼすことも考えられます。
ただし、現状公表されている財務省の提案資料には、こうした助成対象者に対しても保険適用外とする明確な記載は確認されていません。あくまで“可能性の段階”であることを踏まえつつも、最低限の医療アクセスが必要な層に対しては、例外的な措置や柔軟な対応が今後の議論で検討されるべきでしょう。
4-3. セルフケア時代への転換期
これは、セルフケアやセルフメディケーションの推進という観点からは大きなチャンスとも言えます。受け身で医療を受ける時代から、自分の健康に主体的に関わる時代への転換点とも言えます。自分の体と向き合い、必要な判断をする力──すなわち「ヘルスリテラシー」が重要になるという点です。これが高まることで、徐々に増えつつある生活習慣病の予防や大病の回避にもつながり、将来的には医療費全体の削減にも貢献することができるようになるかもしれません。
この制度変更は、OTC医薬品をどう使い分け、どのタイミングで受診すべきか——その判断において、薬剤師が担うべき役割は今まで以上に重くなります。そのためにも、早急などの地域も漏れがなくかつ適正な体制づくりが求められます。制度だけを整えても、現場が追いついていなければ意味はありません。薬剤師の専門性が、真に患者の安心に繋がる仕組みが必要です。
5. 諸外国の費用対効果評価の活用
日本では、厚生労働省が認めた医薬品は基本的にすべて保険が使えるのが当たり前になっています。ですが、世界に目を向けてみると、必ずしもそうではありません。
- アメリカの例
アメリカでは、すべての薬が保険適用されるわけではなく、保険会社や公的プログラム(メディケア・メディケイド)ごとにカバーされる薬が異なります。特に新薬は高額になりやすく、加入している保険プランによって価格が大きく変わるのが特徴です。
最近では、薬の費用対効果を評価する動きが強まり、ICERが薬の効果と価格のバランスを評価し、保険会社が適用を決める際の参考にしています。また、フォーミュラリー(薬剤リスト)によって保険適用の薬が選定され、含まれない薬は自己負担が大きくなることがあります。 - イギリスの例
「その薬、本当にお金をかける価値ある?」という視点で専門機関(NICE)が評価します。この評価では、患者さんがその薬でどのくらい健康に長生きできるか、それにかかる費用は妥当か、といった「コスパ」を見ます。そのうえで、効果に見合った金額なら保険適用に、そうでなければ適用外になることもあります。 - ドイツの例
「これまでの薬より、どれだけ効果が上がるか?」という“追加の効果”に注目して、保険で使えるかどうかや価格を決めています。
こうした仕組みを持つ国々では、「なんでもかんでも保険で」という考え方ではなく、「限られたお金を、より効果的な薬に使おう」という発想が基本になっています。
日本でも今後、すべての薬が保険でカバーされるのではなく、「本当に必要なものを見極める」動きが強まっていくかもしれません。
6. さいごに〜薬剤師として私的な視点から
あくまで個人的な意見ですが、今回の制度改正については、一時的に患者負担が増える面があるとはいえ、医療制度全体を俯瞰すれば非常に意義のある取り組みであり、私は賛成の立場を取ります。もちろん、それを実現するためには制度面・体制面を含め、解決すべき課題も早急に対応しなければいけません。
以下は、主に薬剤師の立場および薬局現場に向けた私見です。
制度や体制が不十分という声もありますが、整備を待っていてはいつまでも始まりません。むしろ、始めるからこそ制度も育ちます。薬局はこれまでも「地域包括ケア」や「健康サポート薬局」などの取り組みを通じて地域医療の一翼を担ってきました。今回のスイッチOTCも、その延長線上にあると考えます。
「医師と薬剤師の役割が曖昧になるのでは」という指摘もありますが、スイッチOTCは軽症・自己判断可能な症状への対応が前提です。薬剤師がトリアージ(受診勧奨かOTC対応か)を担うことで、医師の診察が本当に必要な人へ資源を集中できる体制を支えることができます。薬剤師は“医師の代わり”ではなく、“医師につなぐ橋渡し役”であり、それこそが本来の職能です。
さらに、かかりつけ薬局でのOTC購入時に予防や重症化の兆候を早期に見抜くことができれば、結果的に医療費の抑制や健康寿命の延伸にもつながります。医療費の適正化という国の最重要課題に対しても、薬剤師が貢献できる絶好の機会だと捉えるべきでしょう。
セルフケア・セルフメディケーションの推進は、薬剤師が地域で真価を発揮するためのステージです。制度の未整備を嘆くよりも、「薬剤師が介在することで、OTCの安全な使用を支える体制」を自ら築いていく——それが、今後求められる姿勢だと私は考えます。
7. 追記(2025年12月20日現在)
その後の議論を経て、当初財務省が示していた「OTC類似薬の保険適用除外(いわゆる保険外し)」については、全面的な保険外しは見送られる方向となりました。
現在は、自民党と日本維新の会の間で、OTC類似薬については保険適用を維持したまま、薬剤費の4分の1(25%)を患者が追加で負担するという仕組みで合意がなされています。
報道によれば、当初、日本維新の会は、約7,000品目あるとされるOTC類似薬のすべてを保険適用から除外する案を主張していました。しかし、自民党側が難色を示したことから、最終的には保険適用は維持したまま、一部の薬剤について追加負担を求める形で折り合うこととなりました。
その結果、今回新たな負担の対象となるOTC類似薬は、77成分・約1,100品目に限定され、湿布薬や胃腸薬、アレルギー薬など、日常的に処方される頻度の高い薬剤が含まれるとされています。対象範囲は限定的ではあるものの、患者への影響が無視できない規模であることは明らかです。
一方で、合意書には、子どもや慢性疾患を抱える患者、低所得者、入院患者などについては配慮を検討する旨も明記されました。会談後には、「こうした点については今後も丁寧に議論していきたい」との発言もあり、すべての患者に一律で追加負担を求める制度とはしない方向性が示されています。
なお、この「25%」という負担水準は、すでに導入されている特許切れ医薬品(長期収載品)における患者負担増と同じ数値であり、医療費適正化の文脈では既存制度を踏まえた設定といえます。
OTC類似薬をめぐる議論は、保険から切り離すか否かという二者択一ではなく、どこまでを医療保険で支え、どこからを自己負担とするのかという現実的な調整段階に入ったといえるでしょう。
追記の追記(12月24日現在)
今回の追加負担の対象薬として、アレルギー薬のフェキソフェナジン(アレグラ®)や鎮痛薬のロキソプロフェン(ロキソニン®)など、具体的な薬剤名が一部報道で挙げられています。これを受け、ネット上では「この程度の薬を対象にしても医療費削減にはつながらない」「長期的に使用している患者への影響が大きすぎる」といった否定的な声が目立ちました。
しかし、今回の見直しは、個々の薬剤の価格や使用頻度そのものを問題視したものではなく、医療保険がどこまで公的に支えるべきか、そしてどこからを自己負担とするのかという“制度の構造”に関わる議論の一環として捉える必要があります。特定の薬剤を狙い撃ちにした制度変更ではなく、OTCで代替可能な医薬品について、保険の関与のあり方を再整理する流れの中に位置づけられるべきものです。
また、今回の合意内容には、慢性疾患や長期治療が必要な患者、子ども、低所得者、入院患者など、医療アクセスに配慮が必要な層への特別な扱いを検討する旨が明記されています。すべての患者に一律で追加負担を求める制度ではない点は、議論の理解において重要なポイントです。
今回の議論は、「痛み止めをどう扱うか」という個別論に矮小化すべきではなく、国民皆保険制度を持続可能な形で次世代へ引き継ぐために、医療保険の役割分担をどのように再設計するかという、より大きな文脈の中で捉える必要があります。

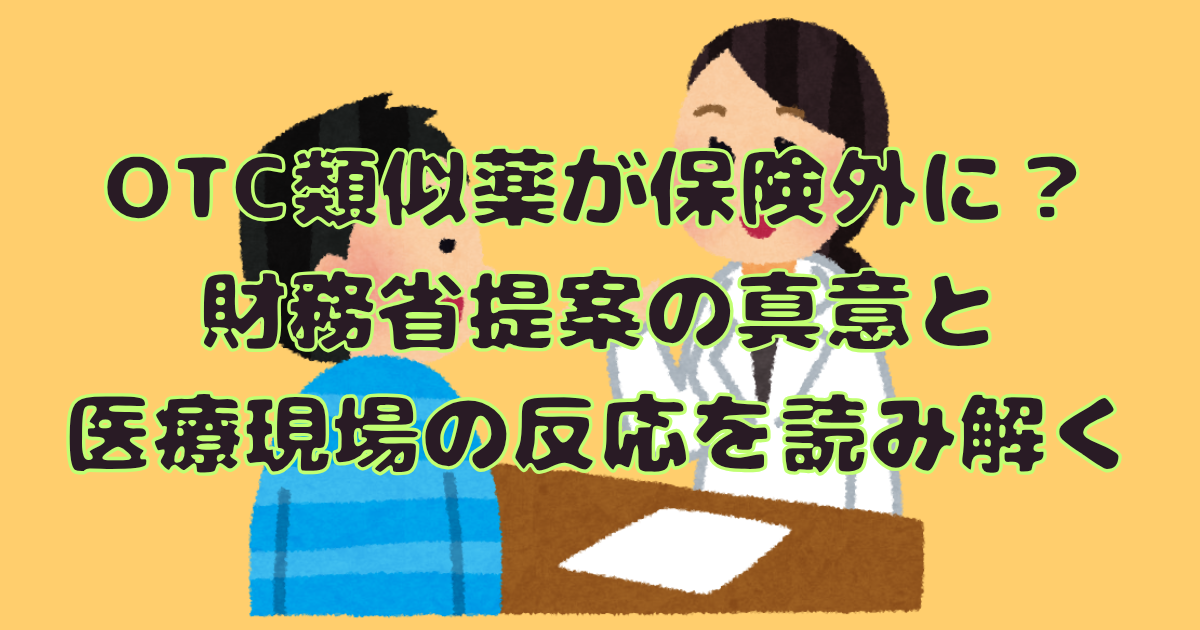
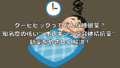
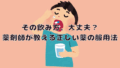
コメント
はじめまして
この下の内容は厚労省か財務省のpdfにありますか?
またはニュース記事でしょうか?
「さらにもう一つ、財務省は「創薬イノベーション(新薬開発の促進)」も重要視しています。限られた医療財源を、すでに市販薬で代用できる薬ではなく、がんや難病など“今まさに新しい治療が求められている分野”に回したいという狙いもあるのです。今後は「費用に見合った効果がある薬しか保険で使えなくなる」方向性(費用対効果評価の本格導入)も視野に入っており、今後ますます“保険が使える薬”の範囲は厳密に見直されていく可能性があります。」
はじめまして。ご質問ありがとうございます。
ご指摘の内容については、2025年5月に財務省が公表した報告書(P72~73)を参考にしております。
そこでは、限られた財源をより必要性の高い医療(難病、新薬開発など)に振り向けるべきという考え方が示唆されており、「創薬イノベーションの促進」も重要視されていると個人的に読みとりました。
該当資料はこちらでご確認いただけます:
https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics_fy2025/20240423-01.html
[…] 日本経済新聞 – 自公維、26年度からOTC類似薬見直しで合意 OTC類似薬が保険外に?財務省提案の真意と医療現場の反応 全日本民医連 – OTC類似薬の保険適用除外に断固反対する声明 […]