1. ニキビの原因
主には以下の3つが主要因となります:
- ①皮脂の過剰分泌: ホルモンバランスの乱れやストレス、食生活などにより皮脂腺が過剰に皮脂を分泌します。
- ②毛穴のつまり: 皮脂や古い角質が毛穴に詰まり、角栓を形成します。これにより毛穴が閉塞し、皮膚表面に炎症が起こりやすくなります。
- ③アクネ菌の増加: 毛穴の詰まりによって酸素が不足すると、ニキビの原因菌であるアクネ菌が繁殖しやすくなり、炎症を引き起こします。
これらの要因が複合的に作用し、最終的にニキビを形成します。特に、皮脂の過剰分泌と毛穴の詰まりがアクネ菌の増殖を助長し、炎症を悪化させる主要因となります。
2. アクネ菌とは
本来アクネ菌は皮膚に必要な菌の一つであり、健康な皮膚の状態を維持する役割があります。しかし、過剰に増殖すると皮脂の分解を促し、炎症を引き起こすことがあります。したがって、アクネ菌の必要以上の増加を抑えることが重要です。
アクネ菌は、皮膚の常在菌の一つであり、健康な皮膚の状態を維持する役割があります。この菌は皮脂を分解し、皮膚のpHバランスを保つなどの機能を果たします。しかし、過剰に増殖すると、皮脂の分解産物が毛穴に炎症を引き起こす原因となり、ニキビの発生に繋がります。そのため、アクネ菌の過剰な増殖を抑えることが、ニキビ予防において重要です。
アクネ菌は「通性嫌気性菌」であり、酸素が少ない環境を好みます。毛穴が詰まり、酸素が届かない状態になると、アクネ菌が繁殖しやすくなります。これを防ぐためには、毛穴の詰まりを防ぐことが重要であり、特に女性の場合、化粧をしっかり落とすことが予防の基本となります。
さらに、アクネ菌は皮脂を栄養源とするため、皮脂の分泌が多い肌では増殖しやすくなります。したがって、皮脂の過剰分泌を抑えるための洗顔やスキンケアが、ニキビ予防において重要な役割を果たします。適切なスキンケアにより、皮脂バランスを整え、アクネ菌の繁殖を防ぐことが効果的です。
3. 正しいスキンケアの方法
適切なスキンケアは、ニキビ対策において極めて重要です。ただし、過剰な洗顔やピーリングなど、肌への刺激が強いケアは逆効果となることがあります。過剰に皮脂を取り除くと、肌が乾燥し、その結果として皮脂の分泌が過剰に促進され、ニキビが悪化することがあるため注意が必要です。
そのため、洗顔には洗浄力がやさしい低刺激の洗顔料を使用し、肌に必要な油分を取りすぎないようにすることが大切です。特に、敏感肌や乾燥肌の方は、洗顔後の肌の状態に応じて適切な保湿を行うことが、肌のバリア機能を保ち、ニキビの炎症を和らげる効果があります。
具体的には、1日1〜2回の洗顔が推奨されます。朝は夜の寝汗や皮脂を優しく洗い流し、夜は日中の汚れや化粧をしっかりと落とすことが重要です。また、洗顔後にはすぐに保湿を行い、肌を潤すことで、乾燥による皮脂の過剰分泌を防ぎます。適切な保湿ケアを続けることで、肌のバリア機能を強化し、ニキビの発生を予防することができます。
4. 食生活やストレスとニキビとの関係性
4-1. 食生活とニキビの影響
食生活は、ニキビの発生や悪化に影響を与える重要な要素の一つです。特に、糖分や脂質の過剰摂取は、皮脂の過剰分泌を促し、ニキビの悪化に繋がる可能性があります。例えば、高GI食品(血糖値を急上昇させる食品)や脂肪分の多い食品の過剰摂取は、皮脂腺の活動を活発にすることが知られています。しかし、特定の食物を過度に制限することは、特に嗜好品に対する欲求不満やストレスを引き起こし、結果的に健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
したがって、食事はバランスを重視し、野菜や果物を多く取り入れた食事を心がけることが重要です。適度な炭水化物、たんぱく質、脂質を含むバランスの良い食事は、ホルモンバランスの維持や皮膚の健康に貢献します。また、食事による栄養バランスの改善は、ニキビの予防や治療においても重要な役割を果たします。
4-2. ストレスとニキビの関係
ストレスもニキビの悪化に関与する重要な要因です。ストレスが溜まると、体内でコルチゾールといったストレスホルモンの分泌が増加し、これが皮脂の過剰分泌を促すことがあります。さらに、ストレスによるホルモンバランスの乱れは、皮膚のバリア機能を低下させ、炎症を引き起こしやすくなります。そのため、ストレスを適切に管理することが、ニキビの予防と改善において重要です。
ストレス管理の方法としては、適度な運動、十分な睡眠、リラクゼーション法などが効果的です。これらを日常生活に取り入れることで、ストレスを軽減し、ニキビの改善に寄与することが期待されます。
5. ニキビの進行段階の把握
ニキビの症状は、大まかに以下の4つの段階に分類されます。これを理解することで、適切な対処法や医療機関への相談のタイミングを判断するのに役立ちます。
- ①白ニキビ(閉鎖面皰): 毛穴に皮脂や角質が詰まり、毛穴が閉じた状態で、皮膚表面に白っぽい小さな突起が見える状態です。この段階では、炎症はまだ起こっておらず、比較的軽度な状態です。
- ②黒ニキビ(開放面皰): 白ニキビが進行し、詰まった皮脂や角質が毛穴から空気に触れることで酸化し、黒く変色した状態です。これを「開放性粉瘤」とも呼びます。毛穴が開いているため、炎症を起こす前にケアすることが重要です。
- ③赤ニキビ(炎症性面皰): 黒ニキビがさらに進行し、毛穴に詰まった皮脂がアクネ菌により炎症を引き起こした状態です。皮膚が赤く腫れ、痛みを伴うこともあります。この段階では、適切な治療が必要です。
- ④黄ニキビ(膿疱性面皰): 炎症がさらに進行し、毛穴の中で膿が溜まった状態です。黄色状の膿が皮膚表面に見えることから「黄ニキビ」と呼ばれます。この状態を放置すると、皮膚に凹凸やクレーターが生じるリスクが高まります。
各段階に応じた適切なスキンケアや治療法を選択することで、ニキビの悪化を防ぎ、改善を促進することが可能です。白ニキビや黒ニキビまでは、予防や市販薬などで対応できますが、特に、赤ニキビや黄ニキビの段階では、専門医による診断と治療が必要となります。
6. ニキビの治療薬
炎症が悪化している場合は、ニキビが赤く腫れたり、痛みを伴うことがあります。また、ニキビが黄色く膿んだり、周囲の組織が破壊されることもあります。また、治療が遅れるとニキビ跡の大きな要因となります。このような症状が見られる場合は、早めに皮膚科の医師に相談することが重要です。
6-1. 急性期治療薬
6-1-1. 内服の抗生物質
抗生物質は炎症を抑え、化膿を防ぐ作用があるため、急性期にはとても有効な薬となります。ただし、長期間や過剰使用は耐性菌の発生を促す可能性があるため、医師の指示に従って使用する必要があります。
抗生剤の種類としては、テトラサイクリン系(ドキシサイクリン、ミノサイクリン)、次いでマクロライド系(ロキシスマイシン、クラリスロマイシン)の有効性が高いとされています。また、セフェム系(ゼフジニル)、ペネム系(ファロペネム)なども用いられることもあります。
6-1-2. 外用抗生剤
ニキビの炎症を鎮め、皮膚表面の菌の増殖を抑える効果があります。外用薬は直接炎症部位に塗布することで効果を発揮します。内服同様に耐性菌の発生を抑えるため、最小限の使用を心がけ、患部のみの使用を守ることが大切です。
よく用いられる医薬品には、クリンダマイシン、ナジフロキサシンがあり、剤型もゲル、クリーム剤、軟膏剤、ローション剤と多様であり、症状や皮膚に合った物を選択します。
6-2. 寛解期の治療薬
6-2-1. ピーリング効果のある外用薬
ピーリング効果のある外用薬は、古い角質を除去し、毛穴の詰まりを解消します。これにより、ニキビの発生を抑える効果が期待できます。代表的な医薬品には、ディフェリン、ベピオとその合剤であるエピデュオがあります。
6-2-2. ビタミン剤
ビタミンB群やビタミンCは、皮膚の健康をサポートし、ニキビの改善に役立ちます。特にビタミンB6やビタミンCは、皮脂の分泌を抑制する効果があります。
6-2-3. 市販の治療外用薬
市販のニキビ治療外用薬は、複数の成分が組み合わされており、効果が相乗的に発揮されます。以下は主要成分の簡単な説明です。
- ①イソプロピレンピコノール(IPPN)
遊離脂肪酸の産生を抑制し、炎症を軽減します。ニキビの初期段階での使用が推奨され、炎症を抑えることで悪化を防ぎます。 - ②イオウ:皮脂分泌抑制、殺菌作用
- ③イソプロピルメチルフェノール(IPMP):広範囲の殺菌作用
- ④ビタミンE(トコフェロール):血行改善作用、強い抗酸化作用
- ⑤レゾルシン:殺菌作用、角質溶解作用
- ⑥グリチルレチン酸:抗炎症作用
- ⑦酸化亜鉛:皮膚保護作用、
以下では、比較的に手に入りやすい価格帯のものを挙げていきます。乾燥肌・敏感肌の方は、グリチルレチン酸やビタミンEなど、炎症を抑えつつ保湿効果が期待できる成分を含むものが適しています。オイリー肌や脂性ニキビの方は、イオウなどの皮脂抑制や殺菌効果のある成分を含む製品を選びましょう。
代表的な市販薬とその特徴
| 市販薬名 | 成分 | 特徴 |
|---|---|---|
| アクネキュアクリーム(イハダ) ペアアクネクリームW(ライオン) | ①③ | 皮膚に優しい弱酸性、初期のニキビに効果的 |
| アポスティークリーム(ゼリア新薬) | ①③④ | 保湿成分(ヒアルロン酸Na、濃グリセリン)を配合し、乾燥も防ぐ |
| アンナザルベ・エース(エスエス製薬) | ②⑤⑥ | 伸びが良いバニシングタイプのクリームで、塗りやすい |
| メンソレータム アクネス(ロート製薬) | ②④⑤⑥ | 赤いニキビや痛いニキビに対しても対応 |
| ピンプリットN(資生堂) | ②⑤⑥⑦ | オイルフリーでベタつかず、無香料。敏感肌にも適した処方 |
また市販薬にも、抗生物質が入ったものがありますが、それらはアクネ菌に対する効果はあまり期待できません。よって、どうしても化膿を抑えたい時には使用しても良いですが、基本は使用を控えるべきです。
6-3. 漢方治療薬
漢方薬は、体内のバランスを整え、ニキビの原因となる体内の不均衡を改善する効果があります。また、直接炎症を抑えたり原因のアクネ菌を抑える作用を持つものもあります。注意点としては、漢方薬はその方剤により個人差が大きいため、専門医の指導のもとで使用する必要があります。各漢方薬の詳細に関しては、以下の章で説明をします。
6-4. 特に推奨されている治療薬
6-4-1. 予防や長期間の治療への適応
ニキビのガイドラインの中でも、最も推されているものはベピオやディフェリン(その合剤のエピディオ)です。その理由としては、長期使用しても比較的安心して使用でき、予防としても使い続けることができるからです。
まだニキビになる前の状態である微小面皰にも効果があります。また、ベピオとエピデュオにはアクネ菌に対し殺菌効果はありますが、抗生物質とは異なる作用をするため、耐性菌の心配もありません。よって、これらと保湿ケアが治療の基本となります。
6-4-2. ピーリング効果のある薬の高頻度の副作用
ただしこれらの薬には、1点大きな注意点があります。それは皮膚を薄くするために、外部からの刺激にとても敏感になり、刺激作用や発赤が強く出ることで、これはかなり高確率でなる恐れがあります。
対策としては、使用開始および再開時は使用量を少なく、かつ使用部位を小さくし、1週間くらいかけて徐々に常用量にしていくことです。また刺激症状などは次第に慣れてくるために、ひどくないようならば、使用量を減らして様子を見ながら使用していきます。
またベピオ(エピデュオ)はもう一つ注意事項があり、漂白作用を持ち合わせています。よって、塗った部位には、なるべく寝具や衣服にはつかないように注意した方が良いです(髪の毛に関しては、実証実験ではほぼ問題はないらしいです)。
6-4-3. ショートコンタクトセラピー
刺激感などの副作用対策として、ショートコンタクトセラピーがあります。これは入浴や洗顔の15分程度前に塗布し、入浴時などにしっかり洗い流す手法です。通常外用薬は、塗布後1〜2時間はそのままにしないと効果を示しませんが、この手法であればたった15分程度でも有効性は認められているため、副作用があるけどこれを続けたいと考えている方は、医師や薬剤師の指示を受けながら継続も可能になるかもしれません。
7. 漢方薬のニキビ治療
7-1. 「証」に基づく漢方治療の基本的な考え方
「証」とは、患者の体質、症状、経過、原因などを総合的に判断し、治療法を決定する基準です。ニキビに対する漢方治療では、主に「湿熱(しつねつ)」「血熱(けつねつ)」「瘀血(おけつ)」などが関連しますが、患者の体質や生活習慣により選ばれる処方は異なります。
7-2. 主な「証」と対応する漢方薬
7-2-1.「湿熱」タイプ(体内に湿気や熱がこもりやすいタイプ)
湿熱タイプの人は、油っぽい肌、化膿したニキビ、赤く腫れたニキビが特徴です。このタイプは、食事の不摂生やストレス、特に脂肪分や甘いものを過剰に摂取することが原因になることが多く、腸の働きの悪さとも関連します。
①十味敗毒湯
早期の化膿性ニキビに使用され、炎症を抑えつつ膿を取り除く作用があります。初期段階のジュクジュクしたニキビに効果的で、改善後も予防として用いられます。
②荊芥連翹湯
すでに炎症が長期間伴っており、症状が深い位置にまで達している場合のニキビにより効果的です。また、長期服用することで体質改善を促し、血行促進したり炎症を抑えることによる皮膚の正常化が期待されます。
③清上防風湯
赤ら顔など熱がこもっているタイプで、炎症や化膿を伴っているニキビに対して用います。特に、思春期のオイリー肌な方に対して効果があります。
④黄連解毒湯
非常に強い赤みや炎症を抑えるため、ひどい炎症性ニキビに用い、抗菌作用でアクネ菌にも効果的です。ただし強い清熱作用のため、冷え性や乾燥肌の方には不向きです。
7-2-2. 「瘀血」タイプ(血の流れが滞っているタイプ)
瘀血タイプは、皮膚に血流が不足し、顔色が悪く、古いニキビ跡が残りやすい人です。ニキビ自体は赤黒く硬い場合が多く、触ると痛みを伴うこともあります。月経不順や冷え性の人にも多いです。
①桂枝茯苓丸
血行を促進し、瘀血を改善する作用があります。特に月経不順や冷え性を伴う女性のニキビに有効です。特に、瘀血の腹証である下腹部の痛みや硬さがある場合に使用します。
②桃核承気湯
体力があり、便秘を伴う瘀血タイプのニキビに効果的です。下腹部の痛みや充満感があり、強い便秘が続く場合に適しています。
③加味逍遙散
ストレスやイライラを伴い、月経前に体調が悪化しやすい場合に有効です。体力がやや低下している状態で、炎症が強いニキビに用いられます。肋骨下を押すと痛みがある胸脇苦満が使用目標です。
④当帰芍薬散
冷えやむくみを伴うホルモンバランスの乱れによるニキビに効果的です。特に、女性の月経不順や冷え性が関連するニキビに使用されます。
ニキビ治療において、ガイドラインではまず「熱を取る」漢方薬として、荊芥連翹湯、十味敗毒湯、清上防風湯が選択されます。これらは、主に「湿熱タイプ」の炎症性ニキビに対して使用され、現場でも多くの医師が初期治療に用いる漢方薬です。
各薬の選択は、ニキビの状態や炎症の期間に応じて使い分けることが重要です。例えば、清上防風湯は思春期の脂性肌、十味敗毒湯は化膿初期のジュクジュクしたニキビ、荊芥連翹湯は炎症が深いニキビに適しています。
これらで治らない場合、症状が長引く・再発を繰り返す場合は、患者の体質や生理周期を考慮して、瘀血タイプに対する漢方薬(桂枝茯苓丸、加味逍遙散など)を試すことも有効です。場合によっては、湿熱タイプの漢方薬にこれらを併用することで、体質改善を促し、根本的なニキビ治療を目指すことができます。
8. ニキビ痕(瘢痕)の治療
現代の医療では、ニキビ跡を治す特効薬はありません。一番良い対策としては、まず予防し悪化し始めたらなるべく早い段階で治療をすることです。それでも少しでも痕があると、気になる方は多いと思われるため、いくつか例を挙げておきます。
- ①レーザー治療
ニキビ跡の種類により、それに対応したレーザー治療を行います。クレーター状にはフラクショナルレーザー、他にもピコレーザーなどもあります。機器の種類により、その効果もさまざまです。 - ②ステロイド局所注射
肥厚性瘢痕やケロイドに対して特に有効な治療法です。ステロイドは瘢痕部に直接注射され、コラーゲンの過剰産生を抑制し、瘢痕を軟化させ、縮小させます。瘢痕治療のガイドラインでも推奨度が最も高く、C1推奨とされています。 - ③充填性注射
萎縮性瘢痕(皮膚が凹んでしまうタイプのニキビ痕)に対し、コラーゲンやヒアルロン酸などの充填剤を注入し、凹みを目立たなくする治療です。これにより、皮膚の表面を滑らかにし、見た目を改善します。定期的な注射が必要な場合もあります。 - ④ノーリス光治療
光エネルギーを用いて、主に赤みを伴ったニキビ跡に用います。従来の光治療で懸念であった照射時の痛みが大分軽減されています。 - ④漢方薬
肥厚性瘢痕に対し、細胞の増加や分化に関与するTGF-βの産生を抑制したり、線維芽細胞の増殖を抑制する柴苓湯などが用いられることがあります。 - ⑤トラニラスト(リザベン)内服薬
肥厚性瘢痕やケロイドの治療に有効で、瘢痕形成の過程で過剰に産生されるコラーゲンを抑制します。トラニラストは、コラーゲン合成を抑え、瘢痕の肥厚や硬化を防ぐ働きがあり、長期的な治療に使用されます。

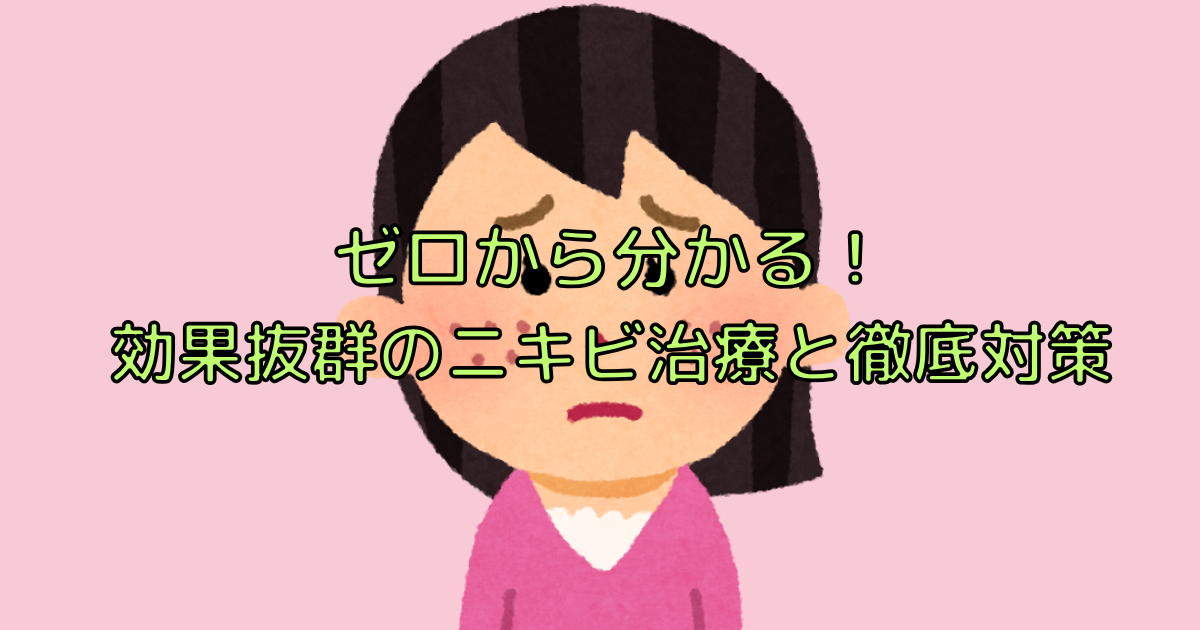
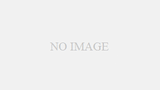
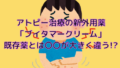
コメント