はじめに
最近、漢方薬専門のクリニックや薬局で「漢方薬が保険から外れるかもしれない」という内容のポスターやチラシを見かけた方もいらっしゃるかもしれません。アレルギー、胃腸の不調など、日々の体調管理に漢方を取り入れている方にとっては、見過ごせない話題です。
実は現在、「OTC(一般用医薬品)と似た性質を持つ医療用薬を保険適用の対象から除外すべきではないか」という議論が進められており、その中に漢方薬も含まれる可能性があるとされています。財務省を中心とした提案ですが、医療現場や専門学会などからは反対や懸念の声も上がっています。
本記事では、なぜこうした議論が起きているのか、漢方薬が保険から外れると私たちの生活にどのような影響があるのかを丁寧に読み解いていきます。「未病」のケアや体調維持にとって、漢方薬が果たしている役割にも改めて目を向けながら、この問題の本質を探ります。
1. 政策提案の概要
近年、「OTC類似薬」を保険の対象から外す動きが本格化しています。すでに漢方薬以外の一部薬剤については、2026年度から保険適用外となる予定となっています(※詳細は過去記事「OTC類似薬が保険外に?財務省提案の真意と医療現場の反応を読み解く」をご参照ください)。
この動きの背景には、医療費削減やセルフメディケーションの推進という政策的意図があります。軽症や未病の段階では、医師の関与を最小限にし、自らの判断で対処するという考え方です。私自身、セルフメディケーションの考え方には一定の意義があると感じていますが、すべてのケースに当てはめられるべきではないとも考えています。
とくに、漢方薬は「未病」—すなわち病気になる前の体の変化—に対してアプローチできる貴重な治療手段です。西洋医学では見過ごされがちな症状や体質改善に効果があることから、単なる「OTC類似薬」として一括りにされるのは疑問が残ります。
次章では、そもそも「OTC類似薬」や漢方薬がどのような位置づけなのか、もう少し具体的に掘り下げていきます。
2. OTC類似薬と漢方薬の立ち位置とは?
2-1. 「OTC類似薬」とは?
OTCとは「Over The Counter」の略で、薬局などで処方箋なしに購入できる一般用医薬品を指します。これに対して、医療機関で処方される医療用医薬品の中には、成分・効能・用法がほぼ同じものが存在します。これらが「OTC類似薬」と呼ばれ、今その保険適用の見直しが議論されているのです。
この流れの中で、注目されているのが医療用漢方薬です。例えば「葛根湯」や「小青竜湯」などは、OTCとしても市販されていますが、同じ処方が保険適用の医療用としても利用されているため、「OTC類似薬」に含まれる可能性があります。
2-2. 漢方薬選択の難しさ
一般的な西洋薬であれば、ある程度は「症状に合わせて使う」ことが可能です。例えば、頭が痛ければ頭痛薬を、胃がむかむかすれば胃薬を、というように、自己判断でも比較的安全に対処できる場面があります。
しかし、漢方薬は少し事情が異なります。もちろん一部には対症的に使われる処方もありますが、基本的にはその人の「体質(証)」に合わせた処方が必要とされます。例えば同じ「風邪」の症状でも、冷えが強い人と熱がこもる人では、処方される漢方薬はまったく違うことがあります。「風邪の引きはじめは葛根湯」は皆に通用するものではありません。
この「証」を見極めるには、専門的な知識と経験が不可欠であり、自己判断で正しく選ぶのは容易ではありません。そうした特性を持つ漢方薬を、他のOTC類似薬と同列に扱い、保険適用外とするのは本当に妥当なのか、疑問が残るところです。
もちろん、保険適用外の対象となる可能性がある漢方薬の中には、対症的に用いられるものも含まれるかもしれません。しかし、その線引きは極めて難しく、場合によっては「本来は証に基づいて処方されるべき薬」までが保険の対象外となってしまうおそれもあります。
3. 保険見直しで医療費はどう変わる?私たちの負担への影響
OTC類似薬の保険適用が見直される中で、患者にとって最も直接的な影響は「自己負担の増加」です。現在1割もしくは3割負担で処方されている漢方薬が、全額自己負担(10割)となることで、1処方あたりのコストは数千円単位で跳ね上がることもあります。
一方で、軽い風邪や季節性アレルギーで葛根湯や小青竜湯をすでに処方されている人は、薬局での購入に切り替えることで、医療機関の受診が不要になるという利点もあります。これは、時間や医療費全体の削減という点で評価できるでしょう。
反面、長期間同じ漢方薬を処方されている慢性症状の患者や、高齢者・妊婦など継続的な医師の判断が必要なケースでは、「薬局で済ませる」ことが現実的でない状況も多くあります。そうした患者にとっては、保険適用外となることは実質的な“治療の断念”を意味する場合も考えられ、結果として病気が進行・重症化し、将来的により高額な医療が必要になるという本末転倒な結果も懸念されます。
4. 医療現場等からの反応
漢方薬を「OTC類似薬」として保険適用から外すという議論について、医療現場や専門団体からは慎重な姿勢や反対の声が上がっています。
とくに、日本東洋医学会や和漢医薬学会といった漢方に関わる学会は、「漢方薬は体質(証)に基づいて処方される医療用医薬品であり、市販薬と同列に扱うべきではない」とする声明を発表しています。これは、漢方薬が単に“症状を抑える”ためのものではなく、患者一人ひとりの体質・症状の組み合わせに応じて使われるものであるという医学的背景によるものです。
実際、医師による処方で漢方薬を継続的に服用している患者の中には、「保険が効かなくなったら継続が難しい」「自己判断で同じ薬を買うのは不安」という声もあります。とくに高齢者や慢性疾患の患者にとっては、医師の診断に基づいた処方と保険適用の組み合わせが、治療を支える柱となっているのです。
もちろん、OTC類似薬の見直し全体については、医療費の抑制やセルフメディケーション推進の観点から一定の理解もあり得るでしょう。私自身もその方向性には一定の共感を持っています。しかし、漢方薬に関してはその特性ゆえに、他のOTC類似薬と同じ基準で判断するのは適切ではないと考えています。
次章では、こうした視点を踏まえて、漢方薬が対応する「未病」の概念と、セルフメディケーションの在り方について、より深く掘り下げていきます。
5. 未病とセルフメディケーションの間で
5-1. 漢方が目指す「未病」へのアプローチとは
「未病」という言葉をご存じでしょうか。これは、東洋医学で古くから使われている概念で、「病気には至っていないが、何らかの不調がある状態」を指します。西洋医学では見過ごされがちなこうした状態に対して、漢方薬はきめ細かく対応する力を持っています。
たとえば、冷えや疲れやすさ、胃腸の不調、イライラや不安感など、西洋医学では「経過観察」とされがちな症状に対して、漢方薬は体質を整え、症状の悪化を防ぐための処方が行われます。これは、まさに「病気になる前に整える=未病の治療」というアプローチにあたります。
5-2. セルフメディケーションと漢方薬の付き合い方
近年、セルフメディケーションの重要性が叫ばれており、自分の体調を自分で管理するという考え方自体には私も一定の賛同をしています。軽度の不調に対して、すぐに病院に行くのではなく、市販薬や生活習慣の見直しで対処することは、医療費削減や医療リソースの最適化という面でも意義があります。
しかし、漢方薬に関しては「自己判断で使える薬」かどうかには慎重であるべきです。前章でも触れたように、漢方薬はその人の「証(体質・症状の組み合わせ)」に合っていないと、逆に効果が出なかったり、体調を崩すことすらあります。
たしかに、風邪の初期などに使われる「葛根湯」など、一見すると対症的に用いられる処方もあります。ただし葛根湯一つをとっても、単に「風邪っぽいから」という理由で使えるものではなく、服用するタイミングやその時の状態が重要です。たとえば、発熱する力があるか、自汗がないか、脈が浮いているかなど、麻黄の作用に耐えられるだけの体力と条件が揃っている必要があります。
さらに、鼻炎といえば「小青竜湯」がよく知られていますが、これも誰にでも合う薬ではありません。小青竜湯は、水っぽい鼻水や寒気がある「寒証」の人に向いており、体を温める作用を持つ生薬が含まれています。そのため、ほてりや顔の赤みがある「熱証」の人には適さないこともあります。
同じ症状でも、体質や状態によって処方は変わるのが漢方の特徴です。やはり、自己判断ではなく、専門的な視点で選ぶことが大切です。
「未病に対応する薬」としての漢方薬は、単なるOTC類似薬として保険から除外されるのではなく、その価値と特性をふまえた慎重な制度設計が求められていると感じます。
5-3. 個人で漢方薬の理解を深めたい方
もしこれまでの記事を読んで「漢方について少しでも理解を深めたい」と感じた方がいらっしゃれば、以下にご紹介する書籍が参考になるかもしれません。いずれもネットで購入でき、日常的な体調管理や制度理解にも役立つ内容です。
- 健康保険が使える漢方薬の事典(著者:今津嘉宏)↗️
→保険が適用される漢方薬がどれなのかを知りたい方に最適な実用書。具体的な症状との対応や使い方のポイントも丁寧に解説されています。 - 生薬と漢方薬の事典(田中耕一郎 編著)Kindle版↗️
→119種の生薬や298処方の漢方薬を、症状・体質別にイラストとともにわかりやすく解説。初学者でも「自分の体質に合った処方」が探しやすく、セルフケアや未病対策の参考書として非常に実用的です。
6. これから私たちにできること – 制度と向き合う視点
漢方薬がOTC類似薬として保険適用外になる可能性が取り沙汰されている現在、私たちに求められるのは、感情的な反発だけではなく、制度の背景と意図を理解したうえで、冷静にこの問題と向き合う姿勢です。
たしかに医療費の増大や制度の持続可能性といった課題は、無視できない社会全体のテーマです。軽度の症状や短期的な不調に対しては、セルフメディケーションを活用し、医療リソースを必要な場面に集中させるという考えには一定の合理性があります。
しかし、漢方薬は一部のOTC類似薬とは異なり、「未病」や体質改善といった中長期的視点での健康管理を支える医療資源でもあります。 その価値を過小評価し、短期的なコスト削減の観点だけで保険適用の有無を判断するのは、結果的に医療全体の質や公平性を損なう恐れがあります。
今後、どのような薬が具体的に保険適用外となるか、制度設計がどう進むかはまだ不透明です。だからこそ、私たちは信頼できる情報に基づいて状況を把握し、必要があれば意見を表明することが重要です。
そして、医師と相談しながら、自分に必要な治療を見極め、「何を自分で対応できるのか」「どこからが医療に頼るべき領域か」を、より丁寧に考えることが求められているのかもしれません。それこそが真のセルフメディケーションの第一歩となるでしょう。

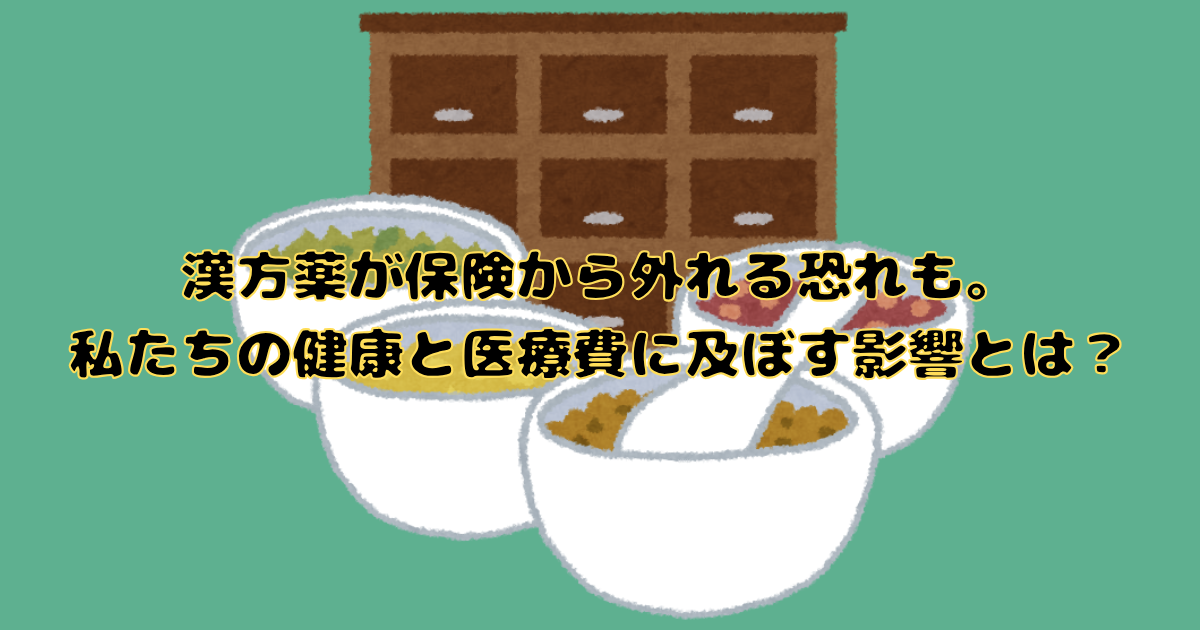
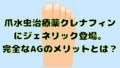
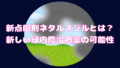
コメント