1. 原発性局所多汗症とは?
1-1. 汗っかきとの違い
「汗っかき」と「原発性局所多汗症」は、どちらも「汗が多い」という点では共通していますが、その背景や程度には明確な違いがあります。
まず、「汗っかき」は主に気温や運動、緊張などの外的要因に対して正常に反応している状態です。つまり、身体が体温調節を行うために必要な汗をかいているだけであり、病的なものではありません。
一方、「原発性局所多汗症」は、特定の部位(手のひら、足の裏、脇、顔など)に過剰な発汗がみられ、明らかな原因がないにもかかわらず日常生活に支障をきたす状態を指します。特に思春期前後から症状が現れ、緊張とは無関係に突然汗が出てくることも多く、日常的に「ハンカチを常に持ち歩く」「紙が汗で濡れて書きづらい」「握手ができない」などの悩みにつながります。
実際には多くの人がこの疾患に悩まされているにもかかわらず、原発性局所多汗症の認知度は低く、日本皮膚科学会によると医療機関への受診率は決して高くありません。「汗っかきだから仕方ない」と自己判断してしまい、適切な治療にたどり着かないケースも少なくないのです。
1-2. 好発部位(多汗症の種類)
原発性局所多汗症は、身体の限られた部位に対して、左右対称に発汗が過剰になる疾患です。中でも特に多く見られるのが以下の4つの部位です。
1-2-1. 掌蹠多汗症
掌蹠多汗症とは、手のひらと足の裏に精神的緊張により過剰な発汗がみられる状態であり、原発性局所多汗症の中でも患者数が多い代表的なタイプです。多くは幼少期のころに発症し、明確な原因がないまま汗をかくのが特徴です。
重症例になると、汗が滴るほど出るケースもあり、日常生活にさまざまな支障をきたします。特に掌部では、紙が濡れて上手く書けない、スマホやPCなどの機器の操作への支障、握手の抵抗感など、学校生活や仕事、人間関係にストレスを感じる場面が多くなります。
また、足の裏の多汗は、湿潤状態が長時間続くことで皮膚バリアが崩れ、皮疹が起こりやすくなるだけでなく、足白癬(水虫)、尋常性疣贅(イボ)といった細菌や真菌、ウイルス感染症のリスクも高まるとされています。
1-2-2. 腋窩多汗症
脇の下は、精神性発汗と温熱性発汗の両方が起こりやすい特殊な環境にあるとされており、原発性局所多汗症の中でも左右対称に多汗が現れる典型的な部位です。このため、夏の暑さだけでなく、緊張や人前での発表、面接など精神的な場面でも発汗が誘発されやすく、日常生活でのストレスにつながりやすいのが特徴です。
特に目立つのが「汗ジミ」であり、衣類の色選びに悩んだり、対人関係を避けたくなるといった心理的負担を抱える患者も少なくありません。
1-2-3. 頭部、顔面多汗症
頭や顔に過剰な発汗がみられるタイプで、原発性局所多汗症の中では比較的頻度は少ないものの、見た目に直接関わるためQOLへの影響が大きい部位です。男性に多く、18〜20歳ごろから自覚しやすく、長期間にわたり持続することもあるとされています。発汗のきっかけとしては、精神的ストレスや緊張のほか、物理的刺激も影響します。
またこのタイプは、見た目に影響があるため、恥ずかしさや不安から外出を控えるようになる人も少なくありません。化粧が崩れやすくなる、眼鏡がくもる、などの実用的な支障も訴えられます。
2. チェックポイントと診断基準
2-1. 診断基準
原発性局所多汗症の診断には、Hornbergerら[1]によって提唱された6つの診断基準がよく用いられます。
明らかな原因がないまま、過剰かつ限局性の発汗が6か月以上持続し、かつ以下の6項目のうち2項目以上に該当する場合に診断が可能とされています。
- 左右対称性に発汗がみられる
- 日常生活に支障をきたす程度の多汗である
- 週に1回以上の頻度で多汗の症状が現れる
- 初発年齢が25歳以下である
- 家族歴がある
- 睡眠中は発汗が止まっている
「手汗がひどいけど病気なの?」と悩む方も少なくありません。
上記のようなチェックポイントに2つ以上当てはまれば、“多汗症かもしれない”サインです。
気になる方は一度、皮膚科などの専門医に相談してみましょう。
この診断基準の特徴は、問診ベースでもある程度の診断が可能な点です。つまり、特別な検査を行わなくても、上記のポイントを確認することで、医師が比較的簡便に診断できるというメリットがあります。
2-2. 重症度
原発性局所多汗症の重症度を評価する際には、HDSS(Hyperhidrosis Disease Severity Scale)=多汗症疾患重症度評価スケールがよく用いられます。
このスケールは、患者自身の主観に基づいて、日常生活への支障の度合いを4段階で評価するシンプルな方法です。
| スコア | 症状の程度 | 日常生活への影響 |
|---|---|---|
| 1 | 発汗が気にならない程度 | 全く支障がない |
| 2 | 発汗は気になるが我慢できる | 時に支障が出る |
| 3 | 発汗はほとんど我慢できない | 頻繁に支障が出る |
| 4 | 発汗がひどく我慢できない | 常に支障が出る |
「ただの汗かきなのか、病的な多汗なのか分からない…」と悩む方は、まずこのHDSSを参考にしてみましょう。
あなたの日常生活にどれほど影響があるのかを可視化することで、皮膚科での相談もスムーズに進みやすくなります。
3. 局所多汗症の治療
原発性局所多汗症の治療法には、内服薬、外用薬、外科的手術、イオントフォレーシスなどがあり、それぞれ一定の効果が認められています。これらの治療法の推奨度は、最新の診療ガイドライン[2]に基づき、エビデンスレベルに応じてB、C1、C2の順に分類されています。以下に、各治療法の概要と推奨度を示します。
3-1. 外用薬
3-1-1. 塩化アルミニウム
推奨度:腋窩多汗症B、手掌多汗症B、足底多汗症C1、頭部・顔面多汗症C1
塩化アルミニウムは、原発性局所多汗症において幅広い部位に使用される代表的な外用薬です。
その制汗作用の仕組みとしては、アルミニウムイオンが汗腺の中でムコ多糖類と反応し、複合体を形成することで、細胞を損傷させ汗を出す管(汗管)を物理的に塞ぎ、発汗を抑えるとされています。
この際、汗管周囲の上皮細胞に軽度の損傷が起こるものの、汗の分泌細胞そのものは影響を受けないと考えられています。
しかしながら、長期的に塗布を継続することで、汗管のダメージが蓄積し、次第に分泌細胞の機能や構造にも変化が生じ、結果として発汗機能自体が低下する可能性があると報告されています。このため、症状が軽快しても定期的な塗布を継続することが望ましいとされています。
3-1-2. 抗コリン外用薬
推奨度:腋窩多汗症B、掌蹠多汗症C1、頭部・顔面多汗症C2
抗コリン薬は、エクリン汗腺に多く存在するムスカリンM3受容体に結合し、神経伝達物質アセチルコリンの働きを阻害することで、発汗を抑制する作用を発揮します。
近年において外用タイプの抗コリン薬には、ゲルタイプ塗布剤エクロック®︎ゲル(ソフピロニウム)や、1回使い切りシートのラピフォート®︎ワイプ(グリコピロニウム)が登場しており、従来の内服薬に比べて全身性の副作用(口渇・便秘・散瞳など)が軽減される点が大きな利点です。これにより、日常生活に支障を来すことなく使用を継続しやすいという特徴があります。
一方で、現時点では「腋窩多汗症」にのみ保険適応が認められており、掌蹠や顔面など他部位の多汗症に対する使用は保険適応外(自費)となっているのが課題です。薬理学的な作用機序から見れば、他の部位にも効果が期待できる可能性は十分ありますが、現段階ではエビデンスや治験結果が限定的であり、今後の研究や適応拡大が期待されます。
3-2. 内服薬
内服薬は、原発性局所多汗症の第一選択ではないものの、他の治療が無効なときなど検討される治療法のひとつです。
3-2-1. 抗コリン内服薬
推奨度:C1
多汗症に対する内服治療の主な選択肢として、抗コリン薬が挙げられます。これらは、外用療法、イオントフォレーシス、ボツリヌス毒素注射などの治療が無効な場合や、これらの治療が難しい頭部・顔面多汗症などの症例において、積極的に試みても良いとされています。
現在、日本で多汗症に対して保険適用されている抗コリン薬は、臭化プロパンテリン(商品名:プロ・バンサイン®︎)のみです。その他、本来は過活動膀胱の薬であるオキシブチニン(ポラキス®︎)やコハク酸ソリフェナシン(ベシケア®︎)などの薬剤も使用されることがありますが、これらは保険適用外であり、効果には個人差があります。
抗コリン薬の副作用としては、口渇、便秘、眠気などが発症率が高くなっています(特にプロ・バンサイン)。また、前立腺肥大や閉塞隅角緑内障のある患者には禁忌とされています。さらに、高齢者においては、長期使用が認知機能に影響を及ぼす可能性があるため、慎重な使用が求められます。
3-2-2. 漢方薬
推奨度:ガイドラインには記載なし
多汗症の治療において、漢方薬も古くから用いられ、効果があるとされています。特に、生薬「黄耆」を含む漢方薬がよく使用されます。以下は一例であり、症状や体質、問診結果などにより、さまざまな漢方薬が用いられることがあります。
- 防已黄耆湯
代表的な多汗症に対する方剤の一つで、冷えがあり、脈が弱く体が重く疲れやすい、尿が少ない、浮腫みやすいといった体質の方に向いています。体内の余分な水分を排出し、汗腺の機能を調整するとされています。 - 補中益気湯
胃腸が弱っていたり、体力が落ちており、特にじっとりとした寝汗をかきやすい方に適しています。 - 白虎加人参湯
強い口渇や多尿などを伴っている方で、多汗がありながら皮膚が乾燥している方に推奨されます。 - 柴胡加竜骨牡蛎湯
不安感やストレスが強く、不眠を伴う比較的体力がある方に向いています。
3-2-3. その他の内服治療薬
以下の薬剤は、ストレスや緊張などの要因による多汗症に対して効果があったとする報告がありますが、いずれもエビデンスが限定的であり、さらなる研究が求められています。
- α2受容体刺激薬:クロニジン(カタプレス®)
高血圧治療薬として使用されるクロニジンは、中枢神経系に作用し、交感神経の活動を抑制することで発汗を減少させる可能性があります。 - 自律神経調整薬:トフィソパム(グランダキシン®)
自律神経のバランスを整える作用があり、精神的な緊張による発汗に対して有効とされることがあります。 - 選択的セロトニン再取り込み阻害薬:パロキセチン(パキシル®)
抗うつ薬として使用されるパロキセチンは、抗コリン作用を有し、精神的要因による多汗症に対して効果があるとする報告があります。 - 三環系抗うつ薬:アミトリプチリン(トリプタノール®)
抗うつ作用に加え、抗コリン作用を持つアミトリプチリンは、特に顔面多汗症に対して有効とされることがあります。
3-3. イオントフォレーシス療法
推奨度:掌蹠多汗症B、腋窩多汗症C1、頭部・顔面多汗症C2
イオントフォレーシス療法は、特に手掌や足底の多汗症である掌蹠多汗症に対して高い有効性を示す治療法です。水に浸した状態で微弱な直流電流を皮膚に通電することで、汗腺の機能を一時的に抑制すると考えられており、その後の研究で多汗症に対しても効果が示されました[3]。溶液は電解質でなく、水道水であってもほぼ同様の効果が得られることがわかり、現在では一般的に水道水が用いられています。
治療の目安としては、1回20〜30分の通電を週1〜2回、10回前後実施することで制汗効果が得られるとされています。効果が現れた後は、週1回程度の継続治療が推奨されます。
特に掌蹠多汗症の推奨度が高く、腋窩多汗症に対しても一定以上の効果が認められていますが、腋窩に対しては治療法が困難とされています。また、顔面頭部多汗症はエビデンスに乏しいため、推奨はされていません。
また、保険適用が認められている治療法である一方、通院が困難な場合には家庭用の機器も選択肢となります。ただし、これらは一般的に1台あたり約12万円前後と高価であり、導入には費用面の考慮が必要です。
3-4. A型ボツリヌス毒素局所注射療法
推奨度:掌蹠多汗症C1、腋窩多汗症B、頭部・顔面多汗症C1
A型ボツリヌス毒素(BT-A)は、ボツリヌス菌が産生する神経毒素の一種で、交感神経終末からのアセチルコリン放出を抑制することで、汗腺の活動を抑制し発汗を減少させます。注射後1週間程度で効果が現れ、約4〜9か月持続するとされています。
BT-A療法は、重度の腋窩多汗症に対しては保険適用が認められていますが、手掌、足底、頭部・顔面に対しては保険適用外となり、自費診療となります。注射部位における筋力低下が副作用として報告されていますが、通常は一時的なものであり、症状は投与量に比例するとされています。
3-5. 外科的手術(胸腔鏡下交感神経遮断術:ETS)
推奨度:重症手掌多汗症B、腋窩多汗症C1、顔面多汗症C1
局所多汗症に対する外科的治療の中でも、交感神経遮断術は代表的な選択肢の一つです。特に胸腔鏡下交感神経遮断術(ETS)が主流で、内視鏡を用いて胸部の交感神経を切除し焼灼する方法が一般的です。
ETSは、保存的治療(外用薬、イオントフォレーシス、ボツリヌス毒素注射など)で効果が不十分な重症の局所多汗症に対する外科的治療法です。特に手掌多汗症に対しては高い効果が報告されています。手術時間は片側約20分と比較的短く、安全性も高いとされています。
一方で、代償性発汗(手術で発汗が抑制された部位とは異なる部位で発汗が増加する現象)が主な合併症として挙げられます。代償性発汗の発生頻度や程度は個人差があり、日常生活に支障をきたす場合もあります。そのため、術前に十分な説明と同意が必要です。
4. 日常生活でできる汗対策とNG習慣
多汗症の治療は医療機関での介入が中心となりますが、日常生活の工夫によって汗を抑えたり、悪化を防ぐことができる場合もあります。この章では、日常でできる対策と避けるべき習慣について解説します。
市販の制汗剤は、多汗症の重症度によっては補助的な役割にとどまりますが、軽症例やQOLの改善には一定の効果が期待できます。ただし、誤った使用では思わぬ弊害も招く可能性もあるため、以下のような正しい使用方法を知ることが重要です。
4-1. 市販の制汗剤の選び方
現在では多くの制汗剤が発売されており、どれを選んで良いか迷うと思われます。その中でも、以下のような点を注意して選ぶと良いでしょう。最近の制汗剤はデオドラント(防臭効果)成分はほとんどのものに入っているため、その点はどれを選んでも気にすることはないと思われます。
4-1-1. 主成分
- アルミニウム製剤
- 塩化アルミニウム
医療機関で多汗症治療に用いられる代表的な成分です。高い制汗効果がありますが、皮膚刺激や衣類の劣化を引き起こす可能性があるため、使用には注意が必要です。 - クロルヒドロキシアルミニウム
皮膚刺激が出やすい塩化アルミニウムを改良した成分で、現在多くの市販制汗剤に使用されています。皮膚への刺激が少なく、使用感も良好です。
- 塩化アルミニウム
- 焼ミョウバン
古くから使用されている天然の制汗成分で、収れん作用と殺菌作用があります。食品添加物としても使用されており、安全性が高いとされています。 - 酸化亜鉛
収れん作用により汗を抑える効果がありますが、制汗効果は比較的穏やかです。医療用医薬品として、収れん・消炎剤として使用されています。さらに、酸化亜鉛はニオイの原因となる低級脂肪酸に作用することにより、汗による悪臭も軽減することができます。
4-1-2. 使用するタイミング
制汗剤の効果を十分に発揮させるには、汗をかく前の清潔な肌に使用するのが最も効果的です。入浴やシャワー後、肌が清潔で乾燥している状態で使用することで、効果が持続しやすくなります 。近年の制汗剤は持続時間も長く、前日の夜に使用することで活動時におけるニオイの元をあらかじめ抑えることができます。
汗をかいた後に使用する場合は、まず汗をしっかりと拭き取り、皮膚を生活にしてから制汗剤を使用することが推奨されます。これにより、成分が肌にしっかりと密着し、効果が高まります 。
4-1-3. 注意点
- 香料のない製品を選ぶ
汗が多く出る方は、その臭いも気になることが多いですが、香料で臭いをマスキングしようとすると、香料と汗の臭いが混ざり、かえって不快な臭いになる場合があります。現在の多くの制汗剤にはデオドラント成分が含まれているため、できる限り香料のない製品を選ぶことが推奨されます。 - 汗を抑えたい部位のみに使用する
制汗剤は長期間使用できるように設計されていますが、使用部位を限定することが重要です。厚生労働省の報告によると、塩化アルミニウムを全身に20年ほど継続使用した際に無汗症を発症したケースが報告されています。また、必要のない使用により皮膚障害の要因となることもあります。これらのリスクを避けるためにも、制汗剤は気になる部位のみに使用し、使用後はしっかりと洗い流すことが大切です。
4-2. 緊張やストレスとの向き合い方
多汗症の症状は、緊張やストレスと密接に関連しています。特に精神的な負荷がかかる場面では、交感神経が過剰に反応し、発汗が促進されることがあります。このような状況を改善するためには、日常生活の中でストレスを適切に管理し、リラックスできる時間を確保することが重要です。
4-2-1. 認知行動療法(CBT)
CBTが多汗症に対する心理療法の一つとして挙げられています。推奨度はC2とされていますが、特に不安や緊張が発汗を誘発する場合に有効とされています。思考や行動のパターンを見直し、ストレスへの対処能力を高めることを目的としています。
4-2-2. 日常での対処法
- リラクゼーション技法の実践
深呼吸、瞑想、ヨガなどのリラクゼーション技法は、心身の緊張を和らげるのに効果的です。これらを日常的に取り入れることで、交感神経の過剰な興奮を抑え、発汗のコントロールに役立ちます。 - 環境の調整
発汗を感じやすい環境では、衣服の素材や室温の調整など、物理的な対策も有効です。通気性の良い衣類を選ぶ、ハンカチやタオルを常備するなど、事前の準備が安心感を生み、緊張の軽減につながります。 - 専門家への相談
ストレスや緊張が日常生活に支障をきたす場合は、心理カウンセラーや医療機関の専門家に相談することを検討しましょう。CBTを含む心理療法は、思考や行動のパターンを見直し、ストレスへの対処能力を高めるのに役立ちます。
【参考資料・文献】
- Hornberger J, Grimes K, Naumann M. et al: Recognition, diagnosis and treatment of primary focal hyperhidrosis,J Am Acad Dermatol, 2004; 51: 274―286. ↩︎
- 日本皮膚科学会. 原発性局所多汗症診療ガイドライン2023年改訂版(2023年12月一部改訂). 日本皮膚科学会雑誌. 2023;133(13):3025-3056. ↩︎
- Bouman HD, Grunewald Lentzer EM: The treatment of hyperhidrosis of feet with constant current, Am J Phys Med, 1952; 31: 158―169. ↩︎

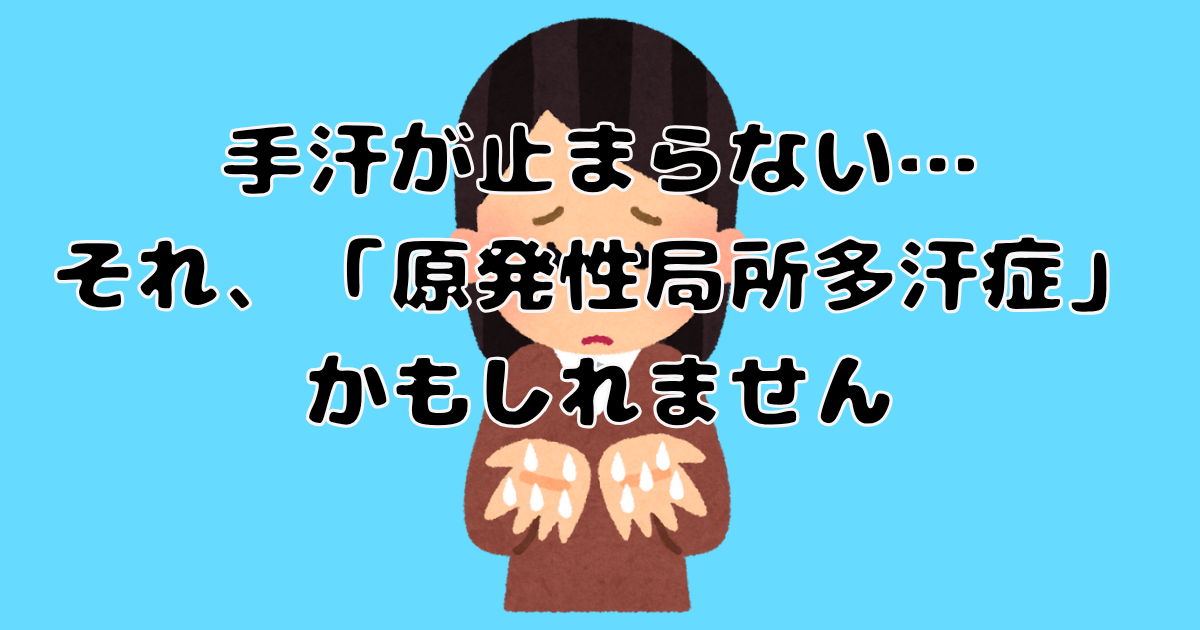


コメント