※本記事にはアフィリエイト広告を利用しています。商品リンクを経由して購入された場合、当サイトに収益が発生することがあります。
序章. 〜血液検査を“読む”ということ〜
健康診断や病院での検査で手渡される「検査結果の紙」。ほとんどの人が見て気にすることと言えば、せいぜい「コレステロールが高い」「血糖値がギリギリ」といった、医師から指摘された部分だけではないでしょうか。
しかし、検査結果にはそれ以外にも、さまざまな「からだの声」が隠されています。正常範囲から大きく外れていればもちろん問題ですが、一見正常でも、微妙な変化やバランスの崩れ方によって、不調の兆候を見つけるヒントが含まれていることもあります。
例えば、赤血球が正常範囲ギリギリでも、ヘモグロビンやMCVの数値が微妙に低下していれば「貧血の予備軍」かもしれませんし、白血球の数値の推移で感染や炎症の初期を察知できることもあります。
本シリーズでは、「検査結果を自分の言葉で“読める”ようになること」を目指して、パート別に解説していきます。
今回はその第一弾、
【臨床検査を読む力をつける】Part1 〜血球成分編〜
赤血球・白血球・血小板といった、血液の主役たちの見かたをやさしく丁寧にひもといていきましょう。
また、記事で解説する検査値の読み方を体系的に学ぶなら、以下の書籍がおすすめします。
- 今日の臨床検査2025-2026(南江堂)
1. 血球って何?── 血液中の主要な3つの血球成分
血液というのは、ただの「赤い液体」ではありません。実は、大きく分けて 2つの成分 に分かれています。
ひとつは、「赤血球」「白血球」「血小板」といった血液の主要プレイヤーである血球成分。もうひとつは、それらを運搬する液体部分である血漿成分です。ざっくり血液の構成を表にすると・・・
| 成分 | 内容 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 血漿 | 水 タンパク質 ホルモンなど | 栄養や老廃物の運搬 血液の浸透圧維持 止血や感染防御など |
| 血球 | 赤血球 白血球 血小板 | 酸素運搬 免疫機能 止血など |
今回のテーマである「血球」は、成人では主に骨髄で産生されます。血球はそれぞれ異なる役割を担っており、「少なすぎる」だけでなく、「多すぎる」場合や「形態異常」がある場合にも、何らかの異常や疾患の兆候であることがあります。
1-1. 赤血球(RBC):酸素を運ぶ“輸送屋”
赤血球は、血液中で最も多い細胞成分であり、血球全体の約90%を占めます。
内部にはヘモグロビン(Hb)という鉄を含んだタンパク質が豊富に存在し、これが酸素と結合して全身へと運搬します。
また、血漿と協力して不要となった二酸化炭素を肺まで運び出す役割も担っています。
「ヘモグロビンが低い=貧血」というのは、赤血球による酸素運搬能力が低下している状態を意味します。
1-2. 白血球(WBC):体を守る“免疫の戦士たち”
白血球は、ウイルスや細菌などの外敵から体を守る免疫細胞の集合体です。
「白血球が多い」→感染症の可能性
「白血球が極端に少ない」→免疫不全、骨髄抑制の可能性
など、免疫状態のバロメーターとしてよく使われます。
※白血球にも種類があり、詳細は次章以降で触れます。
1-3. 血小板(PLT):出血を止める“止血部隊”
血管が傷ついたときに、真っ先に集まって「血栓(けっせん)」を作るのが血小板です。
血小板が少なすぎると、出血しやすくなったり、あざができやすくなったりします。
一方で多すぎると、逆に血が固まりすぎて血栓症のリスクとなります。
1-4. 血球は“体調の通知表”
血球の異常は、
- 栄養状態(鉄・ビタミン欠乏)
- 感染症や炎症
- 骨髄の疾患(白血病など)
- さらには薬剤性の変化 まで
体のあらゆる異常を知らせてくれる“通知表”のような存在です。
「なんとなく疲れやすい」「検診で引っかかった」──そんなとき、血球成分を丁寧に読み解くことが、早期発見のきっかけになるかもしれません。
2. 赤血球関連の検査値
赤血液検査のうち、「赤血球」に関する指標としては、まず赤血球数(RBC)、ヘモグロビン濃度(Hb)、ヘマトクリット値(Ht)の3つが基本となります。
この中でも、もっとも重要な病態である「貧血」の診断には、通常ヘモグロビンの値が基準として使われます。
ただし、Hbが低い=貧血、というだけでは、その原因まで読み解くことはできません。そこで鍵になるのが、MCV(平均赤血球容積)などの赤血球指数や、網赤血球数(Ret)といった追加の検査値です。
これらを組み合わせて評価することで、鉄欠乏、造血低下、溶血、出血性など、貧血の原因をある程度推定することが可能になります。
言い換えれば、赤血球関連の指標を正しく読み解くことが、「原因に迫る」第一歩となるのです。
2-1. 赤血球数(RBC)、ヘモグロビン濃度(Hb)、ヘマトクリット値(Ht)
赤血液検査のうち、「赤血球」に関する指標としては、まず赤血球数(RBC)、ヘモグロビン濃度(Hb)、ヘマトクリット値(Ht)の3つが基本となります。この中でも、もっとも重要な病態である「貧血」の診断には、通常ヘモグロビンの値が基準として使われます。
同検査の主な目的は、貧血症や多血症の診断および鑑別です。
| 項目名 (略号) | 基準範囲 | 主な役割・意味 |
|---|---|---|
| 赤血球数 (RBC) | 男性:433〜555万/μL 女性:386〜492万/μL | 赤血球の総数を表します。少ないと貧血、多いと多血症の可能性。 |
| ヘモグロビン (Hb) | 男性:13.7〜16.8g/dL 女性:11.6〜14.8g/dL | 赤血球に含まれる、酸素を運ぶタンパク質の量。貧血の診断で最重要。 |
| ヘマトクリット (Ht) | 男性:40.7〜50.1% 女性:35.1〜44.4% | 血液中に占める赤血球の割合。脱水や多血症、貧血などの指標。 |
【高値の場合(=赤血球増加症)】
下記表のいずれかの数値が基準値を超える場合、「赤血球増加症」が疑われます。
赤血球増加症は、赤血球そのものが増える「絶対的赤血球増加症」と、体液の減少などによって見かけ上増えたように見える「相対的赤血球増加症」に大別されます。
| 成分 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 赤血球数 | 600万/μL以上 | 550万/μL以上 |
| ヘモグロビン | 18.0g/dL以上 | 16.0g/dL以上 |
| Ht | 55%以上 | 50%以上 |
- 絶対的赤血球増加症
赤血球数そのものが実際に増加している病態であり、原因に応じて2つのタイプに分類されます。
- 真性赤血球増加症
造血幹細胞の主に遺伝的(JAK2遺伝子変異)な異常により、赤血球の産生が必要以上に進んでしまうことで起こるものです。症状としては、白血球や血小板が増えたり、血清EPOの濃度が低下するのが特徴的です。
赤血球が増えると血液がドロドロになりやすく、血流が悪くなります。その結果、頭痛・めまい・耳鳴りといった脳の血流低下に関連する症状が現れることがあります。
さらに、真性多血症では血小板も同時に増加することから、血栓ができやすくなるため、脳梗塞や心筋梗塞などのリスクが上昇します。 - 二次性赤血球増加症
体内の酸素が慢性的に不足する状況に適応する形で、赤血球を増やすホルモン「エリスロポエチン(EPO)」の分泌が過剰になり、それに伴って赤血球が増加する病態です。真性赤血球増加症と異なり、赤血球以外(白血球・血小板)は通常増加しません。
主な原因としては、高地での生活、慢性の肺疾患や心疾患による低酸素状態、あるいはEPOを過剰に産生する腫瘍などが挙げられます。EPO産生腫瘍としては、腎臓のほか、肝臓・子宮・脳などに発生した腫瘍が関与することがあります。
- 真性赤血球増加症
- 相対的赤血球増加症
相対的赤血球増加症は、赤血球数自体は増加していないのに、脱水などで血漿成分(液体成分)が減ることで見かけ上、赤血球が多くなったように見える状態です。主な原因は、脱水やストレスなどが挙げられ、ストレス多血症には、高血圧や喫煙などの生活習慣も関係するとも言われています。
見かけ上であったとしても血液が濃くなった状態であるため、脳梗塞や深部静脈血栓症などの血栓症リスクがやや高まる可能性が指摘されています。
【低値の場合(=貧血)】
赤血球が低値を示す場合、多くは何らかの貧血状態を意味します。
一般に、ヘモグロビン(Hb)が男性で13.0g/dL未満、女性で12.0g/dL未満、高齢者では11未満の場合に貧血と判断されます。
貧血にはさまざまな種類と原因があり、その鑑別には特定の検査項目が重要です。詳しくは、次の項で解説していきます。
2-2. 赤血球指数
赤血球の数自体で貧血かどうかを気にする方は多いですが、その貧血は何が原因なのか?まで踏み込んで考える方はあまりいないと思います。そこに書かれている、MCVやMCHCの数値が大きいと、または小さいと何を示すかもとても意義のあることです。以下、各項目に関し簡単に説明をします。また、各数値は血液検査の表になかったとしても、赤血球数(RBC)とHb(ヘモグロビン)およびHt(ヘマトクリット値)から簡単に計算ができます。
| 項目名 | 略語 | 基準範囲 | 主な役割・意味 |
|---|---|---|---|
| 平均赤血球容積 | MCV | 80〜100 fL | 赤血球の大きさの平均を表します。赤血球が小さいと鉄が足りないタイプの貧血、大きいとビタミンなどが不足したタイプの貧血が疑われます。 |
| 平均赤血球ヘモグロビン量 | MCH | 27〜34 pg | 赤血球1個にどれくらいヘモグロビン(酸素を運ぶ物質)が入っているかを表します。赤血球が小さいと少なめ、大きいと多めになる傾向があります。 |
| 平均赤血球ヘモグロビン濃度 | MCHC | 31〜36 g/dL | 赤血球の中に、どれくらいギュッとヘモグロビンが詰まっているかを示します。詰まり具合が少ないと“色が薄い貧血”になりやすいです。 |
ここで主に指標となるものが、MCVとMCHCであり、これらの増減の組み合わせにより貧血が大まかに分類され、さらにその他の数値との組み合わせで、その詳細な病態や原因などを推測することができます。
| MCV(fL) | MCHC(%) | 分類 | |
|---|---|---|---|
| 80以下 | 30以下 | 小球性 低色素性貧血 | 鉄欠乏性貧血、 慢性出血、 慢性感染症など |
| 81~100 | 31~36 | 正球性 正色素性貧血 | 再生不良性貧血、 白血病、 骨髄線維症など |
| 101以上 | 31~36 | 大血球性貧血 | 悪性貧血、 巨赤芽球貧血、 甲状腺機能低下症など |
2-3. 網赤血球数
網赤血球とは、骨髄で作られたばかりの“若い”赤血球のことで、成熟赤血球へと移行する途中の段階です。
この検査は、貧血の原因が「赤血球の産生不足によるものか」「破壊や喪失によるものか」などを見極める目的で用いられます。
【高値を示す場合】
- 溶血性貧血
赤血球が異常に早く壊れる病態で、骨髄がそれを補おうと赤血球産生を亢進します。
網赤血球数が高値を示し、間接ビリルビンやLDHの上昇が併発することが多く、溶血のマーカーとして評価されます。 - 出血後の回復期
外傷など出血により赤血球が失われたあと、骨髄が造血を活性化することで、一時的に網赤血球が増加します。
このような場合、貧血の進行ではなく“回復傾向”のサインとして扱われます。
【低値を示す場合】
- 再生不良性貧血
骨髄の造血機能が低下することにより、赤血球・白血球・血小板のすべてが減少する疾患です。網赤血球数も低値を示し、骨髄の“再生能力そのもの”が障害されていることを示唆します。厚生労働省の指定難病にも認定されています。 - 腎性貧血
腎臓で産生されるエリスロポエチンが減少し、赤血球の産生が低下することで生じます。
近年では、心不全・腎不全・貧血が互いに悪影響をおよぼし合う「心腎貧血症候群」という概念が注目されており、早期介入が重要とされています。 - 骨髄抑制(薬剤や重症感染症など)
抗がん剤や一部の抗菌薬、ウイルス感染などにより骨髄の造血機能が一時的に抑制されると、網赤血球数が低下します。この場合も、網赤血球は「造血機能の指標」として有用です。
3. 白血球(基準値:3,300~8,600/μL)の検査値
3-1. 白血球の概要
白血球は、体内に侵入した細菌・ウイルスなどに対する防御の最前線で働く血球成分です。
その数や種類の変化を見ることで、減少傾向ならば感染症、増加傾向ならば炎症・アレルギー反応・造血器の疾患(白血病など)の兆候があることを推測することができます。
白血球数にはある程度の個人差があるため、単回の数値だけでなく継続的な変化を追うことが重要です。また一般に、乳幼児では高め、高齢者では低めの傾向があるためそれも考慮に入れます。
白血球数に異常が認められた場合は、白血球の種類(好中球・リンパ球・単球・好酸球・好塩基球)ごとの割合を調べる「白血球分類」が診断に不可欠です。白血球の分類を確認することで、どの免疫系に負荷がかかっているか、また異常細胞の存在も評価することができます。
また一つ理解しておきたいことは、白血球の変化は多くの場合、「病気によって生じた反応(相関関係)」であり、白血球自体が病気を引き起こすケース(因果関係)はごく一部に限られます。
例えば、感染やストレスによる好中球やリンパ球の増加は身体の防御反応に過ぎませんが、白血病のように白血球の異常そのものが病気の本体となる場合もあります。
3-2. 白血球の分類
白血球は大きく「顆粒球(好中球・好酸球・好塩基球)」と「無顆粒球(リンパ球・単球)」の2系統に分類されます。これらはそれぞれ異なる機能を持ち、感染防御・アレルギー反応・炎症調整など、免疫系のさまざまな局面で重要な役割を担っています。
以下に、各白血球の基本的な働きと、増加時に考えられる主な疾患や状態を簡潔にまとめます。
白血球は、大きく顆粒球系と無顆粒球系に分けられます。顆粒球には、好中球、好酸球、好塩基球があり、無顆粒球には、リンパ球、単球と計5種が存在し、各々がアレルギーに対して個別の役割を果たしています。下記に簡単な役割を記した表を記します。
| 分類 | 種類 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 顆粒球 | 好中球 | 38~74% | 細菌の貪食・殺菌、 急性炎症時に増加しやすい |
| 好酸球 | 0~8.5% | 寄生虫の排除、 アレルギー(特に即時型)の調整 | |
| 好塩基球 | 0~2.5% | ヒスタミンなどを放出し、 アレルギー反応に関与 | |
| 無顆粒球 | リンパ球 | 16.5~49.5% | T細胞:免疫全体の調整役 B細胞:抗体を産生 NK細胞:ウイルス感染細胞や腫瘍細胞の排除 |
| 単球 | 2~10% | 感染初期に異物を貪食、 マクロファージに分化し、抗原提示や他白血球の免疫補助に関与 |
3-3. 白血球数が高値を示す場合
白血球数が10,000〜30,000/μL程度の上昇であれば、感染症(特に細菌感染)や炎症性疾患、急性心筋梗塞などの非感染性炎症が疑われます。また、この程度の増加は妊娠や強い精神的・身体的ストレス、喫煙など、生理的・生活習慣的な要因でも認められることがあります。
一方、50,000/μL以上の高度な増加がみられる場合は、腫瘍性疾患(特に白血病などの造血器腫瘍)が強く疑われます。こうした病態では、正常な分化を経ない未熟な白血球(芽球)が血液中に出現することが特徴的です。
また、白血球増多の背景を読み解くには、白血球の「種類ごとの増減」を把握することが非常に重要です。以下に、各白血球が増加したときに関連する代表的な疾患や状態をまとめました。
3-3-1. 好中球増加症(7,500/μL以上)
好中球の血中での増加は主に急性炎症や感染症を反映しており、その背景にある病態の見極めが重要となります。
| 区分 | 関連疾患・要因 | 解説・補足 |
|---|---|---|
| 感染症 | 主に細菌感染; 肺炎、敗血症、虫垂炎など | 細菌感染症が最も代表的な原因。 ウイルス感染ではむしろ減少することが多い。 |
| 血液腫瘍 | 慢性骨髄性白血病 真性多血症など | 白血球が過多になり、血液の中に「通常なら骨髄にしかいない未熟な白血球」が現れることも。これが見られる場合は、血液の病気が隠れている可能性があり、精密な検査が必要。 |
| 外的ストレス | 火傷、外傷、出血、術後など | 組織損傷による炎症反応で好中球が動員される。 |
| 内分泌・代謝性疾患 | クッシング症候群、ステロイド薬投与、糖尿病性ケトアシドーシス、痛風 | ステロイドは好中球の血中滞留時間を延長させ、増加に見える。 |
| 生理的・その他 | 妊娠、喫煙、激しい運動、強いストレス、肉体疲労 | 一時的な増加。特に妊娠後期や喫煙者で軽度の増加が見られることがある。 |
3-3-2. 好酸球増加症(700/μL以上)
好酸球の増加はアレルギー疾患や寄生虫症、特定の自己免疫疾患などを示唆することがあります。背景にある疾患の特定が重要です。
| 分類 | 関連疾患・要因 | 解説 |
|---|---|---|
| アレルギー疾患 | 気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、薬剤アレルギー | アレルギー反応に関わる白血球として最も有名です。気道や皮膚などで炎症を起こします。 |
| 寄生虫感染症 | 回虫、鞭虫、鉤虫、トキソカラ症など | 特に組織内に侵入するタイプの寄生虫で上昇しやすいです。海外渡航歴なども重要な手がかりになります。 |
| 自己免疫疾患・膠原病 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、全身性強皮症など | 好酸球が関与する自己免疫性炎症。血管や肺などに障害を起こします。 |
| 血液腫瘍 | 好酸球性白血病、骨髄増殖性腫瘍(慢性好酸球性白血病など) | 好酸球が腫瘍化して増殖する稀な疾患。高値が持続する場合は注意が必要です。 |
| その他の原因 | アジソン病(副腎皮質機能低下症)、皮膚疾患(痒疹など)、照射線放射後 | ホルモン異常や皮膚の慢性炎症、薬剤の影響でも好酸球が増えることがあります。 |
3-3-3. 好塩基球増加症(150/μL以上)
| 分類 | 関連疾患・要因 | 解説・補足 |
|---|---|---|
| 内分泌疾患 | 甲状腺機能低下症 | 基礎代謝の低下に伴って好塩基球が軽度に増加することがある。橋本病などが代表的。 |
| 血液腫瘍 | 慢性骨髄性白血病(CML)、その他の骨髄増殖性腫瘍(MPN) | CMLでは著しい好塩基球増加が特徴。真性多血症や本態性血小板血症などのMPNでも増加することがある。 |
3-3-4. リンパ球増加症
リンパ球の増加は、ウイルス感染や慢性感染症、あるいは一部の血液腫瘍で認められます。年齢や症状、持続期間をふまえて、良性か悪性かを見極めることが重要です。
| 分類 | 疾患・要因 | 解説・補足 |
|---|---|---|
| 絶対的リンパ球増加(4,000/μL以上) | ウイルス感染症(感染性単核球症、風疹、麻疹、肝炎など) | 特にEBウイルスやサイトメガロウイルスによる感染で顕著に増加。感染症などに反応して体が防御反応を起こしている際に見られる。 |
| 百日咳 | 細菌感染だが、リンパ球増多が特徴的(リンパ球の末梢血残存時間延長による)。 | |
| 慢性リンパ性白血病(CLL)・成人T細胞白血病(ATL)などの血液腫瘍 | 異型リンパ球の持続的増加。特にCLLでは高齢者に好発し、無症候で見つかることも。 | |
| 相対的リンパ球増加 | 好中球減少を伴う病態 | 実際にはリンパ球数が増えているわけではなく、他の白血球(特に好中球)の減少により相対的に高く見える状態。 |
3-3-5. 単球増加症(1,000/μL以上)
| 分類 | 疾患・要因 | 解説・補足 |
|---|---|---|
| 感染症 | 結核、亜急性細菌性心内膜炎、マラリアなど | 特に慢性感染症でみられやすく、病原体の貪食や炎症の調整に関与。 |
| 血液腫瘍 | 慢性骨髄単球性白血病(CMML) | 骨髄系の腫瘍。高齢者に多く、単球の著しい増加がみられます。 |
3-4. 白血球数が低値を示す場合
3-4-1. 好中球減少症(1,500/μL以下)
好中球は減少すると感染症に対する抵抗力が著しく低下し、日和見感染のリスクが高まる可能性があります。
特に500/μL以下では「顕著な好中球減少」とされ、重篤な細菌感染の発症リスクが高まるため、注意深い観察と迅速な対応が求められます。
| 分類 | 疾患・要因 | 解説・補足 |
|---|---|---|
| 感染症 | ウイルス感染(インフルエンザ、麻疹、EBウイルスなど)、重度の感染(敗血症) | ウイルス感染では骨髄抑制が起きやすく、一時的な好中球減少が見られる。 |
| 薬剤性 | 抗がん剤、抗菌薬(ST合剤など)、抗てんかん薬など | 骨髄抑制や免疫介在性による好中球破壊が原因。重篤な薬剤性無顆粒球症に注意。 |
| 血液疾患 | 無顆粒球症、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群(MDS) | 骨髄での造血能の低下により全血球が減少する。汎血球減少の一環として出現。 |
| 自己免疫 | 全身性エリテマトーデス(SLE)、自己免疫性好中球減少症 | 自己抗体によって好中球が破壊される。慢性的な経過をとることがある。 |
| その他 | 放射線被曝、など | 強いストレスや全身性のダメージにより、一時的に好中球が枯渇する。 |
3-4-2. 好酸球減少症(100/μL以下)
好酸球は減少しても臨床的な症状が現れることは少なく、免疫系の他の仕組み(好中球やリンパ球など)が機能を補うため、通常は大きな問題とはなりません。
このため、好酸球減少自体の診断的意義はやや低く、単独では重大な疾患の指標となることはまれです。しかし、副腎皮質ステロイドの投与や、特定の感染症および内分泌異常などの背景病態を推定する手がかりにはなり得ます。
| 分類 | 疾患・要因 | 解説・補足 |
|---|---|---|
| 内分泌系 | クッシング症候群 | コルチゾール分泌亢進による。また、好酸球のアポトーシスを促進。 |
| 薬剤性 | ステロイド投与 | 代表的な原因。好酸球はステロイドに非常に敏感。 |
| 感染症 | 特に腸チフス | 腸チフスに特徴的な所見。 |
| 血液疾患 | 再生不良性貧血、無顆粒球症 | 骨髄での産生低下により好酸球含めた全血球が減少。 |
| その他 | 重度のストレス状態、外傷、大手術 | 急性ストレスによる副腎刺激により、内因性ステロイドが増加することに起因。 |
3-4-3. リンパ減少症(1,000/μL以下)
リンパ球数が減少すると、ウイルス感染や特定の免疫不全症への感受性が高まる一方で、無症状の場合も少なくありません。
| 分類 | 疾患・要因 | 解説・補足 |
|---|---|---|
| 感染症 | ウイルス感染(HIVなど)、結核 | ウイルスによる骨髄抑制や、リンパ球の末梢からの消失が原因。特にHIVではヘルパーT細胞の著明な減少が特徴。 |
| 膠原病 | 全身性エリテマトーデス(SLE) | 自己免疫によるリンパ球の破壊や産生障害。SLEでは診断基準の1つでもある。 |
| 血液疾患 | 再生不良性貧血、悪性リンパ腫の進行例 | 骨髄の造血不全や腫瘍によるリンパ球減少。 |
| その他 | 放射線被曝、抗がん剤投与、栄養失調など | 免疫系の広範な抑制やリンパ球の消耗による減少。 |
3-4-4. 単球減少症(300/μL以下)
単球減少においては、一部の感染症リスクを高めることがあるため、特定の治療が必要になる場合があります。
| 分類 | 疾患・要因 | 解説・補足 |
|---|---|---|
| 感染症 | 重症敗血症 | 全身性の感染や急性感染症で、一時的に単球が減少することがある。 |
| 血液疾患 | 骨髄異形成症候群、再生不良性貧血 | 骨髄機能の低下により、単球を含む全血球系が減少する。 |
| その他 | 放射線被曝、自己免疫疾患 | 広範な造血障害や免疫調整異常により単球も含めた減少がみられる。 |
4. 血小板数の検査値(基準値:15.8万~34.8万/μL)
血小板は主に骨髄でつくられ、常に血液中を循環しています。これは多くの方がご存じかもしれませんが、その重要な役割は、出血時にキズをふさぎ、過剰な血液の流出を防ぐことです。ここでは、血小板の働きを理解するために、まず止血の仕組みについて簡単におさらいしておきましょう。
4-1. 止血のメカニズム
出血時、血液が過剰に体外に流れ出ないよう、私たちの体には巧妙で複雑な止血機構が備わっています。ここではそのうちの主要な2段階、一次止血と二次止血について簡単に紹介します。
(1)一次止血:血小板による“応急処置”
出血のきっかけとなるのは、血管内皮の損傷です。これをスイッチとして、以下のような一連の反応が起こります。
- 血管が収縮し、傷口が狭くなり出血量を抑えようとします。
- 血流に乗っていた血小板が損傷部位に集まり、フォン・ヴィレブランド因子(VWF)などのタンパクと結合して粘着。
- 血小板同士がさらに凝集し、「仮のふた」=一次止血血栓を形成します。
これはあくまで一時的な止血であり、時間が経てば自然に流れてしまうほど脆弱です。
(2)二次止血:凝固因子による“本格補強”
一次止血でできた仮の血栓を、より強固な「かさぶた」へと補強するのが二次止血です。
- 血液中の凝固因子(第Ⅰ〜ⅩⅢ因子)が活性化され、凝固カスケードが開始
- 最終的にフィブリンという網目状のタンパクが生成
- フィブリンが血小板の一次止血血栓を覆うことで、安定した止血血栓が完成
この過程では、ビタミンKやカルシウムイオンなども重要な役割を果たします。
※本来、凝固反応は内因系・外因系他複雑な反応がありますが、ここでは割愛します。
4-2. 血小板数が高値を示す場合
血小板が増加する原因は、大きく2つに分けられます。
一つは血小板を産生する骨髄の腫瘍が原因となる「腫瘍性(本態性)血小板増加症」、もう一つは他疾患によって引き起こされる「反応性(二次性)血小板増加症」です。
4-2-1. 本態性血小板増加症
本態性血小板増加症は、血小板を産生する巨核球が腫瘍性増殖する骨髄増殖性腫瘍の一つです。根治は難しいものの、他の腫瘍に比べ予後は比較的良好とされます。主な治療目標は血栓症の予防であり、一部では出血傾向も認められるため、その管理も重要です。
| 疾患・要因 | 解説・補足 |
|---|---|
| 本態性血小板血症(ET) | 骨髄増殖性腫瘍の一種。JAK2などの遺伝子変異などを伴い、血栓・出血リスクの両面に注意が必要。 |
| その他骨髄増殖背疾患 (慢性骨髄性白血病、真性赤血球増加症など) | ETを含む骨髄増殖性疾患では、稀に急性白血病に進展があるものの、長期の化学療法を受けていない限り、その頻度は非常に低い。その中でも原発性骨髄線維症では、比較的高い頻度で急性白血病に進展する可能性がある。 |
4-2-2. 反応性(二次性)血小板増加症
反応性(二次性)血小板増加症は、外傷や炎症性疾患などの外的要因によって一時的に血小板数が増加する状態を指します。目安としては、血小板数が45万/μL以上とされています。
反応性では、このような血小板の増加は通常一過性であり、血栓や出血のリスクが必ずしも高まるわけではないため、多くの場合は特別な治療は不要とされます。ただし、血小板増加の背景にある基礎疾患への対応が必要となることがあります。
| 疾患・要因 | 解説・補足 |
|---|---|
| 感染症 | 感染症により、炎症性サイトカイン(IL-6など)が肝臓でのトロンボポエチン産生を促進。 |
| 慢性炎症性疾患 | 関節リウマチ、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)などの慢性炎症により持続的に血小板が増加。 |
| 手術後・外傷・出血後 | 一時的な骨髄刺激により血小板産生が増加。特に失血後の回復期に顕著。 |
| 鉄欠乏性貧血 | トロンボポエチン増加の詳細なメカニズムは未解明だが、軽~中等度の血小板増加を伴うことが多い。 |
| 脾臓摘出後 | 脾臓での血小板の貯留がなくなり、血中血小板数が増加。持続的な高値を示すことがある。 |
4-3. 血小板数が低値を示す場合
血小板減少症は、主に「血小板の産生が低下する場合」と「血管内での消費や破壊が亢進する場合」の2つに大別されます。どちらのタイプであっても、背景にある原因や病態に応じた対応が求められます。
4-3-1. 血小板の産生が低下する場合
血小板の産生に関しては、骨髄像の検査を行い、巨核球の数や成熟の状態を確認することで、その原因を正しく見極める必要があります。
| 分類 | 疾患・要因 | 解説・補足 |
|---|---|---|
| 先天性 | 先天性血小板減少症(MYH9異常症、Wiskott-Aldrich 症候群など) | 遺伝子異常が原因となり、生まれつき血小板数が低値を示す疾患群。臨床上は血小板の大きさにより分類。 |
| 骨髄障害 | 再生不良性貧血 | 骨髄の造血幹細胞の障害により、他すべての血球が減少。重度に進行で致死的より、早期治療が必要。 |
| 骨髄異形成症候群(MDS) | 異常な造血により血小板を含む各系統が減少。年齢により発症率が上昇、急性骨髄性白血病への進展に注意。 | |
| 骨髄浸潤 | 白血病、悪性リンパ腫、癌の骨髄転移など | 腫瘍細胞が骨髄を占拠することで、正常造血が阻害される。巨核球の産生も抑制され、結果として血小板減少に至る。 |
| 薬剤性 | 化学療法薬、一部抗てんかん薬など | 化学療法薬や抗がん剤などの骨髄抑制作用により、一時的に造血機能が低下。通常は可逆的だが、重度の場合は投与中止や治療計画の見直しが必要。 |
4-3-2. 血小板の消費や破壊が亢進される場合
血小板は、出血時に止血機能を発揮する一方で、体内で過剰に消費・破壊されることでも減少します。このタイプの血小板減少では、骨髄での産生は保たれているにもかかわらず、末梢での破壊や消費が増加するのが特徴です。原因は免疫学的なものや感染症、血管内での消費など多岐にわたります。
| 分類 | 疾患・要因 | 解説・補足 |
|---|---|---|
| 免疫性 | 免疫性血小板減少性紫斑病 | 自己抗体が血小板を標的として破壊。成人では慢性化しやすく、プレドニゾロンなどの免疫抑制療法が用いられる。小児ではウイルス感染後の一過性も多い。 |
| 薬剤誘発性血小板減少症 | 一部の薬剤(例:ヘパリン、抗菌薬、抗てんかん薬など)が血小板に対する抗体を誘導し、免疫性に破壊される。中止により回復することが多い。 | |
| 自己免疫疾患に伴う血小板減少 | SLEや抗リン脂質抗体症候群などで、血小板が免疫介在的に破壊される。基礎疾患の治療とともに血小板減少の管理が必要。 | |
| 感染症 | ウイルス性疾患(例:HIV、サイトメガロウイルスなど) | ウイルス感染により血小板が直接破壊されたり、IgGが結合してマクロファージに貪食されたりする。ウイルスによる巨核球抑制の併発にも注意。 |
| 播種性血管内凝固(DIC) | 感染症・悪性腫瘍・産科疾患に伴うDIC | 凝固因子とともに血小板が大量に消費される。血栓と出血が同時に進行するため、早期診断と原疾患の治療が不可欠。 |
| 脾機能亢進(脾腫) | 肝硬変・血液疾患に伴う脾腫 | 脾臓での血小板のプール・破壊が増加。産生は保たれているが末梢血中の血小板が減少する。脾臓摘出が検討される場合も。 |
5. 最後に
たとえば赤血球ひとつをとっても、単に「貧血かどうか」を見るだけではなく、その大きさや形態、数の変化から、背景にある疾患や病態を読み取ることが可能です。
臨床検査の評価は、数値が「高い」「低い」といった単純な判断にとどまりません。そこからどのような疾患が潜んでいるのかを推測し、場合によっては病態の進行を未然に防ぐための重要な手がかりとなるのです。
このように、臨床検査の結果には“数値の裏側”に医師や医療従事者が見逃してはならないヒントが隠れています。
今後も本シリーズでは、日常診療に欠かせない臨床検査の「読み方」や「その先にあるもの」を、実例やエビデンスを交えながらわかりやすく解説していきます。


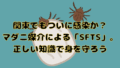
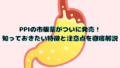
コメント