はじめに
私は、長年にわたり皮膚科の門前薬局に勤務し、多くのアトピー性皮膚炎患者の方々と接してきました。その中で、私が当たり前だと思っていた知識が、実は一般的には十分に知られていなかったり、SNSやインターネット上で誤った情報が広まり、それによって治療の方向性が誤ってしまうケースを多く目にしてきました。
さらに、私自身も幼少期からアトピー性皮膚炎を患っており、長年その症状と向き合いながら生活してきました。その経験から、患者としての視点と専門家としての知識を融合させ、少しでもアトピー性皮膚炎に悩む方々の役に立てればと考えています。
今回、薬局でよく受ける質問や、患者さんが疑問に思うこと。さらに、参照としては「アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2024」である最新の情報を取り入れ、アトピー性皮膚炎に関するQ&Aを作成しました。このQ&Aが、正しい情報を広める一助となり、読者の皆さまがより適切な治療やケアに取り組むための参考になれば幸いです。
1. アトピー性皮膚炎に関する基本的な質問
Q1. アトピー性皮膚炎とはどの様な病気なのですか?
A1. アトピー性皮膚炎は、かゆみを伴う湿疹が繰り返し起こる皮膚の病気です。そして、多くの患者はアトピー素因を持っています。乳児期や幼児期に発症し、子供時代に症状が治まることもありますが、大人になっても再発することがあります。稀に思春期や成人で初めて発症することもあります。
Q2. アトピー性皮膚炎と普通の湿疹を一般的知見からどう見分けるのですか?
A2. アトピー性皮膚炎と一般的な湿疹を見分けるポイントは、かゆみの有無、症状の反復性、そして経過の長さです。見た目がひどくても、かゆみが全くない場合はアトピー性皮膚炎以外の皮膚疾患である可能性が高いです。アトピー性皮膚炎は、乳児では2ヶ月以上、その他の年齢層では6ヶ月以上続き、発症と寛解を繰り返す特徴があります。よって、短期の湿疹はアトピーとは別物となります。
Q3. アトピー性皮膚炎は年齢とともに良くなってきますか?
A3. 一般的に、アトピー性皮膚炎は年齢を重ねるにつれて改善することが多く、特に児童期を過ぎると約7割が寛解するとされています。寛解しやすい要因には、症状が軽度であること、発症年齢が高いこと、他のアレルギー疾患を併発していないことなどが挙げられます。ただし、個人差があるため、成人期まで症状が続く場合もあります。
Q4. 悪化要因にはどの様なものがありますか?
A4. アトピー性皮膚炎の悪化要因には個人差が大きいため、まず自身にとって何が影響しているのかを特定することが重要です。一般的な悪化要因として、髪の毛や衣服との摩擦、乾燥や寒暖差といった物理的刺激が挙げられます。
また、外用薬や化粧品、金属、汗などとの接触によるアレルギー反応や、特定の食べ物による食物アレルギーも原因となることがあります。さらに、黄色ブドウ球菌をはじめとする細菌やマラセチアなどの真菌が皮膚に炎症を引き起こし、症状を悪化させる場合があります。加えて、心理的ストレスも悪化要因の一つであり、特に現代社会においてはその影響が大きいと言われています。
Q5. 合併症には何がありますか?
A5. アトピー性皮膚炎の患者は、気管支喘息、アレルギー性鼻炎や結膜炎、食物アレルギーなどの他のアレルギー疾患を合併することが多い傾向があります。この現象は「アレルギーマーチ」と呼ばれ、乳幼児期にアトピー性皮膚炎を発症した場合、成長とともに他のアレルギー疾患を発症するリスクが高まることが知られています。特に乳児期には、アレルギーが疑われる場合に早期に適切な対処を行うことが重要です。これにより、他のアレルギー疾患の予防や症状の進行を抑えることが期待されます。
2. 治療に関する一般的な質問
Q6. 治療において、推奨度の高い塗り薬は何ですか?
A6. アトピー性皮膚炎の治療では、ステロイド外用薬が最も広く使用されており、高い推奨度があります。副作用の心配はありますが、適切な使用方法を守れば安全で効果的です。また、非ステロイド系の外用薬として、タクロリムス(プロトピック軟膏)、デルコシチニブ(コレクチム軟膏)、ジファミラスト(モイゼルト軟膏)も推奨されています。
Q7. 保湿剤は並行して続けるべきですか?
A7. 皮膚の乾燥はアトピー性皮膚炎の主な症状の一つであり、保湿剤を使用することは非常に重要です。急性期や症状が悪化している際には即効性は期待できませんが、慢性期においてはステロイドや非ステロイド外用薬と併用することでかゆみの改善に役立ちます。また、寛解期においては症状の再発予防において欠かせない存在です。特に、保湿剤は1日1回よりも1日2回塗布する方が効果が高いとされています。継続的に使用することで、皮膚のバリア機能を保ち、症状のコントロールを助けます。
Q8. 症状軽快後、ステロイド外用薬はどう使用するのが良いですか?
A8. 軽症の患者であれば、症状が完治した時点で使用を中止しても問題ありません。しかし、再燃を繰り返す中等度以上の患者では、症状の予防目的でステロイド外用薬を引き続き使用することがあります。その際、次の2つのアプローチがあり、①ステロイドの強さを徐々にランクダウンする方法と②同じランクのステロイドを使用頻度を減らして、週2回程度にする方法です。どちらの方法も有効ですが、研究によると、②の使用頻度を減らす方法がやや優れているとされ、推奨されています。最終的には、個人の生活スタイル、症状の状態などで医師と相談して判断すると良いでしょう。
Q9. ステロイド外用薬は長く続けない方が良いのですか?
A9. ステロイド外用薬は、炎症やかゆみを抑える非常に有効な薬です。ただし、その使用に関しては適切な方法を守る必要があります。一般的に、ステロイド外用薬は「症状がある期間に集中的に使用し、症状が落ち着いたら中止または徐々に減量」という形が推奨されます。これにより、必要最小限の使用で高い効果を得ることができます。
一方で、「長期間使用は良くない」という考え方には、誤解も含まれています。確かに、自己判断で強力なステロイドを長期間使用し続けると、副作用(皮膚の萎縮など)が出る可能性があります。しかし、医師の指導のもとで適切に使用すれば、これらのリスクは最小限に抑えられます。
特に、症状が繰り返し悪化する場合には、プロアクティブ療法(Q13を参照)が効果的です。この方法により、再発を予防し、長期的に症状をコントロールすることが可能です。
重要なのは、「必要なときに、適切な量を、適切な期間だけ使用する」という基本原則を守ることです。自己判断での中止や継続を避け、必ず医師の指示を仰ぎながら治療を進めましょう。
Q10. アトピー性皮膚炎やその治療による眼への悪影響はありますか?
A10. アトピー性皮膚炎の患者では、結膜炎や網膜剥離、細菌・ウイルスによる感染症、さらには白内障や緑内障といった眼疾患が発症する可能性があります。特に重症患者では、角膜炎や結膜炎の発症頻度が高いため、症状が安定している場合でも定期的な眼科受診が推奨されます。
治療薬の影響としては、ステロイド外用薬の使用により、特に高強度のものを頻回に使用する場合に白内障や緑内障のリスクが指摘されています。また、デュピルマブ(デュピクセント皮下注)は結膜炎の発症と関連することが報告されています。
さらに、アトピー性皮膚炎そのものによる眼疾患の背景には、目をこするなどの物理的な刺激が大きな要因として関与しており、特に網膜剥離のリスクを高めるとされています。
Q11. 顔にステロイド外用薬は心配なのですが?
A11. 顔にステロイド外用薬を使用することに対して不安を感じることがあるかもしれません。顔の皮膚は他の部位よりも薄いため、薬剤の吸収が高く、副作用が出やすいことがあるためです。しかし、適切なランクと使用方法を守れば、顔が赤くなるなどの副作用のリスクは大幅に低くなります。
具体的には、原則ミディアムクラス(下から2番目)のステロイドを短期間にとどめ、目の周りや粘膜部の使用は避けて使用します。軽快後は、非ステロイドであるプロトピックやコレクチム軟膏などで症状を維持すると良いでしょう。
Q12. 非ステロイド外用薬の中で、推奨度の高いものはありますか?
A12. 現在発売されている薬の中では、タクロリムス(プロトピック軟膏)、デルコシチニブ(コレクチム軟膏)、ジファミラスト(モイゼルト軟膏)の3種が、有効度と安全性の観点から特に推奨されている薬剤です。また、新薬であるためガイドラインには記載されていませんが、タピナロフ(ブイタマー)も同等の効果と推定され、1日1回の使用で良い利点もあることから、推奨度は高くなると思われます。
NSAIDs製剤に関しては、以前は非ステロイド外用薬の代表として小児などに使用されていましたが、カブレの副作用頻度が比較的高いこと、タクロリムスなどのより有効な薬が発売されたことから、アトピー性皮膚炎に際しては、推奨されない外用薬となっています。
Q13. 外用薬のプロアクティブ療法とはどのようなものですか?
A13. プロアクティブ療法は、アトピー性皮膚炎において再発を防ぐための有効な治療方法の一つです。この療法は、急性期治療によって症状を十分に軽快させた後、保湿剤などの日常的なスキンケアと併用して、ステロイド外用薬やタクロリムス軟膏を週2回程度定期的に使用します。これにより、目に見える症状がなくても皮膚内部に残る炎症を抑え、再悪化を予防することを目的とします。
中等度以上のアトピー性皮膚炎では、一見きれいに見える皮膚でも、内部で慢性的な炎症が持続しているケースが多く、それが再発の原因となります。このような隠れた炎症に対処する点でプロアクティブ療法は非常に有用です。ただし、十分に皮膚炎を改善した後でなければ効果が期待できず、症状が残っている状態で始めることは適切ではありません。よって、必ずこの療法においては、自己判断ではなく専門の皮膚科医の指導の元で行うことが重要です。
Q.14 小児と成人で治療のアプローチが異なる理由は?
A14. 小児と成人では、皮膚の構造や生理的特性、生活環境などが異なるため、治療のアプローチも変わります。
・皮膚の特性の違い
小児の皮膚は成人に比べて薄く、バリア機能が未発達です。そのため、薬剤が経皮吸収されやすく、外用薬の使用には、ステロイド外用は1〜2ランク弱い薬剤を使用するなど特に注意が必要です。一方で、成人は皮膚のバリア機能が安定しているため、小児ほど薬剤の吸収に配慮する必要はありません。
・生活環境や悪化要因の違い
小児は保育園や学校などの集団生活で感染症やアレルゲンにさらされる機会が多いため、これが皮膚炎の悪化要因となることがあります。また、衣服やおむつ、家庭環境の湿度管理など、小児特有の生活環境が症状に影響を与える場合があります。一方成人では、職場環境やストレス管理などを重視する必要が高いです。
・治療目標の違い
小児と成人ともに、日常生活に支障がなく薬物治療の最小化が目的ではあります。小児はそれに加え、成長と発達への影響を最小限にすることが治療の重要な目標です。成人にとっては、見た目などの観点も含め、QOL(生活の質)も重要視されます。
Q15. アトピー性皮膚炎の最終的な治療目標はなんですか?
A15. アトピー性皮膚炎は、年齢とともに症状が自然と消失する方もいれば、長期間にわたって症状が続いたり、悪化するケースもあります。現在の医療では、アトピー性皮膚炎を完全に治癒させる薬は存在しません。そのため、現実的な治療目標は、症状を十分に抑えたうえでその状態を維持し、患者さんが日常生活を快適に送れるようにすることです。
具体的には、「症状がない、または非常に軽微であること」「日常生活に支障がないこと」「薬物療法が最小限で済む状態に到達すること」が目標となります。
また、治療においては、完璧を求めすぎないことも重要です。過度な期待やプレッシャーを感じると、精神的な疲労がたまり、かえって悪化を招く可能性があります。「普段の生活で症状がほとんど気にならない程度で十分」と考え、病気とうまく付き合っていくことが、長期的な治療成功の鍵といえるでしょう。
3. 飲み薬や他の治療に関する質問
Q16. かゆみ止め(抗ヒスタミン薬)は飲んだ方が良いのでしょうか?
A16. 抗ヒスタミン薬は、市販でも購入可能であり、比較的長期間の服用でも安全性が担保されている薬です。しかし、アトピー性皮膚炎に対する単独使用においては、臨床試験で明確な有効性が示されていないのが現状です。皮膚のかゆみは主に炎症が原因であり、ヒスタミンだけが関与するわけではないため、抗ヒスタミン薬単独では症状の改善効果は限定的です。
ただしステロイド外用薬およびタクロリムスなどの非ステロイド外用薬と併用することで、かゆみの軽減に相乗効果をもたらす可能性が示唆されています。そのため、外用薬だけでは十分な効果が得られない場合や、夜間のかゆみによる睡眠障害がある場合などには、抗ヒスタミン薬の服用を検討する価値があると考えられます。
さらに、アレルギー性鼻炎やじんま疹、花粉症といった他のアレルギー症状を併発している場合には、抗ヒスタミン薬はより有効性を発揮します。これらの症状に対しては、抗ヒスタミン薬を定期的に服用することで、総合的なアレルギー症状の改善が期待できます。
Q17. かゆみ止め(抗ヒスタミン薬)はどれがよく効くのですか?
A17. 抗ヒスタミン薬は、医療用医薬品として少なくとも10種類以上が存在し、市販薬としても多くの種類が販売されています。そのため、どれが最も効果的なのかを選ぶのに迷うことがあるかもしれません。
結論として、どの抗ヒスタミン薬が最も効果的かは一概には言えません。効果や副作用には個人差があるため、使用者自身がどの薬が最も効果的で副作用が少ないかを把握することが重要です。特に、かゆみやその他の症状に対する効果は人それぞれで異なる場合が多く、副作用の代表例である眠気の程度も同様に個人差があります。
即効性を期待するというのであれば、ジフェンヒドラミンやd-クロルフェニラミンなどの第一世代抗ヒスタミン薬が有効になります。ただし、眠気や口渇などの副作用が出やすい問題もあります(よく風邪薬が眠くなりやすいと言うのは、この成分が入っているせいです)。一方、定期で効果を安定させたい場合は、フェキソフェナジンやエピナスチンなどの第二世代以降の抗ヒスタミン薬が良いでしょう。副作用もほとんどの薬ではかなり軽減されています。
選択のポイントとしては、日常生活に支障をきたさない副作用の少ない薬を選ぶことが基本です。例えば、眠気が強い仕事や学業中には第二世代抗ヒスタミン薬を、夜間にかゆみがひどい場合には第一世代抗ヒスタミン薬を使用する、といった使い分けも有効です。
Q18. かゆみどめ(抗ヒスタミン薬)は続けると効き目が弱くなるというのは本当ですか?
A18. 抗ヒスタミン薬を長期間使用すると効果が弱くなるという意見を耳にすることがありますが、基本的にはそのようなことはありません。抗ヒスタミン薬の作用機序において、薬効が時間とともに減少することを示す明確なエビデンスはありません。多くの研究においても、長期間使用しても効果が維持されることが示されています。
仮に薬の効き目が弱くなったと感じる場合は、皮膚炎が進行または悪化し、薬の効き目が追いつかず、効果が薄れたように感じるケースがほとんどです。
Q19. 長く重症化が続いていますが、何か良い薬はないですか?
A19. アトピー性皮膚炎が重症化すると、かゆみや炎症が悪化して広範囲に広がり、外用薬だけでは対応しきれなくなる場合があります。この状態では、かきむしることでさらに症状が悪化し、いわゆる「負のスパイラル」に陥りやすくなります。
以前は、重症例に対して免疫抑制剤のシクロスポリンやステロイドの内服薬が主な治療法でした。しかし、これらの薬剤は全身性の免疫抑制効果が強いため、副作用のリスクが高く、長期使用には不向きでした。
近年では、より特異的に炎症を抑える薬剤が登場しています。たとえば、内服薬のJAK阻害薬(バリシチニブなど)や、注射薬である生物学的製剤(デュピルマブ、ネモリズマブなど)は、炎症の原因物質をピンポイントで抑える作用を持ちます。これらの薬剤は、比較的安全性が高く、長期間の治療にも適しているため、重症化したアトピー性皮膚炎の治療選択肢として注目されています。
Q20. 他にアトピー性皮膚炎に推奨されている治療法はありますか?
A20. ある程度重症度の高いアトピー性皮膚炎では、強力なステロイド外用薬や生物学的製剤を用いない限り、完全な寛解に至ることは難しい場合があります。一方で、中等度以下の症状で基本的な治療が効果を示さなかった場合、以下のような治療法が考慮されます。
・漢方治療
アトピー性皮膚炎における漢方療法の目的は、患者の体質を改善する「本治」と、皮疹を含む症状を抑える「標治」の両面から治療を行う点にあります。画一的に「アトピー性皮膚炎にはこの漢方薬が効く」というものではなく、個々の患者の体質や症状に合わせて処方が選択されます。よく「標治」に対し使用される方剤として、消風散(皮膚の炎症やかゆみを抑える)、十味敗毒湯(化膿性疾患に対応する)、温清飲(乾燥を伴う炎症の改善)などが挙げられます。
・ナローバンドUVB療法
難治性のアトピー性皮膚炎に対して、紫外線療法が有効な場合があります。紫外線には皮膚の免疫を抑制する作用がありますが、一部の波長は皮膚がんリスクを増加させる可能性が指摘されています。そのため、現在では皮膚がんリスクを低減しつつ効果を発揮するナローバンドUVB(311-313nmの波長)が用いられることが推奨されています。
4. 妊娠や授乳に関するQ&A
Q21. 妊娠や授乳中の母親の食事制限は子の発症予防につながりますか?
A21. 妊娠中や授乳中の母親が特定の食物を制限することが、子どものアトピー性皮膚炎の発症予防につながるという明確な科学的根拠はありません。
アトピー性皮膚炎の発症には、遺伝的要因や環境因子が大きく関与しています。食物アレルギーもその一因となることがありますが、妊娠中の食物摂取が直接的に子どものアレルギーリスクを増減させるという確固たる証拠は見つかっていません。
特にピーナッツアレルギーについては、かつて妊娠中の摂取制限がアレルギー予防に有効であると考えられていました。しかし、近年の研究(例えばLEAP試験など)では、早期の摂取がむしろアレルギー発症リスクを低減する可能性が示唆されました。その結果、ピーナッツを含む特定の食物の摂取制限は推奨されなくなっています。
また、日本小児アレルギー学会のガイドラインでも、妊娠中や授乳中の母親がアレルゲンを避けることがアトピー性皮膚炎の予防につながるという推奨はされていません。むしろ、バランスの取れた栄養摂取が母子ともに健康を維持するために重要です。
Q22. 妊娠や授乳中でのステロイド外用薬は安全ですか?
A22. 適切な使用方法と使用量を守れば、ステロイド外用薬の使用は妊娠・授乳中でも安全性が高いとされています。これまでの観察研究によれば、先天奇形や低出生体重などのリスクにほとんど影響を与えないことが確認されています。また、授乳中の使用についても、皮膚に塗布された薬剤が乳汁に移行する量は極めて少なく、乳児への影響はほとんど懸念されません。
ただし、より安心して使用するために、妊娠中は強ランクのステロイド外用薬の長期連用を控えたり、塗布部位が乳児の口に触れる可能性がある場合、薬剤が完全に拭き取られた状態で授乳を行うようにするとなお良いでしょう。

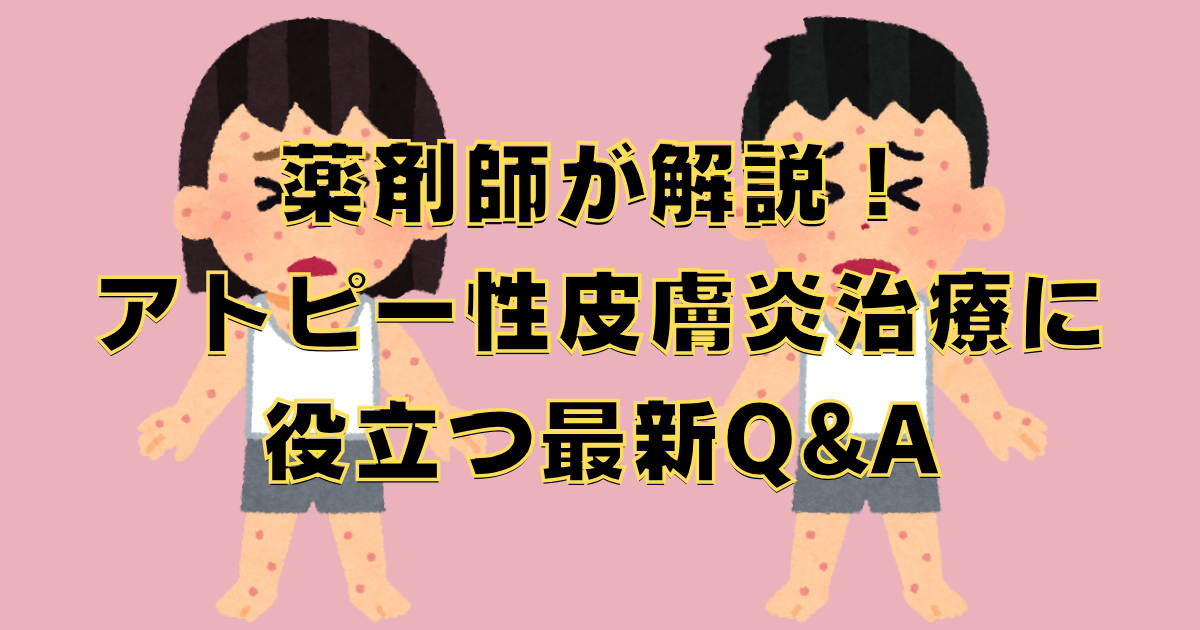


コメント