※本記事にはアフィリエイト広告を利用しています。商品リンクを経由して購入された場合、当サイトに収益が発生することがあります。
1. はじめに 〜薬を正しく服用する意義〜
薬を正しく服用することは、その効果を最大限に引き出し、副作用を最小限に抑えるために非常に重要です。正しい服用法を理解し実践することで、薬の治療効果を最大限に活用することができます。薬によっては指示された飲み方以外では、薬の効果が十分に発揮されなかったり、逆に過剰に作用したりすることもあります。
- 効果の最大化
薬は適切なタイミングで服用することで、体内の吸収率や薬の効果が大きく変わることがあります。一例としては、一部の血糖降下薬(α-グルコシダーゼ阻害剤など)は食後に服用すると効果がほとんど得られないことがあります。正しいタイミングで服用しないと、毎日飲んでいるにもかかわらず、期待した効果が現れないこともあります。 - 副作用の最小化
薬を誤ったタイミングで服用すると、思わぬ副作用が出る恐れがあります。薬は正しく服用することを前提に作られているため、自己判断での服用は避けましょう。例えば、特に鎮痛剤など胃に負担がかかるものは、空腹時の服用で胃が荒れやすくなったりします。 - 治療の効率化と適正化
医師は正しく薬を飲んでいることを前提に治療方針や薬を設定します。適正な薬の服用により、治療が無駄に長引くことを防ぎ、余計な薬を服用する必要がなくなります。治療が効率的に進むことで、患者の負担も軽減されます。
2.服用時間の理解
服用時間を正しく理解していない方は意外と多いです。薬を毎日しっかり飲んでいるのに効き目が鈍い場合、例えば、食前服用の薬を食事の直前に飲んでしまうケースがあります。薬の効果や副作用を考慮し、できる限り指示された服用時間を守ることが重要です。
ただし、指定されていてもいつ服用しても問題ない薬もありますし、同じ「食前」「食後」でも、吸収率を上げる、または妨げる、副作用率を上げる、下げるなどその意義が異なる場合があります。
2-1. 起床時
起きてすぐに薬を飲むことです。ただし、起床直後でなくても、朝食の30分前までに服用すれば問題ありません。一部の骨粗しょう症の薬(ビスホスホネート系内服薬)などは、このタイミングで服用する必要があります。その理由は以下のとおりです。
- 胃の中が空の状態で他の影響を受けない
- 再び横になることで、飲んだ薬が消化管の途中で停滞することを防ぎ、それによる副作用を避ける
2-2. 食前
食事のおおよそ30分前を指します。5〜10分程度の前後は許容範囲ですが、目安は30分前です。胃の中で薬と食事が混ざる状態を避けるためであり、30分以内という指示ではありません。代表的な薬には、消化管の働きを良くするドンペリドン、抗アレルギー薬のビラノスチンなどがあります。
- 食事の影響を受けないようにする
- 効果が増強または減弱するのを防ぐ
- 副作用が増強するのを防ぐ
- 食事前に飲むことで、食事の時間や食後に胃腸を活発にさせる
2-3. 食後
食後30分以内のことを指します。いつ飲んでも良いとされる薬の服用なども、忘れないように食後と指示されている薬も多くあります。大部分の内服薬はこれに該当します。
- 食べ物により胃の刺激を軽減させる
- 食事に含まれる脂肪により吸収されやすくする
- 習慣化しやすく、飲み忘れを減らしやすい
2-4. 食間(空腹時)
食事と食事の間を指し、およそ食事前後2時間以上を指します。食事の最中と混同されることがありますが、全く異なります。漢方薬は一般的に食事の影響を受けないように飲むと良いことから、ほとんどが食前もしくは食間に服用することになります。
- 食事の影響を最小限にする
2-5. 食直前・食直後
おおよそ食事前から5分以内、食事後から5分以内を指します。例としては、食直前の薬には糖尿病治療薬のボグリボース、食直後の薬であると抗真菌薬のイトラコナゾールなどがあります。
- 薬の効果を食事の時間と合わせて最大限に引き出す
- 食事の脂肪などにより吸収率を上げる
- それ以外の服用時間では効果がほぼ出ず、副作用のリスクだけが残る
3. 飲み方のポイント
3-1. 一般的なポイント
(1)コップ一杯の水で飲む
おおかたの薬は水に溶けやすいように設計されています。そのため、唾液だけで飲んだり、少量の水で飲むと、薬が十分に溶けず、吸収が遅れることがあります。また、薬が消化管の途中で引っかかり、潰瘍を引き起こすリスクを避けるためにも、コップ半分から一杯の水で飲むことが推奨されます。
(2) 飲み忘れた場合の対応を事前に確認しておく
どんなに重要な薬であっても、うっかり飲み忘れてしまうことは誰にでも起こり得ます。しかし、飲み忘れた際の対応は薬によって異なり、自己判断で服用すると副作用や過量投与などのリスクがあるため注意が必要です。以下に例をいくつか挙げておきます。
- 1日1回の薬の場合
「次の服用まで○時間以上あれば飲んで良い」「気づいたらすぐ飲む」などが考えられます。 - 週1回の薬の場合
対応は薬ごとによることとなり、- リウマチの薬であるメトトレキサート(リウマトレックス®︎)の場合は、その週は飛ばして次の週に飲むのが原則。
- アレンドロン酸などの骨粗しょう症治療薬では、翌朝にすぐ飲み、次週から元のスケジュールに戻すとされています。
3-2. 各剤型のポイント
3-2-1. カプセル剤
カプセルはその形状や大きさから、飲みにくい剤型の一つです。口内が乾いていると、カプセルが喉に張り付くことがあるため、まずは口に水を含んで潤すことが大切です。また、軽く下を向いて飲むことをお勧めします。上向きに飲むと気道が開き、誤嚥のリスクが高まります。カプセルは水に浮くため、下を向くことで飲みやすくなります。顎を少し引いてゴックンと飲むと、意外とスムーズに飲み込めます。
3-2-2. 散剤
- 少量の水に溶かす方法
特にドライシロップや溶けやすい粉薬の場合におすすめです。しっかり溶かして、口内に残らないように残りの水で最後まで飲み切りましょう。 - 口内に水を溜めて落とし込む方法
私が一番推奨する方法です。やや上向きで口内に少量の水を溜め、そこに薬を入れてすぐに残りの水で流し込むやり方です。直接薬を入れる方法と比較して、口内に薬が張り付かず、苦味などの風味がかなり軽減される利点があります。
粉薬を直接口の中に入れて飲む方がおられますが、口の中に広がりへばりついてかなり飲みづらいかと思われます。
3-3. 服用補助グッズの活用
- 服薬補助ゼリー
- 【和光堂】 お薬じょうず服用ゼリー ゼリータイプ 150g(10回分)×6個 りんご味↗️
→ 苦い薬や粉薬を飲みやすくするための服薬補助ゼリーです。薬の溶け出しや吸収に影響を与えにくく、医療現場でも広く使用されています。水でむせやすい方や子ども、高齢者の服薬サポートに有用です。
- 【和光堂】 お薬じょうず服用ゼリー ゼリータイプ 150g(10回分)×6個 りんご味↗️
- オブラート
苦い粉薬や服用しにくい薬を飲む際に便利です。オブラートには丸型(自分で包むタイプ)と袋型(あらかじめ袋状になっているタイプ)があり、用途や好みに応じて使い分けができます。いずれもでんぷん由来で、薬の吸収や効果に影響を与えることはありません。- 丸型:国光オブラート 丸型特大 200枚入↗️
自分で薬を包む必要がありますが、非常に安価で補助器具も付属しており、毎日頻用する方向け。 - 袋型:国光オブラート 袋型 50枚入 ×5個セット↗️
箱に立ててそのまま使用でき、外出先でも手軽に服用できるタイプです。5個セットで、家族など皆で使用することもできます。
- 丸型:国光オブラート 丸型特大 200枚入↗️
※オブラートの使用上の注意
オブラートも正しく活用して飲めば、どんなに苦い粉薬でもスルッと飲み込めます。量が多い時は複数回に分けましょう。コツは、適量の薬を包んだ後服用する直前に一瞬水につけることです。これをしないと、オブラート自体が口内に張り付いたり、破れてしまうことがあります。
4. 注意すべき飲食物
4-1. コーヒーやお茶、ウーロン茶など
これらの飲料には、「カテキン」や「カフェイン」といった薬の作用に影響を及ぼす可能性のある成分が含まれています。従来、カテキンが鉄剤と結合して吸収を妨げると言われてきましたが、近年の研究では「通常の飲用レベルでは大きな影響はない」とする報告も増えてきています。一方で、カフェインには注意が必要です。
カフェインは中枢神経を刺激する作用を持ち、
- 睡眠薬や抗不安薬などの効果を弱める可能性
- 気管支拡張薬(テオフィリンなど)の副作用を増強する可能性
が報告されています。特に薬の効果を最大限に活かす必要がある場合には、服薬前後のカフェイン摂取を控える方が望ましいでしょう。
むしろ、注意すべき成分としては、カテキンよりもカフェインの方が気をつけなければいけないと言われています。興奮作用があり、向精神薬や睡眠薬の効果を弱めたり、気管支拡張薬の副作用発現を高める可能性もあります。
4-2. 牛乳などの乳製品
牛乳やヨーグルトなどの乳製品には、カルシウムが豊富に含まれています。このカルシウムは、一部の抗菌薬(ニューキノロン系やテトラサイクリン系)と結びつきやすく、薬の吸収を妨げてしまうことがあります。結果として、薬の効果が十分に発揮されなくなる可能性があります。
また、カルシウムを補うための薬(カルシウム製剤やビタミンD3製剤など)を服用している場合には、乳製品を摂りすぎると高カルシウム血症という副作用が起きることがあります。めまいや吐き気、便秘、場合によっては腎臓に負担がかかることもあるため、摂取量には注意が必要です。
さらに、乳製品に多く含まれる脂肪分も、薬の吸収に影響を及ぼす可能性があります。薬によっては、吸収が遅れたり、効き目が不安定になることもあるため、薬を服用する際には乳製品はできるだけ避けた方がよいとされています。
4-3. 青汁、クロレラ、納豆など
青汁やクロレラ、納豆にはビタミンKが多く含まれています。ビタミンKは血液を固まりやすくする物質の生成を助ける働きがあり、ワルファリンカリウム(ワーファリン®)を服用している方は、薬の十分な効果を得られなくなる可能性があるため、これらの食品は摂取を控えるよう指導されており、「血液サラサラの薬を飲んでいるときは納豆はダメ」という話は結構有名ですよね。
ただしこれは、「血液をサラサラにする薬=すべて避ける対象」ではなく、ワルファリンKの作用を弱めてしまうビタミンKが含まれるものに限られるためです。たとえば、低用量アスピリン製剤(バイアスピリン®︎)やクロピドグレル(プラビックス®︎)などの抗血小板剤には、この影響はありません。
4-4. グレープフルーツジュース
グレープフルーツジュースには薬の代謝酵素の働きを抑える成分が含まれており、一部の薬の血中濃度を上昇させ、作用が強く出すぎることがあります。特に高血圧治療薬(Ca拮抗薬)や脂質異常症治療薬、免疫抑制剤などに影響を与える恐れがあります。
4-5. セント・ジョーンズ・ワート(SJW)
ハーブ系のサプリメントとして知られるSJWにも、薬との相互作用が報告されています。この成分は、CYP3A4という酵素の働きを強めてしまうため、一部の薬は分解されやすくなり効き目を弱めてしまうことがあります。
さらに、SJWは脳内のセロトニンの取り込みを妨げることでその効果を高めることもあるため、抗うつ薬(特にSSRIやMAO阻害薬など)と一緒に使うと、薬の作用が強まりすぎて「セロトニン症候群」という副作用を起こす危険性もあります。
4-6. 食物による影響があるが明確な指示がないケースも
これまでに「食前」「食後」「空腹時」など、服用タイミングの違いによって薬の吸収や効果が左右されることを紹介してきました。しかし実は、そうした明確な指示が薬袋に書かれていない薬であっても、食事の影響を受けることがあります。
今回は一例として睡眠薬を取り上げますが、以下のように薬によって異なる影響を及ぼす恐れがあります。
- クアゼパム(ドラール®︎)
脂肪を多く含む食事によって吸収が促進され、眠気やふらつきなどの作用が強く出すぎる可能性があります。 - スボレキサント(ベルソムラ®︎)
食後に服用すると吸収が遅れ、入眠までに時間がかかることが報告されています。 - ラメルテオン(ロゼレム®︎)
食事と一緒に服用すると吸収量が減少し、十分な効果が得られにくくなります。
これらは、薬袋には「就寝前」や「寝る前」としか記載されていないことが多く、服薬指導の際に薬剤師から説明があったり薬の説明書(薬情)自体に記載はあっても、時間が経つと忘れてしまうケースもあります。
よって、薬袋には記載がない場合でも、服用のタイミングや食事との関係が重要なこともあるという点は、覚えておきたいポイントです。
5. 特殊な服用法である剤型
5-1. 舌下錠
文字通り舌の下に入れて、口腔粘膜から溶かして吸収させる薬剤のことです。適正な効果を得るためにも、かんだり飲み込んだりしてはいけません。主に急いで効果を得たい時、狭心症の薬であるニトロペン®︎や、
5-2. 徐放剤
薬の成分が徐々に溶け出すように設計されている薬です。薬の効果を持続させ、飲む回数を減らしたり、毒性を減らすこともできます。徐放剤も噛み砕いたりすることで、体内に有効成分が急激に溶け込み、効きすぎたり副作用が多く出たりなど弊害がでる恐れもあります。徐放錠の中でも、薬品名の最後に徐放錠とついていない場合があります。
5-3. チュアブル錠
チュアブル錠とは、口内で噛み砕いて服用する錠剤をいいます。噛み砕くことで、錠剤が苦手な小児にも飲みやすく設計されています。また水なしでも飲めたり、時間はややかかりますが口内で溶かして飲んでも良いとされています。そのまま飲み込んでも消化管で溶けはしますが、吸収が遅れる可能性があるためしっかり噛み砕くことが推奨されます。
5-4. 口内崩壊錠(OD、D、RM錠)
口内で水がない状態でも、素早く溶けて飲むことのできるタイプの錠剤です。普通の錠剤やカプセル剤を飲み込むことが苦手な方や、ひどい頭痛や吐き気などで水が飲み込めない方に特に推奨されます。注意点として、誤嚥や薬が途中で止まるのを防ぐため、寝たままの状態で水なしでは飲めません。また溶けやすいため、開封後長時間放置したり、濡れた手で触らないようにしましょう。
5-5. その他の剤型
錠剤には、さまざまな工夫が施されたタイプがあります。たとえば、「腸溶錠」は胃酸による分解を避け、有効成分を腸で溶かして吸収させるための剤型です。これにより、胃への刺激を防いだり、成分の効果を狙った部位で発揮させることができます。
また、「糖衣錠」や「フィルムコーティング錠」は、薬の苦味やにおいを軽減したり、成分の安定性を保つ目的でコーティングが施されています。
いずれも、意図的に工夫が施されているため、かみ砕いたり割ったりせず、コップ1杯程度の水でそのまま飲むことが大切です。
6. 正しい薬の服用法のQ & A
Q1.外出時に薬を飲みたい場合はどうしますか?
A1. 外で薬を飲む場合は、まず水を手に入れることを最優先してください。どうしても水が手に入らない場合は、唾液をある程度溜めて薬を飲むこともできます。ただし、多めの水で飲まなくてはいけないものは服用を避け、舌の上で溶かさないように注意しましょう。また、特定の薬は水なしでの服用を推奨しないものもあるため、事前に薬剤師に相談しておくことが大切です。外出時には、小さなペットボトルなどの持ち歩き用の水を準備しておくと安心です。
Q2. 薬がどうしても飲めない。噛み砕いて潰したり、カプセルから外して飲んでも良いですか?
A2. 基本的にはそのままの状態で飲むのが理想です。砕いたりすることで、吸収しにくくなり効果に問題が出たり、胃が荒れやすくなる他、大きな危険性を増すこともあります。まず、薬をもらうときに相談し、自分の飲みやすい剤型に変更してもらいましょう。中には砕いたり脱カプセルしても問題がない薬もあるため、その薬がそれに適しているかを必ず薬剤師に確認しましょう。どうしても無理そうならば、別の類似作用の薬で飲みやすいものもあるかもしれないので、気軽に薬局で相談してください。
Q3. いつも食後服用を忘れてしまうのですが、どうしたら良いでしょうか?
A3. あらかじめ食卓に出しておくことが理想です。また外食が多い場合は、必ず財布かスマホケースに数回分入れておきましょう。それでも忘れることがあるなら、食後指示の薬であっても、食後以外に飲んでも問題ないものも少なくないため、医師や薬剤師に相談して適切な服用方法を確認しましょう。
Q4. 食後には必ずお茶を飲むからそれでどうしても飲みたいんだけど?しょうか?
A4. できれば水道水や白湯で飲むのが一番です。ただし、お茶はそこまで影響がないため、お茶でなら毎日しっかり飲める、または外出時お茶だけは持ち歩くというならば、それでも良いでしょう。ただし、あまり濃いお茶は「タンニン」「カフェイン」という成分が薬に影響を及ぼすことがあるため、注意が必要です。
Q5. 漢方薬は出すところによって飲み方が違うんだけど、どれが正しいの?
A5. 漢方薬は添付文書上では食前または食間となっており、多くの医療機関ではこのように処方されます。ただし、一部の病院では食後に出されることもあります。漢方薬を空腹時に飲む方が良い理由は、食べ物の影響を受けない方が安定して小腸から吸収されやすいからです。ただし、そこまで大きな差はないので指示通りの服用で良いと思われます。
また、生薬によっては、胃の中のpHが低い(酸性度が高い)と、吸収が大きくなりすぎて副作用が出やすい理由もあります。麻黄や附子が入っている漢方薬はできる限り空腹時の方が良いと思われます。
Q6. 1日2回や3回飲む薬だと、どうしても忘れてしまうけどどうしたら良いですか?
A6. 1日2回の薬は6時間以上、3回の薬は4時間以上間隔をあけるのが目安となります。ただし、中には異なるものもあるため、自分が飲む薬については確認をとっておくことが重要です。また、最近は同じ成分でも、効果が長く1日1回で済む薬も出ているため、医師や薬剤師と相談して変えてもらっても良いでしょう。
6.薬の正しい服用法のまとめ
- 薬を正しく服用することは、効果を適正化し、副作用を出来る限り抑え、かつ治療を効率化するためにとても重要なことである。
- 薬の服用時間は、起床時なら起床したすぐ後、食前なら食事の約30分前、食後なら食事の30分以内、食間なら食事と食事の間で約2時間前後あけて、食直前および食直後は各々食事のおおよそ5分前および5分後、を意味している。
- 薬は食後服用を指示されることがほとんどであるが、効果や副作用などの問題でなく、飲み忘れを防ぐためで忘れたら気付いた時に飲んでも良い薬は意外と多い。
- 薬をコップ一杯の水で飲むことにはしっかりとした意義があり、しっかり溶かし速やかに吸収させたり、途中で引っ掛かるのを防ぐためである。
- 飲む飲料水は理想は水道水や白湯であり、お茶でも可能である。ただし、アルコール類、グレープフルーツジュース、牛乳、濃いお茶やコーヒーは影響を受けやすいので避けることが推奨される。
- 飲みにくい剤型の飲み方として、カプセル剤は口を少し湿らせてから飲むときはあごを少し引いて飲むこと。粉薬は口に少し水を溜め、その上に薬を入れてからしっかり水で流し込むこと。また、オブラートや服用補助ゼリーも有効。オブラートは包んだ後、一瞬水につけて体と飲みやすくなる。
- 特殊剤型の薬もいくつかあり、舌下錠は舌の下で溶かし切り、飲み込まないこと。徐放錠は、効果の持続と副作用軽減させるため、噛んだり砕いて飲まないこと。チュアブル錠は錠剤が飲み込めない小児や高齢者に適しており、しっかり噛み砕いてから飲み込むこと。口腔内崩壊錠は、口の中で溶かし水なしでも飲むことができるが、水なしの場合は寝て服用はしないこと。

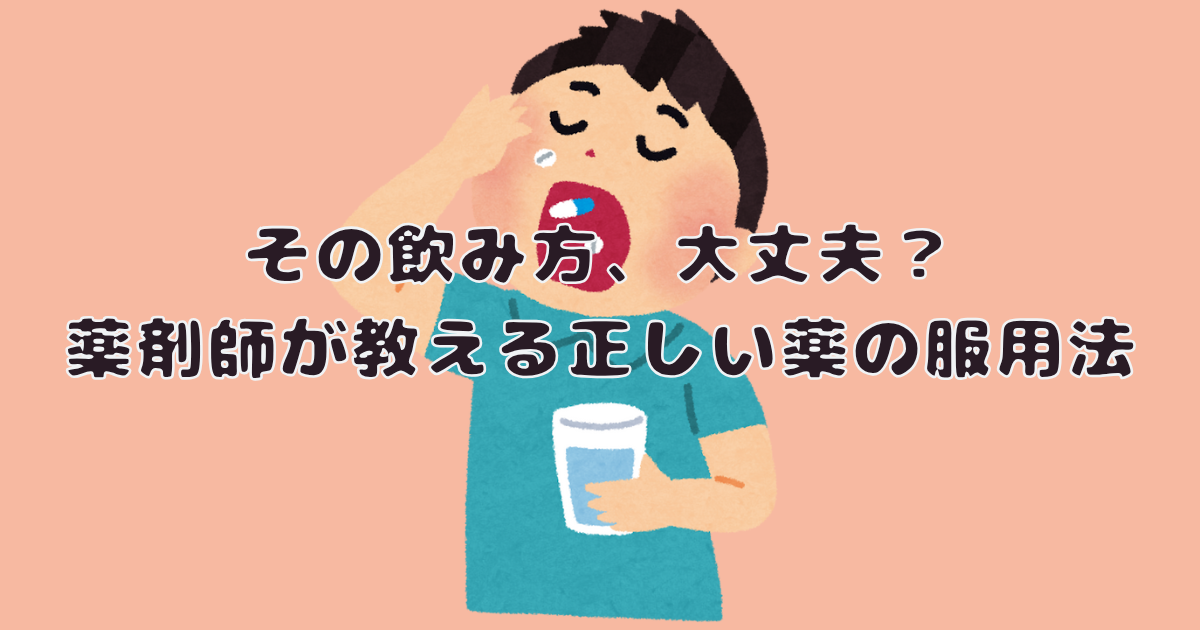
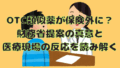
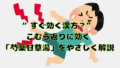
コメント