※本記事にはアフィリエイト広告を利用しています。商品リンクを経由して購入された場合、当サイトに収益が発生することがあります。
1. はじめに ― マグミット錠に新しい仲間「100mg」
便秘の治療に長く使われてきた薬のひとつに「マグミット錠」があります。
“酸化マグネシウム”という成分でできており、医療現場でも古くから親しまれている下剤です。
そんなマグミットに、2025年に新たな100mg錠が加わりました。マグミットには最大量500mgをはじめとして多くの規格があり、これまでの製剤では最も少ない規格が200mgでしたが、より小さな単位が追加されたことで、細やかな用量調整がしやすくなりました。
この記事では、この新しいマグミット錠100mgの登場をきっかけに、従来製剤との違いや便秘治療における役割、そして小児から高齢者までの使い方のポイントについて、わかりやすく解説していきます。
2. マグミットとは? ― 身近な「酸化マグネシウム」の正体
薬局でも病院でも、昔から変わらず目にする「マグミット錠」。 日常的に使われているにもかかわらず、その中身について改めて考える機会は意外と少ないかもしれません。
実は、“酸化マグネシウム”という成分ほど、長い歴史を持ちながら今も現役で活躍している薬はそう多くありません。 その理由は、単に古くからあるというだけではなく、「体への負担が少なく、長く安心して使える」――また、医療用としても市販薬としても広く使われており、年齢や体質に合わせて調整しやすいのも特徴です。
この章では、そんなマグミットの「身近だけど意外と知らない」一面に注目しながら、どんな薬なのかをやさしくひも解いていきます。
2-1. 成分と分類 ― “塩類下剤”という、自然派のアプローチ
マグミットの有効成分は「酸化マグネシウム」。 分類上は「塩類下剤(えんるいげざい)」と呼ばれるタイプの便秘薬にあたります。
下剤と聞くと、「お腹が痛くなる」「クセになりそう」といった不安を感じる方もいるかもしれません。 しかし塩類下剤は、そうした刺激性のタイプとは異なり、腸を直接刺激せず、腸内の水分を引き寄せることで穏やかに作用するのが特徴です。
さらに、酸化マグネシウムは便秘だけでなく、胃酸過多や胃もたれなどの治療にも使われる成分です。 “緩下”と“制酸”の両方に関わる薬として、長年にわたり医療現場で重宝されてきました。
2-2. 市販薬と医療用の違い ―“使い方の幅”の相違
酸化マグネシウムは、市販薬でも医療用でも成分そのものは同じです。 どちらも腸内で水分を保持し、便をやわらかくして排出を促すという基本的な仕組みに違いはありません。つまり、作用や効き方に大きな差はないといえます。
では何が違うのかというと、それは「規格と剤形の選択肢の多さ」です。
市販薬では、ほとんどの製品が1錠あたり約330mgに統一されており、錠剤タイプのみが一般的です。 一方、医療用のマグミットには、新たに登場した100mg錠をはじめ、200mg、330mg、500mg他といった複数の規格がそろっており、さらに細粒(粉末)も用意されています。
このように、医療用では年齢・体格・腎機能などに応じて、より細やかな量の調整が可能です。 特に小児や高齢者、腎機能に配慮が必要な方にとっては、こうした選択肢の広さが大きなメリットとなります。
2-3. 長く使われ続ける理由 ― “古くて新しい”下剤
近年、便秘治療の分野では「上皮機能変容薬(ルビプロストンなど)」や「胆汁酸トランスポーター阻害薬(エロビキシバット)」など、新しいタイプの下剤が次々に登場しています。それでもなお、酸化マグネシウムは長年にわたって第一選択薬としての地位を保っています。
その理由のひとつが、信頼性の高さです。長年使用されて安全性も担保されており、刺激性下剤のように腸を直接動かすのではなく、水分のバランスを整えるという自然な作用機序により、年齢や体質を問わず幅広く使用できます。
さらに、急な腹痛や依存のリスクが少ないため、長期的な使用にも適しているとされています。
もう一つの大きな理由は、経済的な側面です。医療用の酸化マグネシウム製剤は薬価が非常に安く、慢性便秘症の長期治療でも医療費負担を抑えられるという利点があります。そのコストパフォーマンスの高さも、現場で支持され続ける要因のひとつです。
加えて、酸化マグネシウムは便秘以外にも制酸薬としての用途を持ち、新薬の登場が続く中でも、「マグミット」はいまだに
“シンプルで確かな効果を持つ、安心感のある下剤”として多くの人に選ばれています。
3. 作用機序をわかりやすく ― 腸にやさしく“水を引き寄せる”薬
マグミット(酸化マグネシウム)の特徴は、腸を刺激せずに自然な排便を促すことにあります。ここでは、その“やさしい働き”をもう少し詳しく見ていきましょう
3-1. 腸管内での浸透圧作用 ― “水分を保ってやわらかくする”
酸化マグネシウムは、腸内においては炭酸マグネシウムや重炭酸マグネシウムといった形に変化します。 これらは体に吸収されにくく、腸の中にとどまり続けるという性質を持っています。
この“とどまる力”が、実は便秘改善のカギ。 腸内にとどまったマグネシウム塩は、腸内外の濃度差により浸透圧の力で腸の中に水分を引き寄せ、 便に水分を含ませてやわらかく、スムーズに排出しやすい状態に整えてくれます。
イメージとしては、料理で野菜に塩をふる場面を思い浮かべてみてください。 塩をかけると、野菜の中の水分がじわじわと外ににじみ出て、しんなりしてきますよね。 これは、塩の濃度差によって水分が移動する「浸透圧」の働きによるものです。 しかも、しんなりはしても、野菜自体傷つけられているわけではありません。
マグミットの働きも、これとよく似ています。ただし、この場合は水の動く方向は内→外ではなく、外→内と逆になります。腸内でマグミットがマグネシウム塩に変化すると、 それが“塩”のような役割を果たし、腸の外(体内)から水分を腸の中へ引き寄せます。 こうして腸内に水分が集まり、便がほどよく潤ってやわらかくなり、スムーズに排出されやすくなるのです。
そのため、腹痛や下痢といった副作用が比較的少なく、 高齢者や小児を含む幅広い患者層に使いやすいというメリットがあります。
3-2. 腹痛を起こしにくい理由
マグミットは、腹痛を起こしにくく使いやすい下剤として知られています。それはなぜでしょうか。
その理由は、マグミットが腸や神経を直接刺激しないタイプの薬だからです。腸管内の水分を保持することで便をやわらかくし、自然な排便を促す——いわゆる浸透圧性の緩下剤に分類されます。このため、腸の動きを無理に活発化させることがなく、腹痛やけいれんが起こりにくいのです。
一方で、刺激性下剤(センノシドやピコスルファートなど)は大腸の神経や粘膜を刺激してぜん動運動を強め、
短時間で排便を促すタイプの薬です。一時的な便秘には有効ですが、長期連用により腸の反応性が低下し、いわゆる「薬を飲まないと出ない」状態(弛緩性便秘)を招くおそれもあります。
また、新しい作用機序をもつ下剤であるルビプロストン(アミティーザ)やエロビキシバット(グーフィス)なども、腸内に水分を引き寄せて便をやわらかくするタイプの薬です。ただし、その作用は非常に強力で、短時間で腸内の水分量が急激に増やし、腸管が過度に反応して腹部の違和感や痛みを生じることがあります。
このように、マグミットは腸を“動かす”のではなく、腸に“負担をかけにくい”アプローチの薬。その穏やかな作用機序により、腹痛を起こしにくく、長期的にも使いやすい緩下剤とされています。
4. マグミットの新しい選択肢
2025年に新たに承認されたマグミット錠100mgは、これまでの200mg以上の規格にはなかった“小児にやさしい設計”が最大の特徴です。とくに、1歳以上の小児への投与が明確に位置づけられた点は大きな進歩といえます。
なお、今回の改訂では100mg錠だけでなく、既存の200mg、250mgなどの錠剤や83.3%細粒にも小児適応が追加されています。これにより、さらに幅広い年齢層に対応できるようになり、治療の柔軟性が高まりました。
4-1. 小児に適した用量調整がしやすい
従来もマグミット(酸化マグネシウム)は小児に使用されることがありましたが、明確な基準や年齢別の用量設定は設けられていませんでした。
しかし今回、100mg規格の発売を機に、正式に1歳以上の小児に対する用法・用量が添付文書上に明記されました。
通常、1歳以上の小児には酸化マグネシウムとして1日20〜80mg/kgを、食後2回に分けて経口投与する。
と記載されています。この投与量を実際に計算すると、体重10kgの小児なら1日あたり200〜800mg程度となり、これを2回に分けると1回100〜400mgが目安となります。
従来の最小規格は200mg錠であったため、例えば「1回100mgだけ使いたい」「少し減量したい」といった場面では、錠剤を割る、粉砕する、といった処理が必要でした。
新たに登場した100mg錠は、そのような操作を行わなくても、年齢や体重に応じた細やかな投与量の調整が容易になります。また、錠剤が小さい分、嚥下が難しい小児でも飲みやすいという利点もあります。
5. 小児の便秘治療 ― まずは生活習慣と食事から
子どもの便秘は、排便の我慢や水分・食物繊維の不足、生活リズムの乱れなど、日常の小さな習慣から起こることが多いものです。治療の基本は、まず生活習慣と食事の見直し。
薬による治療は、それでも改善しない場合に検討されます。
5-1. 小児便秘のよくある原因
子どもの便秘は、体質というよりも生活習慣や排便リズムの乱れによって起こることが多いです。ここでは、代表的な原因を2つの観点から整理してみましょう。
5-1-1. 排便の“がまん”が悪循環をつくる
小さな子どもでは、「遊びたい」「トイレに行くのが恥ずかしい」などの理由で、排便を我慢してしまうことがよくあります。この“がまん”が続くと、腸の中に便がたまり、直腸が少しずつ膨らんでいきます。
- 直腸が伸びると、脳が便意を感じ取りにくくなる
- 便意が鈍くなると、さらに便がたまる
- 直腸がますます広がり、排便感覚がなくなる
──このような悪循環が、便秘を慢性化させる要因になります。
5-1-2. 排便は“脳と腸のチームプレー”
排便は、単に腸が動くだけの反射ではありません。腸にたまった便の刺激が神経を介して脳へ伝わり、
脳が「今なら出していい」と判断すると、筋肉をゆるめて排便が起こります。この脳と腸の連携がうまく働くことで、スムーズな排便が実現します。
ところが、乳児や幼児ではこの協調がまだ未熟です。排便のタイミングをうまくつかめず、結果として排便困難や便秘を繰り返しやすいのです。
このように、小児の便秘は「腸の動きが弱い」だけでなく、排便の我慢の習慣化や脳と腸の連携の未熟さといった要素が複雑に絡み合っています。まずはこの仕組みを理解し、生活リズムや排便環境を整えることが、治療の第一歩となります。
5-2. 食事と水分のバランス
便秘の改善には、薬とあわせて毎日の食事内容が大切です。まずは、薬を服用する前に、日頃の食生活絡み直すことが大切になります。
- 水分摂取は重要だが万能ではない
水を単に多く飲めば便秘が治るわけではなく、脱水がなければ水分だけで改善するとは限りません。ただし、腸の働きを保つために体を潤すことは基本です。 - 食物繊維の役割
野菜・果物・豆類・海藻などに多く含まれ、水に溶けやすいかどうかで2つのタイプに分かれます。- 不溶性食物繊維:便のかさを増やして排出を促します。
- 水溶性食物繊維:腸内で発酵し、善玉菌(ビフィズス菌など)を育てます。
- 水分と食物繊維はセット
食物繊維を摂るときは、それに見合った水分補給が不可欠。水分が足りないと繊維が膨らまず、逆に便が硬くなることもあり、それが弊害になる恐れもあります。 - 乳酸菌・ビフィズス菌の効果は個人差
ヨーグルトなどに含まれる善玉菌は、必ずしも全員に効果があるわけではありません。一部の子どもに効果があるため、体に合うようであれば積極的に摂って良いでしょう。
このように食事と水分のバランスが整ってこそ、マグミットなどの便秘薬が本来の力を発揮しやすくなるのです。
6. 小児に使われる便秘薬の種類と使い分け
小児の便秘治療では、まず生活習慣の改善が基本ですが、それでも改善しない場合には、薬によるサポートが必要になることがあります。とはいえ、子どもの体は大人よりも繊細で、薬の選び方にも注意が必要です。
便秘薬といっても、実はその働き方や効果には種類があります。ここでは、小児でもよく使われる代表的な薬を紹介し、それぞれの特徴と使い分けを見ていきましょう。
6-1. 酸化マグネシウム(マグミット®︎)
すでに述べたように、マグミットは浸透圧の力で腸内に水分を保ち、便をやわらかくするタイプの便秘薬です。
刺激性が少なく、腹痛を起こしにくいのが最大の特徴。長期的にも使いやすく、まず最初に選ばれる薬として位置づけられています。
医療用では、マグミット錠100mgの登場により小児でも細かな用量調整が可能になりました。一方で、市販薬では1錠あたり333mgの規格が一般的です。
【市販で入手可能な製品はこちら】
酸化マグネシウムを成分とする市販製品は、5歳以上から服用可能とされています。用量に関しては、薬剤師に相談してからの服用にしましょう。
- 酸化マグネシウムE便秘薬 360錠
6-2. ラクツロース(モニラック®)
ラクツロース(モニラック®など)は、乳糖から作られた“体に吸収されにくい糖”です。小腸では吸収されず、そのまま大腸まで届いて、腸内細菌によって分解されます。すると、乳酸や酢酸などの有機酸が生まれ、腸にやさしく働きかけてくれるのです。
ラクツロースは刺激が少なく、赤ちゃんや小さなお子様にも使いやすい穏やかな下剤です。医療現場では、小児の便秘治療に広く使われており、特にシロップタイプのモニラック®は飲みやすさでも定評があります。ただし、ラクツロースは医療用のみの薬で、市販では販売されていません。
🛒 市販で手に入る“やさしい代替品”―マルツエキス
市販で購入できるおすすめは、マルツエキス。こちらはラクツロースと似たしくみで、麦芽糖エキスを主成分とした製品です。麦芽糖が腸内でゆっくり発酵し、腸内環境を整えながら便をやわらかくしてくれます。
6-3. マグロコール(モビコール®)
マグロコールは、水に溶けやすい高分子化合物で、腸の中に水分を引き寄せて便をやわらかくする“浸透圧性下剤”です。体にはほとんど吸収されず、腸内にとどまって水分を保つことで、便のかさが増し、自然と腸の動き(蠕動運動)を促します。
2018年に承認され、2歳以上の小児にも使えるようになったことで、モニラック®︎と並ぶ代表的な「やさしいタイプの便秘薬」として注目されています。電解質も含まれており、腸内のバランスを保ちながら作用するため、腹痛や刺激が少ないのも特徴です。
モビコールも医療用のみで、市販薬としては販売されていません。効果と安全性の両面から評価が高いとされています。最新の診療ガイドライでも、モビコールは第一選択薬として位置づけられています[脚注1]。
6-4. ピコスルファートNa(ラキソベロン®)
ピコスルファートNaは、腸を“直接刺激して動かす”タイプの下剤です。飲んだ直後はまだ“準備中”で、腸内の細菌によって変化してから効き始め、大腸の粘膜を刺激することで蠕動運動を高め、便を送り出しやすくします。
そのため効果がしっかり出やすい一方で、刺激がやや強く、使い方によっては腹痛や下痢を起こすこともあります。反面、刺激が強すぎると腹痛や下痢を起こすこともあるため、使い方には注意が必要です。他の薬でうまくいかないときの“最後のひと押し”として使われることが多いです。
液剤タイプで量の調整がしやすく、小児でも使いやすい反面、“困ったときの助っ人”として使う薬です。
6-4. 漢方系
刺激性下剤による便意低下を避けたい場合や、より体に穏やかな治療を希望する際には、漢方製剤を併用することがあります。
- 弛緩性タイプ
便が出そうでも腸の押し出す力が弱いタイプには、大黄を少量だけ含む処方を検討します。例えば、大黄甘草湯、潤腸湯などです。大黄は結腸運動を高めますが、甘草が大黄の過度な収縮を和らげ腹痛を軽減するため、“少量・最小限”で使うのが基本です - 痙攣性タイプ
差し込むような腹痛やガスが目立つタイプには、腸の緊張をゆるめる芍薬を含む処方が向きます。桂枝加芍薬湯、小建中湯などです。芍薬+甘草は痙攣性疼痛を緩和し、腹痛・膨満の改善が期待できます。 - 小児でよく使われる処方
大建中湯や大黄甘草湯の使用例が多く、大建中湯は直腸知覚の改善が報告されており、便意低下児にも適するケースがあります。大建中湯のみで腹痛が出る場合は小建中湯を併用するという実臨床の工夫も示されています。
【市販の漢方薬の購入はこちら】
- 小建中湯エキス顆粒
- 大建中湯エキス顆粒
7. マグミットの使用上注意点
マグミット(酸化マグネシウム)は、日本では古くから使用されており、効果の面や安全面に関しても安心して使用できる小児に対しても製剤が、いくつか注意を払わなくてはいけない事象があります。
7-1. 高マグネシウム血症
マグミット(酸化マグネシウム)はマグネシウム製剤であるため、長期にわたって使用している場合には高マグネシウム血症のリスクが考えられます。軽度では吐き気や眠気などが見られ、重症化すると脈の乱れや意識障害に至ることもあります。ただし、腎機能に問題のない健康な小児においては報告が非常に限られており[脚注2]、現状では“念のため知っておくべき注意点”ととらえるのが現実的です。
7-2. 注意すべき併用薬
本剤は制酸作用をもち、さらにマグネシウムという金属イオンを含むため、ほかの薬の吸収に影響を与えることがあります。
特に注意したいのは一部の抗菌薬との併用で、とくに小児にも使われやすいセフェム系抗菌薬(例:セフジニルなど)や鉄剤などでは、吸収が低下する可能性があるため、こうした薬を一緒に服用する場合は、少なくとも2〜3時間ほど服用時間をずらすことが推奨されています。
8. まとめ
マグミット(酸化マグネシウム)は、長い歴史の中で多くの患者さんに使われてきた、信頼性の高い下剤です。
今回の改訂では、新たに100mg錠が追加されただけでなく、既存の錠剤や細粒(83%)にも1歳以上の小児適応が拡大され、年齢や体重に応じたより細やかな用量調整が可能になりました。
これにより、医療現場での使い勝手が向上し、PEG製剤(モビコール®など)が第一選択とされる中でも、日常診療での選択肢が確実に広がったといえます。
マグミットは腸に水分を引き込み、便をやわらかくして自然な排便を促す薬です。刺激が少なく、小児でも安心して使える点が大きな魅力ですが、一方で薬の飲み合わせなど、注意すべき点もあります。
便秘治療の基本は、薬だけでなく「生活習慣」「食事」「排便リズム」を整えること。
マグミットはそのサポート役として、安全に・長く付き合える“やさしい便秘薬”としてこれからも活躍していくでしょう。
【参考資料・文献】

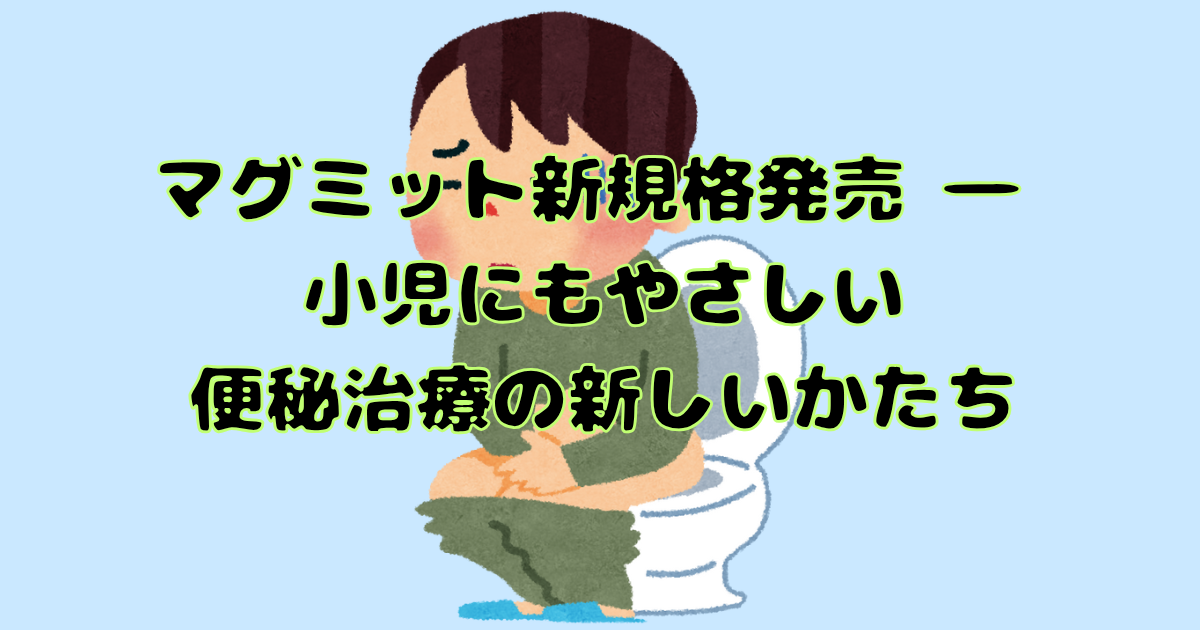
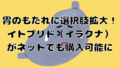

コメント