※本記事にはアフィリエイト広告を利用しています。商品リンクを経由して購入された場合、当サイトに収益が発生することがあります。
1. はじめに
近年、テレビや新聞、医療機関などで「耐性菌」という言葉を耳にする機会が増えてきました。なんとなく「薬が効きにくい菌なのかな?」とイメージする方も多いかもしれませんが、実際にそれがどのようなもので、なぜ生まれ、私たちの健康にどんな影響を及ぼすのかまで理解している人は、まだ少ないのではないでしょうか。
また、「風邪には抗生物質は使わない方がいい」「抗生物質が保険の対象から外れるかもしれない」といったニュースを見聞きして、「薬が減るなんて不安」「本当にそれで大丈夫なの?」と感じた方もいるかもしれません。
こうした動きの背景には、世界的に深刻化している「耐性菌」の問題があります。耐性菌とは、抗生物質が効かなくなってしまった細菌のことで、かつては簡単に治せた感染症でも、治療が難しくなるケースが増えているのです。
WHO(世界保健機関)はこの問題を「静かなるパンデミック」と呼び、私たちの生活や未来の医療に大きな影響を与える課題として警鐘を鳴らしています。
本記事では、「耐性菌とは何か」「なぜ問題なのか」といった基本的な知識から、「抗菌薬の正しい使い方」までをわかりやすく解説します。最後には「私たちが日常生活でできること」についてもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
2. 耐性菌の概念
2-1. 耐性菌とは?
人類は古くから、細菌やウイルスによる感染症によって多くの命を失ってきました。しかし、長年の研究の成果として、抗菌薬(抗生物質)や抗ウイルス薬といった「特効薬」が開発され、これまで命を脅かしていた感染症も治療できるようになりました。
ところが、これらの薬を長期間かつ広範囲に使用することで、細菌やウイルスも生き残るために進化し、薬に対して抵抗力を持つようになります。つまり、薬が効きにくくなったり、まったく効かなくなったりする現象が起きてしまうのです。
このような現象を「薬剤耐性(Antimicrobial Resistance:AMR)」と呼びます。そして、薬剤耐性を獲得した細菌のことを 「(薬剤)耐性菌」 と言います。
2-2. 普通の細菌と何が違うのか?
通常の細菌による感染症であれば、適切な抗菌薬(抗生物質)を投与することで、細菌の増殖が抑えられ、やがて死滅していきます。つまり、「抗菌薬を使えば治る」のが一般的な細菌感染です。
ところが、耐性菌の場合は同じ抗菌薬を使っても効果が得られにくく、場合によってはまったく効かないこともあります。見た目は普通の細菌と変わらなくても、「抗菌薬に対して抵抗力を持っている」という点が最大の違いです。
この抵抗力によって、治療が長引いたり、重症化したりするリスクが高まります。特に、免疫力が低下している高齢者や入院患者にとっては、命に関わる深刻な問題となることもあります。
では、なぜ細菌がこのような抵抗力を持つようになるのでしょうか。その具体的な仕組みについては、後の章「4. なぜ耐性菌が生まれるのか」で詳しく解説していきます。
2-3. 耐性菌が我々に与える影響
耐性菌が社会に広がると、私たちの健康や医療体制に深刻な影響を及ぼします。具体的には、以下のような問題が懸念されています。
- 治療の困難化
従来であれば抗菌薬で簡単に治療できた感染症でも、薬が効かなくなることで治療が長引いたり、重症化するケースが増えます。 - 死亡リスクの増加
特に高齢者や免疫力が低下している人にとっては、耐性菌感染が命に関わる深刻な事態を引き起こす可能性があります。 - 医療費・社会的コストの増加
治療期間が延びることで入院日数が増え、より強力で高価な薬剤の使用が必要になるため、医療費や社会的負担が大きくなります。 - 感染の拡大
耐性菌は人から人へ、または環境を介して広がることがあり、病院内や地域社会で集団感染を引き起こすリスクがあります。
こうした事態を受けて、世界保健機関(WHO)は「薬剤耐性菌は静かなるパンデミックであり、対策を講じなければ2050年までに年間最大1,000万人が死亡する可能性がある」と警告しています。これは、がんを上回る死因になるとも予測されており、国際的に取り組むべき最重要課題と位置づけられています。
3. 抗菌薬の基礎知識
3-1. 抗菌薬とは?
抗菌薬は、細菌などの微生物の増殖を抑えたり、殺菌したりする薬です。肺炎などの感染症の治療に使われることが多く、現代医療に欠かせない存在です。しかし、使い方を誤ると「耐性菌」と呼ばれる薬が効かない菌が生まれる原因にもなります。まずは、抗菌薬の基本を知っておきましょう。
3-2. 抗菌薬と抗生物質の違い
「抗菌薬」と「抗生物質」という言葉は、日常的に混同されがちですが、実は次のような違いがあります。
- 抗生物質:カビや放線菌などの微生物がつくる天然由来の物質から発見された薬です。世界初の抗生物質として有名なペニシリンは、アオカビから偶然発見されたことで知られています。
- 抗菌薬:抗生物質に加え、人工的に合成された細菌に効く薬も含めた、より広い概念です。
👉 つまり、抗生物質は「自然由来」、抗菌薬は「それも含めた総称」と理解すると、違いがはっきりします。
3-3. 抗菌薬の主な種類と特徴
抗菌薬にはさまざまな種類があり、それぞれ作用する仕組みや得意とする細菌のタイプが異なります。ここでは、代表的な抗菌薬のグループとその特徴を簡単に紹介します。
- β-ラクタム系(ペニシリン系・セフェム系・カルバペネム系など)
細菌の細胞壁の合成を阻害し、構造を破壊することで死滅させます。最も使用頻度が高く、安全性も比較的高いグループです。アモキシシリン(ペニシリン系)、セフトリアキソン(セフェム系)、テビペネムピボキシル(カルバペネム系)などが一例であります。 - マクロライド系
細菌のタンパク質合成を阻害します。呼吸器感染症や小児への処方でよく使われ、副作用が少ないのが特徴です。クラリスロマイシン、アジスロマイシンなどがよく使用されます。 - フルオロキノロン系
細菌のDNA複製を妨げることで増殖を抑えます。幅広い菌に効果がありますが、耐性化しやすく、副作用もあるため慎重な使用が求められます。例としてはレボフロキサシンなどがあります。 - アミノグリコシド系 タンパク質合成を阻害します。主に点滴で使用され、重症感染症や院内感染に対して使われます。腎毒性や聴覚障害などの副作用に注意が必要です。アミカシン、ゲンタマイシンなどがあります。
- テトラサイクリン系
タンパク質合成を阻害します。にきびやクラミジア感染症など幅広い用途があり、経口薬としても使われます。ミノサイクリン、ドキシサイクリンなどがあります。 - グリコペプチド系
細胞壁の合成を強力に阻害します。特にMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)などの耐性菌に対して使用される重要な薬剤です。バンコマイシンが有名です。
4. 耐性菌はなぜ生まれるのか?
4-1. 抗菌薬の無駄な使用
風邪やインフルエンザの多くはウイルスが原因であり、抗菌薬(抗生物質)はウイルスには効果がありません。それにもかかわらず、「念のため」と処方されたり、患者の希望によって投与されるケースが長年続いてきました。
こうした不適切な使用は、薬に強い性質を持つ細菌を選び出すことになり、耐性菌の発生と拡散を後押しする大きな要因となってきました。
この問題に対し、近年では国の政策としても対策が強化されています。2025年9月には、風邪や小児インフルエンザに対して抗菌薬を処方しても、原則として保険適用外とする方針が報じられました。これは「不要な抗菌薬の処方を減らす」ことを目的とした重要な一歩であり、医療現場の意識改革にもつながると期待されています。
4-2. 薬の自己判断での中止
抗菌薬を服用していると、「症状がよくなったから、もう飲まなくてもいいだろう」と自己判断で服用を中止してしまう人が少なくありません。しかし、これは耐性菌を生み出す大きな原因のひとつです。
抗菌薬を飲み始めた初期段階では、多くの細菌が減少しますが、体内にはまだ生き残っている菌が存在しています。この時点で服用をやめてしまうと、薬にある程度耐性を持った菌だけが残り、再び増殖することで「耐性菌」が育ってしまうのです。
4-3. 農業や畜産での使用
抗菌薬は人の医療だけでなく、家畜の感染予防や成長促進の目的でも世界中で広く使用されてきました。その結果、動物の腸内や周囲の環境に耐性菌が生まれ、それが食品や水を介して人間社会に広がる可能性があります。
このような背景から、WHO(世界保健機関)は「ヒト・動物・環境を一体として考える『One Health』の視点」で、包括的な対策を進める必要があると提言しています。
5. 耐性のメカニズム
細菌は非常に小さな存在ですが、生き延びるための驚くべき適応力を備えています。抗菌薬によって攻撃されても、それを回避したり、無効化したり、逆に利用したりするさまざまな仕組みを獲得することで、薬に強い「耐性菌」が生まれてくるのです。
ここでは、耐性菌が抗菌薬に対してどのように抵抗するのか、代表的なメカニズムをいくつか紹介します。
5-1. 標的を変えてしまう
抗菌薬は、細菌の生命活動にとって重要な部分、いわば「急所」を狙って作用します。たとえば、ペニシリンは細菌の細胞壁を構成する酵素に結合し、その壁を壊すことで細菌を死滅させます。
しかし、耐性菌はこの「急所」の構造を少し変えてしまうことで、抗菌薬がうまく結合できないようにします。薬が標的を認識できなくなるため、効果が発揮されなくなるのです。
👉 これは、まるで「鍵穴の形を変えて、鍵(抗菌薬)が入らないようにする」ような仕組みです。薬は存在していても、鍵が合わなければ扉(細菌)を開けることができません。
5-2. 薬を壊す酵素をつくる
一部の細菌は、抗菌薬そのものを分解・無効化する酵素を作り出す能力を持っています。これにより、薬が細菌に到達する前に破壊されてしまい、効果が発揮されなくなります。
代表的な例として知られているのが、「β(ベータ)ラクタマーゼ」という酵素です。この酵素は、ペニシリン系抗菌薬の構造を分解し、薬の作用を失わせてしまいます。そのため、βラクタマーゼを持つ細菌には、ペニシリン系の薬が効きにくくなります。
👉 例えるなら、「敵の武器をバラバラに分解してしまう」ようなイメージです。攻撃される前に武器を壊してしまえば、戦いにならないというわけです。
5-3. 薬を外に排出する
細菌の表面には「排出ポンプ(エフラックスポンプ)」と呼ばれる仕組みがあり、細胞内に侵入した抗菌薬を外に押し出すことができます。このポンプ機能が強化されると、薬が細胞内に届いてもすぐに排出されてしまい、十分な効果を発揮できなくなります。
👉 例えるなら、「体内に毒が入ってもすぐに吐き出してしまう」ような防御方法です。薬が届いても、細菌が素早く外に追い出してしまうため、治療が難しくなります。
5-4. 薬の侵入を防ぐ
抗菌薬は、細菌の外膜(細胞膜や細胞壁)を通って内部に入り、標的となる構造や酵素に作用することで細菌を死滅させます。しかし、耐性菌はこの「通り道」を狭めたり、塞いだりすることで、薬の侵入を妨げる仕組みを持っています。このような防御機構によって、抗菌薬が細菌の内部に十分に届かず、効果を発揮できなくなってしまうのです。
👉 例えるなら、「城の門を強化して敵を中に入れない」ようなイメージです。薬という“攻撃者”がいても、門が堅牢であれば侵入できず、細菌は守られたままになります。
6. 抗菌薬が効く仕組みを理解する〜PK/PD理論
抗菌薬の効き方を理解するうえで欠かせないのが「PK/PD理論(薬物動態・薬力学)」です。
ちょっと難しそうに聞こえるかもしれませんが、実は「薬が体の中でどう動くか」「細菌にどう効くか」を整理しただけの、シンプルな考え方です。
6-1. PK(Pharmacokinetics:薬物動態)とは?
PKは、薬が体の中を旅する様子を表しています。
飲んだ薬が体に吸収され → 血液に乗って全身を巡り → 目的の場所に届き → 最後は体の外に排泄される。
この一連の流れをまとめたものがPKです。
PKでは、以下の4つの過程が重要な要素となります:
- 吸収(Absorption):薬が体内に取り込まれる速さと量
- 分布(Distribution):薬が体内のどこに、どれだけ届くか
- 代謝(Metabolism):薬が体内でどのように分解されるか
- 排泄(Excretion):薬がどのように体外へ出ていくか
これらの情報は、薬の投与量や投与間隔を決めるための基礎となります。また、PD(薬力学)と組み合わせることで、「どのくらいの濃度で、どのくらいの時間薬が効くか」を予測することができます。
👉 つまり、PKは「薬が体の中でどれくらいの量で、どれくらいの時間存在するか」を考える理論です
6-2. PD(Pharmacodynamics:薬力学)とは?
PD(薬力学)とは、「薬が体内でどのように作用し、標的となる細菌や細胞にどのような影響を与えるか」を示す概念です。 つまり、薬と細菌が出会ったときに何が起こるかを科学的に捉えるものです。
- 薬の濃度が十分に高ければ、細菌は速やかに死滅する
- 一方で、濃度が不十分だと、細菌は生き残り、治療効果が得られない
PDでは、「薬がどの濃度で効果を発揮し、どの濃度で副作用が現れるか」といった安全性の側面も重要な要素です。 薬の作用が強すぎれば腎臓や肝臓などへの負担が大きくなり、逆に弱すぎれば細菌が生き残ってしまう可能性があります。
このように、「効果」と「安全性」のバランスを見極めることがPDの中心的な考え方です。
👉 つまりPDは、「薬の濃度とその効き方の関係性」を明らかにするものです。
6-3. PKとPDを合わせて考える意味
抗菌薬は「ただ飲めば効く」という単純なものではありません。
体の中で どのくらい薬が存在するか(PK) と、 どのくらいの濃さで細菌に効くか(PD) ― この両方をバランスよく考える必要があります。これが PK/PD理論です。
医師はこの理論をもとに「最適な投与量・投与間隔」を決めています。
- 薬が効きすぎると腎臓や肝臓に負担がかかり、副作用が強く出やすくなる。
- 濃度が低すぎると → 細菌が生き残り、薬に強い「耐性菌」が生まれる可能性がある。
- 感染部位(肺、尿路、皮膚など)によって薬の届き方が違うため、用量を変える必要がある。
👉 言い換えるなら、PK/PD理論とは 「効き目と安全性のちょうどいいバランスを見つけるための設計図」 なのです。
6-4. 濃度依存型と時間依存型
抗菌薬の効果を最大限に引き出すためには、「PK/PD理論」の理解が欠かせません。その中心となる考え方が「濃度依存型」と「時間依存型」であり、抗菌薬のタイプを大きく2種に分けることができます。
まず前提として、抗菌薬が細菌に効果を発揮するには、ある一定以上の濃度が必要です。この最低限の濃度を MIC(最小発育阻止濃度) と呼びます。MICは、細菌が増えるのを止めるために必要な薬の最低濃度を意味し、このMICが低いほど「少ない量で効く」ということであり、その抗菌薬がより高い効果を発揮できるといえます。
PK/PD理論では、このMICを基準にしながら「薬の血中濃度が時間とともにどう変化するか」を考え、効果的な投与方法を導き出します。
6-4-1. 濃度依存型
このタイプの抗菌薬は、血中濃度が高ければ高いほど、細菌を素早く、強力に殺菌します。
さらに特徴的なのは、薬の濃度がMICより下がった後も一定時間、細菌の増殖を抑える 「抗菌薬後効果(PAE)」 が働くこと。そのため、投与の間隔を少し空けても効果が持続しやすいのです。
- 代表例:アミノグリコシド系、フルオロキノロン系
- 効果の指標:Cmax/MIC(最高血中濃度とMICの比)、AUC/MIC(血中濃度の総量とMICの比)
- イメージ:強烈な一撃を与え、その余韻でも相手を封じ込めるタイプ
👉 つまり、このタイプでは 「一回の投与でしっかり高い濃度を達成すること」 が効果を引き出すカギになります。
6-4-2. 時間依存型
このタイプの抗菌薬は、「一定時間以上、菌を抑える濃度を保つか」 が重要です。基本的には、血中濃度がMICを上回っている時間の長さが効果を決めます。
- 代表例:βラクタム系(ペニシリン、セフェム)、マクロライド系
- 効果の指標:T>MIC(薬の濃度がMICを上回っている時間の割合)
- イメージ:相手をずっと押さえ込み続ける持久戦タイプ
👉 そのため、時間依存型の抗菌薬は「投与間隔を守る」ことがとても大切です。飲み忘れると血中濃度が下がり、菌が再び増えてしまいます。
(補足)
ただし、マクロライド系やテトラサイクリン系など一部の薬は、MICを下回っても抗菌薬後効果(PAE)が働き、効果が持続する場合があります。
7. 耐性菌と戦うための最適使用
耐性菌をこれ以上広げないために、私たちが持つ最大の武器――それは「抗菌薬を正しく使うこと」です。
耐性菌は、長年にわたる人類の「薬の使い方」の積み重ねによって生まれてきました。効かなくなった薬、漫然と続けられた治療、必要以上の投与――そのすべてが、細菌に“進化のチャンス”を与えてきたのです。だからこそ、薬を「必要なときに」「正しく」「最小限で」使うことが、未来の医療を守る第一歩になります。これは個人の意識だけでなく、医療現場全体で取り組むべき課題です。
近年では、「抗菌薬適正使用支援(Antimicrobial Stewardship)」[1]という考え方が世界中で広がっており、WHO(世界保健機関)や厚生労働省も、耐性菌対策の柱として位置づけています。
この章では、抗菌薬を最適に使うための具体的なポイントを、薬剤師の視点からわかりやすく紹介していきます。
7-1. 「使わない勇気」〜風邪に抗菌薬は不要
抗菌薬は、細菌に対しては非常に強力に働きますが、ウイルスには一切効果がありません。風邪やインフルエンザの多くはウイルスが原因であり、これらに抗菌薬を使っても症状の改善は期待できません。
もちろん、すべての風邪に抗菌薬が不要というわけではありません。高齢者の肺炎合併や、免疫が低下している方(がん治療中、糖尿病、免疫抑制薬使用など)では、細菌感染のリスクが高く、感染症が明らかな場合などは抗菌薬が必要になるケースもあります。
それでも、「念のため」「昔からの慣習で」といった理由で抗菌薬が処方されてきた歴史があります。こうした“過剰使用”の積み重ねが、耐性菌の拡大を招いてきたのです。
この状況を変えるため、近年では国の政策としても強いメッセージが打ち出されています。2025年には、風邪や小児のインフルエンザに対する抗菌薬投与は原則保険適用外とする方針が示されました。これは、「抗菌薬は本当に必要なときにだけ使う」という社会全体のルールを明確化したものです。
7-2. 必要なときには正しく使う
抗菌薬は、「必要ないときには使わない」ことがとても大切です。しかしそれと同じくらい、「必要なときには、きちんと正しく使う」 ことも重要です。中途半端な使い方をすると、薬が十分に効かずに細菌が生き残ってしまい、結果として薬が効かない「耐性菌」が生まれる原因になります。
そのため、抗菌薬を使うときは、医師の指示どおりに正しく飲むことがとても大切です。医師は、薬が体の中でどのように動くか(吸収されて、効いて、体から排出されるまで)や、どのくらいの濃さで効果を発揮するかなど、さまざまな情報をもとに、最も効果的で副作用の少ない量と回数 を設計しています。
それにもかかわらず、患者さんが「副作用が怖いから回数を減らそう」「もう治った気がするから途中でやめよう」と自己判断してしまうと、薬の濃度が中途半端な状態になり、耐性菌が生まれやすい環境を自分で作ってしまうことになります。特に、細菌が薬にギリギリ耐えられるほどの濃度(MIC)の状態が続くと、耐性菌が発生しやすいことが知られています[2]。
👉 つまり、「医師の指示どおりにきちんと飲み切る」ことこそが、最も確実な耐性菌対策なのです。
7-3. ガイドラインに基づく“オーダーメイド”の投与設計
抗菌薬の使い方は、医師の経験や勘だけで決めているわけではありません。実際には、国内外の「抗菌薬適正使用支援プログラム」や「抗微生物薬適正使用の手引き」といった専門的なガイドラインに基づいて、科学的な根拠のもとに判断されています。
これらのガイドラインでは、たとえば感染している場所(肺、尿路、皮膚など)や原因となる菌の種類、症状の重さなどに応じて、
- どの薬を使うか
- どれくらいの量を使うか
- どのくらいの間隔で、何日間使うか
といったことが細かく決められています。
ただし、患者さん一人ひとりの体の状態は違います。医師は、
- 他に飲んでいる薬との相性
- 年齢や体重
- 腎臓や肝臓の働き具合
などを考慮しながら、ガイドラインをベースにその人に合った使い方に調整しています。
👉 つまり、抗菌薬の使い方は「どの薬を、どれだけ、どのくらいの期間使うか」を丁寧に見極める、オーダーメイドの設計なのです。
7-4. 抗菌薬の「デ・エスカレーション」戦略
「デ・エスカレーション」とは、最初に広く効く抗菌薬を使い、原因菌が特定された後に、より狭い範囲の抗菌薬へ切り替えるという治療戦略です。日本語では「段階的な抗菌薬の絞り込み」とも言われます。
- なぜ最初に“広く効く薬”を使うのか
重症感染症の初期では、まだどんな細菌が原因かわからないことが多いため、まずは「広い範囲の菌」に効く抗菌薬(広域抗菌薬)を使って命を守ることが最優先です。
この段階では、「もし耐性菌が原因だったら」という最悪の事態を想定して治療が始まります。 - 原因菌がわかったら、必要最小限へ
治療を始めた後、検査(培養や感受性試験)で原因菌が特定されたら、その結果に基づいて「本当にその菌に必要な薬」だけに絞り込みます。以下のようにに、治療効果を保ちながらも、使う薬の範囲と量を減らすのが目的です。- 広域抗菌薬 → 必要な菌だけに効く狭域抗菌薬へ変更
- 点滴 → 状況に応じて内服薬へ切り替え
- 複数の薬を併用 → 単剤療法に移行
- 耐性菌を増やさないために
広域抗菌薬を長く使うと、体内の「本来害のない菌」まで殺してしまい、耐性菌が生まれやすくなります。
デ・エスカレーションは、感染を確実に治しながらも、この“余計なダメージ”を減らすための方法です。
厚生労働省の「AMR対策アクションプラン」や日本感染症学会の「抗菌薬適正使用支援プログラム(ASP)」でも、デ・エスカレーションは抗菌薬管理の基本方針として位置づけられています。 - デ・エスカレーションは「引き算の治療」
これまでの医療では「重ければ強い薬を」と考えられがちでしたが、今は考え方が変わっています。
「できるだけ最小限で治す」=未来に耐性菌を残さないという視点が、医療の新しい常識になりつつあります。
👉 デ・エスカレーションは、“治す力”と“守る力”の両立を目指す、まさに「引き算の医療」なのです。
8. 抗菌薬の歴史そして未来
8-1. 抗菌薬と耐性菌の終わらない攻防の歴史
20世紀初頭、ペニシリンの発見によって人類は感染症に対して大きな武器を手に入れました。肺炎や敗血症など、かつて命を落とす病気を治せるようになり、「魔法の弾丸」と呼ばれました。
しかし、喜びもつかの間。ペニシリンが広く使われ始めて数年のうちに、すでに耐性菌(ペニシリナーゼ産生菌)が現れます。
以降、セフェム系・カルバペネム系・マクロライド系など、新しい抗菌薬が登場するたびに、それに対する新しい耐性菌が出現してきました。
8-2. 耐性菌と抗菌薬の現状〜絶えない“イタチごっこ”
現代の医療でもこの戦いは続いています。新しい抗菌薬が登場すれば、やがてそれに適応した耐性菌が現れる──まるで“イタチごっこ”のような状況です。
世界保健機関(WHO)は、薬が効かない感染症が増える「ポスト抗菌薬時代」の到来を警告しています。
一部の感染症では、すでに有効な抗菌薬がほとんど残されていない例もあります(例:多剤耐性グラム陰性菌、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌など)。
8-3. 未来に向けて私たちができること
新しい抗菌薬の開発は年々難しくなっています。
だからこそ、今ある薬を長く使い続けられるように守ること が、私たち全員に求められています。
- 不要なときに抗菌薬を使わない
- 処方された薬は指示どおりに飲み切る
- 手洗いやワクチンなどで感染そのものを防ぐ
- 医療者はガイドラインに基づいた適正使用を徹底する
これらは一見地味ですが、耐性菌を生み出さない最も確実な方法です。
👉「新しい薬が出るのを待つ」のではなく、「今ある薬を大切に使う」こと。 それが、未来の医療を守るために、私たち一人ひとりができる最も確かな方法です。
9. 自分自身でもできること
耐性菌の問題は、病院や医師だけが取り組むものではありません。私たち一人ひとりの生活習慣や環境づくりも、耐性菌を減らす大切なアクションになります。
たとえば、抗菌薬に頼らなくても感染しにくい環境を整えること。これが、抗菌薬の使用を減らし、最終的には耐性菌の発生を防ぐことにつながります。
特に、空気中のウイルスや細菌、ハウスダストなどを減らすために、感染予防に役立つアイテムを紹介しています。ぜひチェックしてみてください。
- 空気清浄機
- シャープ 空気清浄機 KI-SS50-W プラズマクラスター 25000↗️
→ウイルス・カビ・花粉・PM2.5に対応した加湿空気清浄機で、家庭でも手軽に導入できます。 - ダイキン ストリーマ空気清浄機 MCK505A-W↗️
→静音設計で、10年間フィルター交換不要。お手入れも簡単で長く清潔に使える加湿空気清浄機です。
- シャープ 空気清浄機 KI-SS50-W プラズマクラスター 25000↗️
- 除菌スプレー
- 花王 リセッシュ除菌EX プロテクトガード (本体+詰替用2個セット)↗️
→99%除菌・ウイルス除去を実現する除菌スプレー。衣類や布製品など、家庭内の衛生管理に手軽に使えます。
- 花王 リセッシュ除菌EX プロテクトガード (本体+詰替用2個セット)↗️
- 手指消毒グッズ
- サラヤ アルペット手指消毒用アルファ 1L 噴射ポンプ付 2個セット↗️
→食品原料で作られており、食品を扱う現場でも安心して使えるアルコール系消毒剤です。手指の衛生管理を手軽に行えます。 - 健栄製薬 手ピカジェルプラス 300ml↗️、手ピカジェルプラス 60ml(携帯用)×3個↗️
→家庭や外出先でも使いやすい高除菌タイプ。携帯用の製品もあり便利です。
- サラヤ アルペット手指消毒用アルファ 1L 噴射ポンプ付 2個セット↗️
などを日常的に活用することは、感染予防にとても有効です。
これらのアイテムは、直接「耐性菌」を減らすものではありませんが、感染そのものを防ぐことで、抗菌薬を使う機会を減らすことができます。
【参考文献】
- 日本感染症学会・日本化学療法学会.
抗微生物薬適正使用支援プログラム実践のためのガイダンス【2024年度改訂版】. ↩︎ - Zhao, X., & Drlica, K. (2001). Restricting the selection of antibiotic-resistant mutants: a general strategy derived from fluoroquinolone studies. Clinical Infectious Diseases, 33(Suppl 3), S147–S156. ↩︎

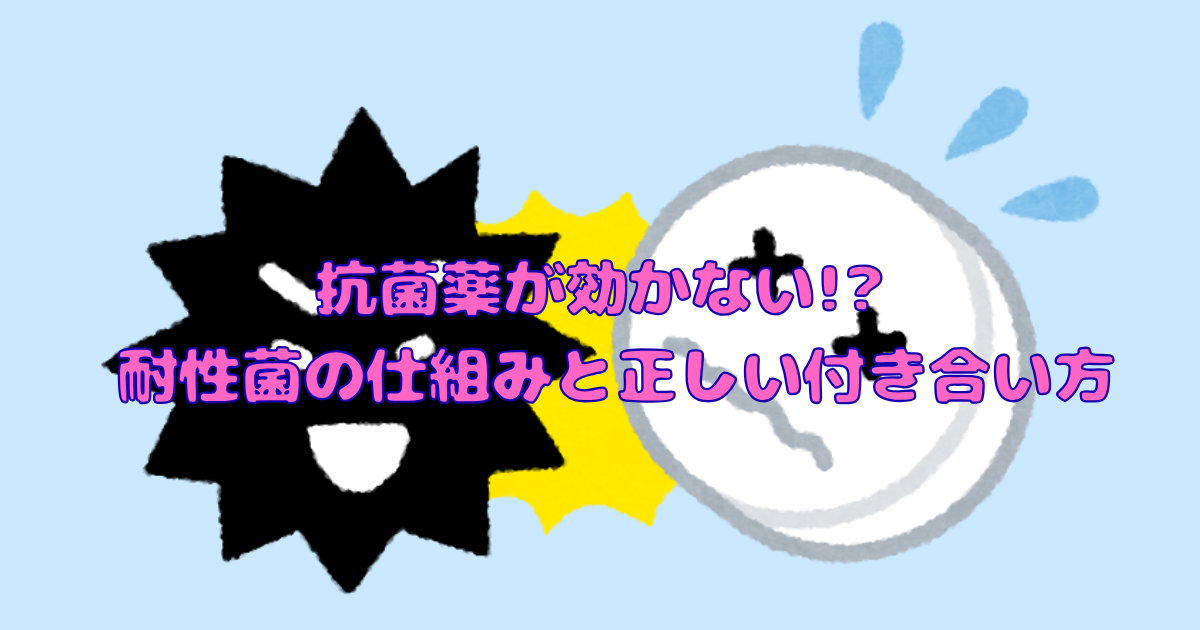
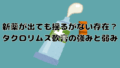
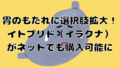
コメント