1. はじめに〜緑内障とは?
緑内障は、日本における失明原因の第1位とされる病気です。特徴的なのは、自覚症状がほとんどないまま進行する点で、気づいたときには視野が欠けていることも少なくありません。そのため「沈黙の病気」と呼ばれることもあります。
治療の基本は「眼圧を下げること(注釈1)」です。眼圧とは、目の中を満たす液体(房水)の圧力のこと。これが高いと視神経に負担をかけ、徐々に視野が狭くなってしまいます。現在の医療では視神経そのものを回復させる手段はなく、眼圧をコントロールすることが唯一の有効なアプローチとなっています。
これまでにも、プロスタグランジン関連薬やβ遮断薬など、多くの点眼薬が開発されてきました。しかし患者さんによっては十分に眼圧が下がらなかったり、副作用のために複数の薬を使い分ける必要があるなど、課題は残されています。
そこで注目されているのが、新しい作用機序を持つ「ネタルスジル」です。本記事では、従来薬と何が違うのか、なぜ画期的といわれるのかを中心にわかりやすく解説していきます。
「緑内障の詳しい解説については、以前のブログ記事👉 『知らないと危険!若者にも関係する白内障と緑内障の基礎知識』もぜひご覧ください。」
2. 既存の緑内障治療薬の種類と方針
大原則として、緑内障の治療は「眼圧を下げること」が中心となります。手段は薬物療法・レーザー・手術の3本柱で、患者さんの病型・病期に応じて選びます。薬物療法では必要最小限の薬剤で最大の効果を目指し、評価しながら調整します。
2-1. 既存の緑内障治療薬の種類
- プロスタノイド受容体関連薬(プロスタグランジン)
房水の“逃げ道”を広げて眼圧を下げる薬で、現在もっとも広く使われ、その効果から第一選択薬とされているグループです。ラタノプロストやタフルプロストなどのFP受容体作動薬に加え、近年ではオミデネパグ/イソプロピル(EP2受容体作動薬)も登場しました。 - β遮断薬
房水の産生を抑えるタイプ。眼圧効果は強いですが、全身への影響(ぜんそく・徐脈など)に配慮が必要なことがあるため、適応や併用は個別判断。 - 炭酸脱水酵素阻害薬
こちらも産生抑制が中心で古くから使用されています。単剤でも用いられることはありますが、併用で補助的に使用されます。 - Rhoキナーゼ阻害薬
繊維柱帯やシュレム管に関与し房水排出を促進します。第一選択薬に効果がないときに用いられ、充血の副作用がよくみられます。
2-2. 緑内障の薬物治療方針
緑内障の薬物治療は、非常に長期間にわたって継続することが前提となります。しかし、患者さんが症状を自覚しにくい病気であるため、「もう薬がなくても大丈夫だろう」と自己判断して点眼を中止してしまうケースが少なくありません。これが治療効果を妨げ、病状を進行させる大きな要因となっています。
ガイドラインでも、点眼治療の最大の欠点はアドヒアランス(自己治療継続のしやすさ)にあると指摘されています。緑内障治療薬は長期間にわたる使用が不可欠ですが、点眼の煩雑さや副作用による不快感が、治療中断の原因になりやすいのです。
したがって、アドヒアランスを高めるためには、以下のような工夫が望ましいとされています。
- 点眼回数を1日1回など、できるだけ少なくすること
- 複数の点眼薬を使用している場合は配合剤に切り替えること
- 患者自身が治療の必要性を理解し、納得して継続できるように説明を行うこと
つまり、緑内障の薬物治療においては「どの薬が強力か」だけでなく、どれだけ長くかつ安定して続けられるかが極めて重要なポイントとなります。
3. ネタルスジルの概要
ネタルスジルは現在、日本国内では承認申請中の段階であり、添付文書やインタビューフォーム(IF)といった正式な国内データはまだ公開されていません。
本章で記載する作用機序・臨床データ・副作用などの概要は、海外の添付文書(米国FDA資料など)や製薬メーカーが公開している情報を参考にした内容です。そのため、国内承認後には用法・用量、副作用の頻度、適応範囲などに変更が加わる可能性があることにご留意ください。(2025年9月現在)
3-1. ネスタルジルとは
3-1-1. 眼圧効果メカニズム
ネタルスジルが眼圧を下げる仕組みには、大きく2つのメカニズムがあります。
- Rhoキナーゼ(ROCK)阻害作用
眼の中では、房水と呼ばれる液体が絶えず作られ、線維柱帯(フィルターのような組織)を通って排出されます。線維柱帯が硬くなったり目詰まりを起こすと、房水が流れにくくなり眼圧が上がります。
ROCK阻害作用は、この線維柱帯を弛緩させて通り道を広げ、房水の排出を促すことで眼圧を低下させます。これは既存薬であるリパスジル(グラナテック®︎)点眼液と共通する作用です。
さらに、ROCK阻害薬は日中と夜間で眼圧下降効果に差が少ないとされており、従来のβ遮断薬や炭酸脱水酵素阻害薬で課題とされていた「夜間の眼圧コントロール不足」を補える可能性があると報告されています[1]。 - ノルエピネフリン・トランスポーター(NET)阻害作用
ネタルスジルには、ROCK阻害作用に加えてNET阻害作用もあります。NETを阻害すると、神経の間隙に存在するノルエピネフリン(NE)が増加し、その結果、房水を作る働きが抑えられると考えられています。
これは、従来の点眼薬にはなかった新しい作用であり、「房水の排出促進」と「産生抑制」の両面に働きかけることがネタルスジルの特徴です。
3-1-2. 用法
ネタルスジルは、通常1日1回の点眼で効果が得られるとされています。
既存のROCK阻害薬であるリパスジル(グラナテック®︎)が1日2回の点眼を必要とするのに対し、ネタルスジルは1回で済む点が大きな違いです。
点眼治療は「毎日決まった回数を忘れずに続けること」が重要ですが、実際には複数薬の併用や使用回数の多さが継続を妨げる要因となります。そのため、1日1回の投与で十分な効果が得られるネタルスジルは、長期継続のしやすさ(アドヒアランス改善)を考慮すると意義の点と考えられます。
3-1-3. 副作用
ネタルスジルに関して、海外臨床試験やFAERS(米国の副作用報告制度)などから報告されている主な副作用は以下の通りです。
- 結膜充血
最も頻度が高い副作用で、臨床試験では投与患者の多くに報告されています。FAERSデータでも「結膜充血」が副作用報告の第1位に挙げられており、やはり本剤に特徴的な有害事象といえます。リパスジル(グラナテック®)でも同様に高率で認められており、ROCK阻害薬全般の共通した副作用と考えられます。多くは軽度〜中等度で自然に軽快します。 - 視力障害・かすみ目
FAERS解析でも比較的頻度が高いものとして挙げられた副作用。こちらも多くは一過性で、点眼後に視界がぼやけるといった症状です。 - 眼刺激感・眼の違和感
点眼直後のしみる感じや異物感を指します。多くは短時間で軽快します。 - その他、アレルギー性眼瞼炎、角膜出血、目のかゆみなども挙げられています。
3-2. プロスタノイド受容体関連薬との比較
ネタルスジルの効果を、現在最も眼圧効果が高いとされる点眼液の一種、プロスタノイド受容体関連薬(ラタノプロスト)と比較した臨床試験があります。
- 28日間の第II相無作為化比較試験(n=224)
- ネタルスジル(0.02% 1日1回):平均眼圧低下 −5.7 mmHg
- ラタノプロスト(0.005% 1日1回):平均眼圧低下 −6.8 mmHg
結果から読み取れることは、ネタルスジルは全体的にはラタノプロストに比べてやや効果が劣るものの、ベースライン眼圧が26 mmHg以下の患者群では両者の効果はほぼ同等であり、26 mmHgを超える高眼圧群ではラタノプロストが優れていたという点です[2]。ここでは、非劣性が明確には示されていません。
一方で、ROCK阻害薬は日中と夜間で眼圧下降効果の差が少ないことが報告されており、日内変動を含めて評価すると、臨床的には同等以上の有効性を示す可能性があります。
さらに、既存薬(特にプロスタノイド受容体関連薬)で効果が不十分な症例において、ネタルスジルを併用することで追加効果が期待できることも臨床試験で示されています[3]。
3-3. 日本での承認申請
ネタルスジルは、2025年7月30日に参天製薬が日本国内で製造販売承認を申請した新しい緑内障治療薬です。参天製薬は眼科領域に特化した国内大手メーカーであり、日本における緑内障点眼薬の主要な供給元の一つでもあります。
以後、日本国内の治験成績や安全性評価も必要となるため、承認の可否や時期は厚生労働省やPMDA(医薬品医療機器総合機構)の審査に委ねられています。現時点では正式な発売時期は未定ですが、承認が下りれば、リパスジルに続く2つ目のROCK阻害薬として新しい選択肢が加わることになります。
3-4. 海外での使用実績
ネタルスジルは海外ではすでに承認および販売されており、ある程度の臨床使用の実績が積み重ねられています。
- アメリカ
2017年にFDA(米国食品医薬品局)から承認を受け、Rhopressa®(単剤)として販売されています。また、ラタノプロストとの配合剤である Rocklatan® も2019年に承認され、より強力な眼圧下降を必要とする患者さん向けに使われています。 - 欧州
欧州医薬品庁(EMA)でも承認され、ドイツやフランスなどの国で使用されています。 - アジア
韓国やシンガポールなどで使用されており、日本では2025年7月に参天製薬が製造販売承認を申請しています。
4. まとめ
ネタルスジルは、これまでの緑内障治療薬とは少し異なる特徴を持つ点眼薬です。
Rhoキナーゼ阻害作用によって房水の出口(線維柱帯)を広げるとともに、ノルエピネフリン輸送体阻害作用によって房水の産生も抑える「二重の作用」を持ちます。さらに、1日1回の点眼で効果が得られるという利便性もあり、継続しやすい治療選択肢となることが期待されています。
副作用として最も多いのは結膜充血ですが、ほとんどが軽度で短期間のうちに改善します。視界のぼやけや眼の刺激感なども報告されていますが、多くは一過性であり、通常は長期使用に大きな弊害となることは少ないと考えられます。
海外ではすでに単剤(Rhopressa®)や配合剤(Rocklatan®)として承認され、臨床的な実績が積み重ねられています。日本でも2025年7月に参天製薬が承認申請を行っており、今後承認されればリパスジルに続く2剤目のROCK阻害薬として新しい選択肢が加わることになります。
ネタルスジルは「夢の新薬」ではなく、既存治療に新たな選択肢を加える薬です。緑内障治療のゴールはあくまで「視野の維持」であり、そのための手段としてネタルスジルがどう活用されるのか、今後の臨床での評価が注目されます。
【参考文献】
- 日本医大医会誌. 緑内障に対する眼圧下降治療の現状と限界. 日医大医会誌. 2023;19(2):156. ↩︎
- Bacharach J, Dubiner H, Levy B, et al. Double-Masked, Randomized, Dose–Response Study of AR-13324 vs Latanoprost in Patients With Elevated Intraocular Pressure. Ophthalmology. 2015;122(12):2490–2497. doi:10.1016/j.ophtha.2015.08.009 ↩︎
- Asrani S, Bacharach J, Holland E, et al. Fixed-Dose Combination of Netarsudil and Latanoprost in Ocular Hypertension and Open-Angle Glaucoma: MERCURY-1 and MERCURY-2 Phase 3 Results. Adv Ther. 2019;36(2):251–265. doi:10.1007/s12325-018-0840-9 ↩︎

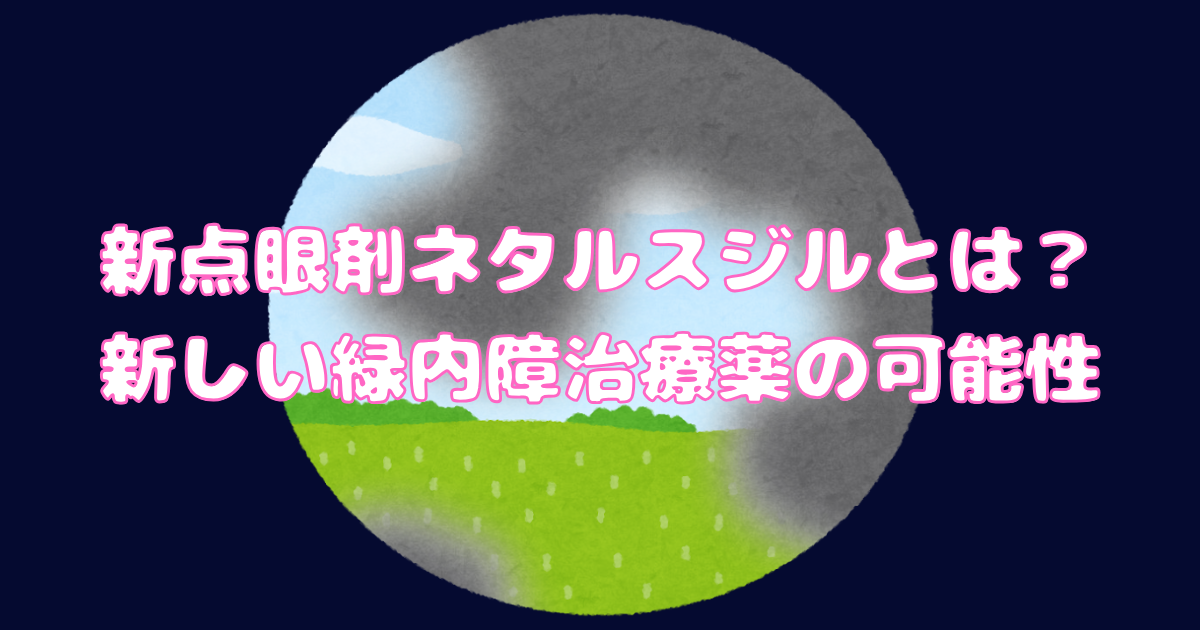

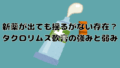
コメント