※本記事にはアフィリエイト広告を利用しています。商品リンクを経由して購入された場合、当サイトに収益が発生することがあります。
1. オレキシンとは?
1-1. オレキシンの概要
オレキシンとは、1998年に発見された、脳内で働く神経伝達物質の一つです。主に脳の視床下部という場所から分泌され、「食欲」や「睡眠と覚醒」のバランスをとる役割を担っています。
発見当初は、空腹のときに分泌が増え、食べたい気持ちが高まるという性質があったため、ギリシャ語で「食欲」を意味する“orexis(オレクシス)”から「オレキシン」と名付けられました。また、別の研究グループはこれを「ヒポクラチン」と呼んでおり、文献によっては両方の名前が登場しますが、今では「オレキシン」の名前が広く使われています。
その後の研究により、オレキシンは「目が覚めている状態」を維持する働きがあることもわかってきました。特に、日中に急に眠ってしまう「ナルコレプシー」という病気との関わりが強く、現在では「覚醒を保つ物質」としての役割のほうが知られるようになっています。
なお、この「覚醒を保つ」というオレキシンの作用をあえて抑えることで、眠気を促す薬が開発されました。それが、本剤をはじめとする「オレキシン受容体拮抗薬(orexin receptor antagonist:以下ORA)」と呼ばれるタイプの睡眠薬です。
1-2. オレキシンの薬理作用
オレキシンは主に中枢神経系に存在し、その神経は脳内のさまざまな領域に広く情報を伝達しており、多くの生理機能に関与しています。
中心的な作用としては、前項で述べた通り「覚醒状態を維持すること」であり、オレキシンが活性化すると脳は“起きているモード”に入ります。この他にも、動物実験などで以下のような作用が報告されています。
| 分類 | 薬理作用 | 補足 |
|---|---|---|
| 中枢神経系 | ・覚醒レベルの上昇 ・自発運動の増加 ・常同行動の増加 | オレキシンは「脳のアクセル」のような役割を果たし、 活動性を高める働きがあります。ナルコレプシー患者では これが欠け、日中の眠気が強くなります。 |
| 自律神経系 | ・交感神経の活性化 ・血圧や心拍数の増加 | オレキシンの活性により、いわゆる「戦闘モード (fight or flight)」に近い状態になります。 |
| 内分泌系 | ・血中コルチコステロン上昇 ・プロラクチン濃度の低下 | 覚醒だけでなく、ストレス応答やホルモンバランス にも影響を与えています。 |
| 代謝系 | ・摂食行動の制御 ・飲水量の増加 | 発見当初はこの作用が注目されていましたが、 現在は副次的な役割と位置づけられています。 |
2. クービビックの概要
クービビック®は、2024年12月に発売開始された、有効成分ダルドレキサントを含む、新しいタイプの睡眠薬「デュアルオレキシン受容体拮抗薬」に分類されます。同じ作用機序を持つ薬剤としては、すでにベルソムラ®(スボレキサント)やデエビゴ®(レンボレキサント)などが販売されています。
ORAはすべて医療用医薬品であり、市販はされていません(2025年5月現在)。また、向精神薬には指定されていないため、ベンゾジアゼピン系睡眠薬などに見られる処方日数制限は原則としてありません。ただし、クービビックは発売から1年未満の新薬であるため、現在は処方日数に制限(原則14日以内)が設けられています(※薬価収載日:2024年11月20日)。
2-1. メカニズム
クービビックは、オレキシン受容体(OX1RおよびOX2R)に選択的に拮抗することで、覚醒を維持する神経活動を抑制し、自然な入眠を促します。オレキシンは脳内で「覚醒維持のアクセル」のような役割を果たしており、これを止めることで過剰な覚醒状態を和らげることができます。
この作用は、従来のベンゾジアゼピン系(BZ系)睡眠薬とは異なります。BZ系が脳の活動を「直接的に抑える(=ブレーキを踏む)」のに対し、オレキシン受容体拮抗薬は「アクセルを離す=エンジンブレーキ」のように、覚醒の維持をやんわりと解除する仕組みです。つまり、(BZ系のように)強引に脳の興奮を鎮めて眠らせるのではなく、より自然な形で眠りに導くのが特徴です。
2-2. 効能効果
クービビック®︎の適応症は「不眠症」です。
一口に不眠症といっても、その症状にはさまざまなタイプがあります。大まかに分類すると、「入眠障害(寝つきが悪い)」と「中途覚醒(夜中に目が覚めてしまう)」の2つに分けられます。ORAは、比較的どちらのタイプにも効果を示しやすい「万能型」とされており、クービビックもこの特徴を持つ薬剤です。
また、クービビックは作用時間が過度に長くないことから、翌朝への眠気の持ち越しも比較的少ないとされています。これは、日中の活動を妨げず、自然な睡眠リズムをサポートするという点でも利点と言えるでしょう。
2-3. 用法用量
クービビック®︎は、通常成人に対して1日1回50mgを就寝直前に経口投与します。なお、患者の状態や副作用の出現状況に応じて、25mgへの減量が可能とされています。
服用のタイミングが「就寝直前」とされているのは、服薬後に速やかに眠気が現れるためです。起きた状態で行動を続けると、ふらつきや転倒などのリスクが高まる可能性があるため、安全性を考慮して「服用後はすぐに就寝できる環境」で服用することが推奨されています。
2-4. 臨床効果
クービビックの効果を評価するために、20~83歳の不眠症患者489名(うち65歳以上が約30%)を対象とした臨床試験が行われました。対象にはダリドレキサント25mgまたは50mg、比較対象としてプラセボを1日1回4週間就寝前に投与しました。
2-4-1. 主観的総睡眠時間(sTST)の延長
主要評価項目の一つ目は、患者が毎朝記録する「睡眠日誌」を用いた主観的総睡眠時間(sTST)の4週間後の変化です。
- プラセボ群(偽薬):平均で約19.7分の睡眠時間延長
- クービビック25mg群:平均で約29.3分の延長(プラセボとの差:約9.2分)
- クービビック50mg群:平均で約41.0分の延長(プラセボとの差:約20.3分)
特に50mg投与では、プラセボと比較して統計学的に有意な改善(p<0.001)が示されており、クービビックの有効用量として50mgが推奨される根拠となっています。
この結果から、クービビックは不眠症患者の主観的な睡眠時間を延ばす効果が明確に認められたことになります。
また、自然な眠気を促すメカニズム(オレキシン受容体拮抗)により、平均で30分以上の延長が期待できるため、睡眠の質を重視する患者にとって有効性の高い選択肢と言えるでしょう。
2-4-2. 主観的睡眠潜時(sLSO)の短縮
もう一つの主要評価項目は、就寝から入眠までにかかった時間、いわゆる主観的睡眠潜時(subjective Latency to Sleep Onset:sLSO)の4週間後の変化です。こちらも患者が毎日記録した「睡眠日誌」に基づいて評価されています。
- プラセボ群(偽薬):平均 約5.6分の短縮
- クービビック25mg群:平均 約13.0分の短縮(プラセボとの差 –約7.2分)
- クービビック50mg群:平均 約16.8分の短縮(プラセボとの差 –約10.7分)
ベースラインでは各群ともに平均して約53〜54分かかっていた入眠までの時間が、クービビック50mg群では4週間後に平均37.9分まで短縮されました。これはプラセボ群と比較しておおよそ10.7分の短縮に相当します。
「たった10分?」と思われるかもしれませんが、不眠症治療において入眠時間を10分以上短縮することは、臨床的に見ても十分に意味のある改善です。入眠までの時間が短くなることで、睡眠の質が向上し、翌日のパフォーマンスや生活の質にも良い影響が期待されるためです。
2-5. 副作用
2-5-1. 重大な副作用
クービビックの添付文書には、「重大な副作用」として特別に記載されている項目はありません。
たとえば、ベンゾジアゼピン系(トリアゾラムやブロチゾラムなど)や非ベンゾジアゼピン系の睡眠薬(ゾルピデムなど)などの従来のBZ系では、以下のような重大な副作用が懸念されてきました。
- 連用による薬物依存や離脱症状
- せん妄、幻覚などの精神症状
- 呼吸器高度低下患者に対する呼吸抑制
これらと比較すると、オレキシン受容体拮抗薬(ORA)であるクービビックは、これらの副作用リスクが低いと考えられており、特に長期使用時の安全性が期待されます。
2-5-2. 頻度の高い副作用
その他の副作用として、発生頻度の高い症状としては、以下の通りとなります。
- 3%以上 :傾眠
- 1〜3%未満:頭痛、疲労感、悪夢など
クービビックは睡眠薬であるため、日中の傾眠が副作用として比較的高頻度で現れる点には注意が必要です。とくに翌朝の注意力や集中力が低下する可能性があるため、自動車の運転や機械操作に従事する人では慎重な対応が求められます。
また、ORAに特徴的とされる副作用として、「悪夢」や「倦怠感(疲労感)」があります。これは、オレキシンが本来、レム睡眠(夢を見る睡眠)の抑制にも関与しているとされているため、オレキシン受容体の拮抗によってレム睡眠が相対的に増加し、「悪夢を見やすくなる」可能性があると考察されています
2-6. 併用禁忌および注意薬
2-6-1. 併用禁忌薬
クービビック(ダリドレキサント)は、主にCYP3A4という肝代謝酵素によって約90%が代謝されます。そのため、CYP3Aを強く阻害する薬剤と併用すると、ダリドレキサントの代謝が抑制され、血中濃度が上昇しやすくなります。この結果、効果が過剰になったり、副作用が強く出たりする可能性があるため、以下の薬剤との併用は禁忌とされています。
| 薬効分類 | 薬剤名(製品名例) |
|---|---|
| 抗真菌薬 | イトラコナゾール(イトリゾール®)、 ボリコナゾール(ブイフェンド®)、 ポサコナゾール(ノクサフィル®) |
| 抗菌薬 | クラリスロマイシン(クラリス®、クラリシッド®) |
| 抗HIV薬 | リトナビル含有製剤(ノービア®、カレトラ®) コビシスタット含有製剤 (ゲンボイヤ®、プレジコビックス®、シムツーザ®) |
| 新型コロナ 治療薬 | リトナビル含有製剤(パキロビッド®) エンシトレルビル(ゾコーバ®) |
| 抗悪性腫瘍薬 | セリチニブ(ジカディア®) |
特に、クラリスロマイシンに関しては、内科や耳鼻科など幅広い診療科で使用される薬であるため、より注意が必要だと思われます。
2-6-2. 併用注意薬
クービビック(ダリドレキサント)と併用に注意が必要な薬剤としては、以下のようなものがあります。
併用禁忌薬ほどの強力な影響ではないものの、同様にCYP3A4を阻害または誘導することで、クービビックの血中濃度に影響を与える薬剤が含まれます。また、中枢神経抑制作用を持つ薬は、併用により傾眠やふらつきなどの副作用が増強される可能性があるため注意が必要です。
| 影響の種類 | 薬剤の分類 | 薬剤例 |
|---|---|---|
| 作用を増強 | 中枢神経抑制薬 アルコール類 | フェノバルビタール クロルプロマジンなど |
| 血中濃度を上昇 | CYP3A阻害剤 | エリスロマイシン ジルチアゼムなど |
| CYP3A基質 | シンバスタチン タクロリムスなど | |
| P糖タンパク基質 | ジゴキシンなど | |
| 血中濃度を減少 | CYP3A誘導体 | リファンピシン カルバマゼピンなど |
2-7. その他注意事項
2-7-1. 特定の疾患を有する患者
- ナルコレプシーまたはカタプレキシー1のある患者
ナルコレプシーは、日中の過剰な眠気を特徴とする中枢性過眠症の一種です。クービビックは睡眠を促進する作用を持つため、すでに過剰な眠気がある患者では、その症状をさらに悪化させる可能性があります。 - 中程度以上の呼吸器障害のある患者
(※閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)および中等度以下の慢性閉塞性肺疾患(COPD)を除く)
ダリドレキサントは、中枢神経系の活動を抑制する可能性があります。そのため、呼吸器障害を有する患者では、呼吸抑制を助長するおそれがあることから、これらの患者を対象とした臨床試験は実施されていません。安全性が十分に確認されていないため、慎重な対応が必要です。 - 閉塞性睡眠時無呼吸および中等度以下の慢性閉塞性肺疾患患者
これらの患者については、短期間の臨床試験において一定の安全性が確認されているものの、長期使用に関する十分なデータは存在しません。特にOSA患者では、無呼吸エピソードの頻度や重症度に応じて、薬剤の影響を受けやすくなる可能性があるため、継続的なモニタリングや慎重な用量調整が求められます。
長期服用における臨床データが少ないとのことです。
2-7-2. 食事の影響
クービビックは、食事の影響を受ける可能性がある薬剤です。
外国の臨床試験では、健康成人に朝服用した際のデータではありますが、高脂肪食を摂取した場合には、薬が最高血中濃度に達するまでの時間(tmax)が平均1.28時間延長し、血中濃度のピーク(Cmax)は15.6%低下したとの報告があります。
現時点では「夜食の摂取が薬効にどのような影響を与えるか」についての明確な臨床データはないものの、これらの結果を踏まえると、食事の影響により入眠までの時間が延長する可能性を示唆します。よって、食事中もしくは食事直後の服用、特に高脂肪の夜食は避けるのが望ましいと考えられます。
3. 主な睡眠薬との違い
現在の医療現場において、不眠症治療に用いられる主な薬剤は、大きく以下の3つの分類に分けられます:
- BZ作動薬(ベンゾジアゼピン系・非ベンゾジアゼピン系)
脳内の抑制性神経伝達物質「GABA」に作用することで、神経活動を抑え、催眠効果を発揮します。優れた入眠効果があり、古くから用いられていますが、依存性や持ち越し効果、筋弛緩作用による転倒リスクが懸念されます。近年まで最も使用されていた系統の眠剤です。 - メラトニン受容体作動薬
睡眠・覚醒リズムの調整を担うホルモン「メラトニン」に作用し、体内時計を整えることで自然な眠りへと導きます。依存性が少なく、生活リズムの乱れからくる体内時計のずれによる不眠に適します。 - オレキシン受容体拮抗薬
覚醒を維持するオレキシンという神経伝達物質の働きを抑えることで、より“自然な眠気”を引き起こします。近年登場した新しい薬剤群であり、依存性が極めて少ないとされ、従来の睡眠薬で効果が不十分だった患者にも選択肢となります。
従来使用されてきたBZ系薬は即効性に優れていますが、依存性や副作用のリスクが課題となっていました。近年では、ORAやMT作動薬といった新しい機序の薬剤が登場し、より安全性を重視した治療への移行が進められています。
以下の表は、それぞれの薬剤の特徴を比較したものです。
| 種類 | BZ系薬 | OX拮抗薬 | MT作動薬 |
|---|---|---|---|
| 作用機序 | GABA_A受容体に作用し神経抑制を促進 | OX1RとOX2Rを拮抗し覚醒を抑制 | メラトニン受容体を刺激し概日リズムを調整 |
| メリット | 種類が豊富で対応力がある | 自然睡眠に近い | 自然睡眠に近い 併用してはいけない薬が非常に少ない |
| デメリット | 併用してはいけない薬が多い 高齢者では認知機能低下や転倒のリスク | 吸収率が食事に影響を受けやすい 特殊な副作用(悪夢、疲労感など)がある 効果に個人差がある | 即効性に乏しい 他眠剤からの切り替えが難しい |
| 依存性 | 高い | 低い | 非常に低い |
| 持続時間 | 超短時間〜長時間 と各薬により異なる | 中時間 | 短〜中時間 |
| 臨床的使用例 | 不眠症、不安症、鎮静 | 不眠症、ナルコレプシー | 入眠困難の改善、時差ボケ |
4. 既存のオレキシン受容体拮抗薬(ORA)との違い
クービビックは、ベルソムラ、デエビゴに続く第3のORAです。
結論から言えば、3剤ともOX1RおよびOX2Rに作用する「デュアルオレキシン受容体拮抗薬」であり、大きな違いはありません。いずれも就寝直前に服用し、主な副作用としては傾眠・悪夢・倦怠感(疲労感)などが共通しています。
しかし、細かく見ていくと、薬物動態や副作用発現率、併用薬の制限、患者背景への適応などに違いがあり、使い分けのポイントになります。以下に、各薬剤の特徴を長所・短所に分けて整理しました。
| 薬剤名 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| ベルソムラ®︎ (スボレキサント) | 重度の肝障害患者も服用可 | 入眠作用はやや弱め 吸湿性があり一包化できない |
| デエビゴ®︎ (レンボレキサント) | 併用禁忌薬がない | 半減期が長く、翌朝への持ち越しリスク高 |
| クービビック®︎ (ダリドレキサント) | 副作用発症率が比較的少ない 半減期が短いため、持ち越しにくい | 新薬のため、2025年12月までは 14日分までの処方制限あり |
■ 使い分けのポイント
- 肝機能に不安がある場合は、ベルソムラが選択肢となります。
- 多剤併用で相互作用が懸念されるケースでは、デエビゴが比較的安全。
- 朝の眠気残りをできるだけ避けたい場合は、クービビックが適しています。
また、薬剤ごとの「作用の強さ」は個人差が大きく、同じ用量でも患者ごとの体感は異なるため、実際の効果や副作用は試用しながら見極める必要があります。
【番外編:市販で試しやすい睡眠改善の選択肢】
クービビックのような医療用医薬品は、医師の診察を受けて処方されるものであり、誰でも簡単に使用できるものではありません。
一方で、市販薬や睡眠環境を整えるためのグッズなどは、比較的気軽に試せる選択肢です。薬剤師の視点から、少しでも睡眠に寄与できるような商品をいくつかご紹介します。
- ドリエル®12錠
→ ヒスタミン受容体ブロックによる鎮静作用により、一時的な不眠に使える市販薬。寝つきが悪かったり、眠りが浅い方に有効。 - DHC GABA
→神経の興奮を抑える作用を持つGABAを配合。睡眠の質改善に寄与する可能性があり、臨床試験では100mg/日で有効性も脚[1](本製品は1日目安量200mgを含有) - 蒸気でホットアイマスク
→ 心地よい温熱で目元をほぐし、リラックスしながら眠りにつけます。 - スタンフォード式 最高の睡眠(電子書籍)
→ 睡眠研究の知見をわかりやすくまとめたベストセラー本。生活習慣の改善にも役立ちます。
ご自身に合った方法を取り入れることで、より良い睡眠習慣につながるかもしれません。
【参考文献】
- Yamatsu, A., et al. Daily intake of γ-aminobutyric acid improves sleep by reducing sleep latency and improving sleep efficacy. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition. 2020; 67(3): 267–273. ↩︎

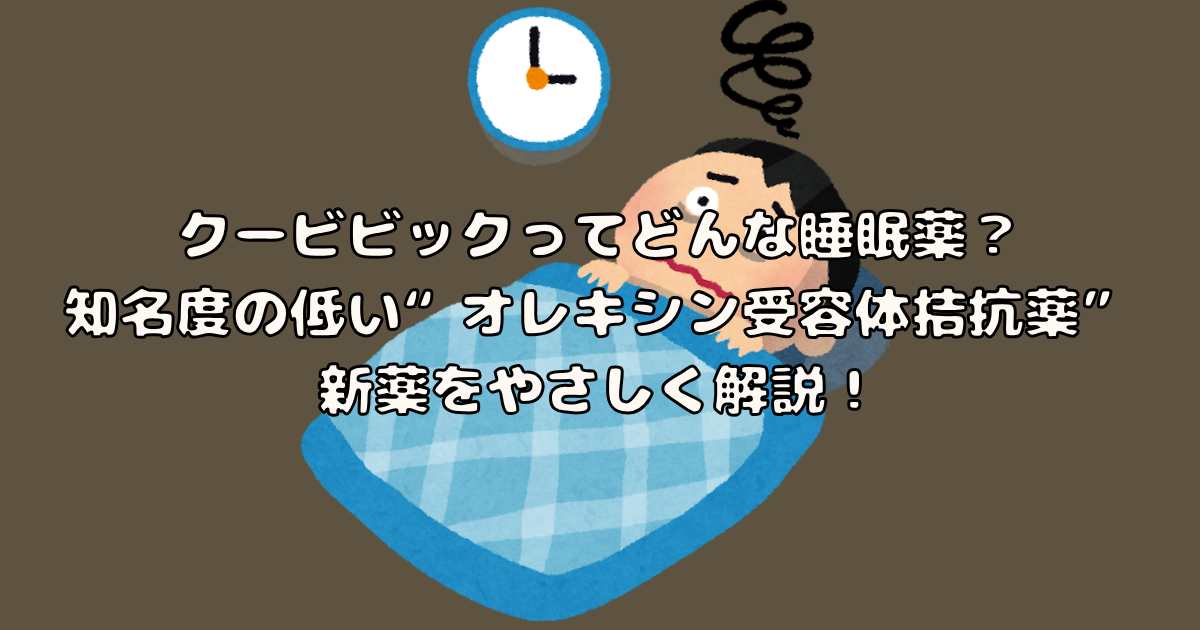
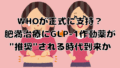
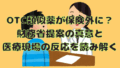
コメント