1. WHOが“推奨”を表明。その背景とは?
2025年4月、世界保健機関(WHO)が成人の肥満症の治療として、GLP-1受容体作動薬(セマグルチドなど)について、「一定の条件下での使用を支持する」という見解を示唆しました。まだ正式な発表ではないようですが、それでも世界の医療現場に与える影響は小さくありません。
今回のポイントは、「世界の肥満人口の約7割が、低・中所得国に集中している」という現状です。「肥満は先進国の問題」と思われがちですが、すでにそうとは言えなくなっており、WHOも治療薬を含めた医療資源へのアクセス改善が急務であると明言しました。
また、WHOの広報担当者は「WHOは2022年以降、子ども・青年・成人というすべての年齢層を対象に、肥満の予防・ケア・治療に関する包括的なガイドライン作成に取り組んでいる」とコメントしています。つまり、GLP-1作動薬のような薬剤に対する評価も、こうした流れの一環としてなされているというわけです。
現在、GLP-1作動薬は高額であり、高所得国の一部でしか使用されていないのが現状です。
しかし今後は、肥満という“世界的課題”に対し、誰もが公平に医療を受けられる環境をどう整えていくかが、国際的な議論の焦点となっていくでしょう。
2. GLP-1受容体作動薬のおさらい
GLP-1受容体作動薬とは、腸から分泌されるホルモン「GLP-1(グルカゴン様ペプチド-1)」の働きを模倣する薬で、主な作用は以下の3つです。
- 食欲を抑える(食べ過ぎを防ぐ)
- 胃の動きを遅らせる(満腹感を持続させる)
- 報酬系の抑制(甘いものや油っこいものの欲求を抑える)
デュアルアゴニストであるゼップバウンドは、GIP受容体作動薬との相乗作用により、さらなる減量効果が期待されれます。
一方で、副作用としては吐き気、嘔吐、下痢、便秘などの消化器症状がよく見られます。まれに、膵炎や胆石、低血糖(糖尿病治療薬と併用時)など重大副作用が報告されることもあり、医師の管理下での適正使用が重要です。
3. 肥満治療薬の実力
WHOが推奨の対象として挙げたのは、GLP-1受容体作動薬を主成分とするウゴービ®︎(セマグルチド)と、GIP/GLP-1デュアル作動薬のゼップバウンド®︎(チルゼパチド)などです。
3-1. 減量効果
ウゴービは週1回の皮下注射で使用され、臨床試験ではおおよそ10〜15%の体重減少が報告されています。一方のゼップバウンドは、さらに強い効果が期待され、20%近い減量効果が示された研究もあります。
こうした減量効果は、欧米人などBMIの高い集団に限らず、日本人を対象とした臨床試験でも有効性が確認されつつあります。また、単に体重が減るだけでなく、食事量の減少や、甘いものや脂っこいものなどへの嗜好品の渇望が薄れるといった行動変容も報告されています。
3-2. 血管疾患リスクの軽減
GLP-1受容体作動薬(セマグルチドやリラグルチドなど)は、「体重を減らす薬」として注目されていますが、実はそれだけではありません。近年の研究で、心臓病などのリスクを下げる可能性があることも分かってきています。
特に注目すべきは、2023年に報告されたSELECT試験という大規模臨床試験の結果。心臓病の既往歴がある肥満者を対象にしたところ、GLP-1作動薬(セマグルチド)を使うことで、心筋梗塞や脳卒中などの「命にかかわる心血管イベント」が約20%も減ったという衝撃的なデータが得られました。
こうした結果から、GLP-1作動薬は「痩せる薬」ではなく、“命を守る薬”としてのポテンシャルも秘めていることが分かります。
詳しくは、以下の記事でそれぞれの薬剤について解説していますので、あわせてご覧ください。
4. 肥満症治療薬の現状の問題点
- 高額な治療費
- 肥満治療薬はGLP-1受容体作動薬を始めとして高価であり、高額な治療費は患者さん個人の負担だけでなく、公的保険制度の財政にも大きな影響を与える可能性があります。
- 上記により、特に低・中所得国でのアクセスを制限する原因となっていっています。
- 美容やダイエット目的の使用
- 近年特に痩せ願望が過剰になり、過度なダイエットが一般的な問題として取り上げられています。特に、日本では若年層を中心に、痩せていることが美しさや健康の象徴と見なされる傾向が強まっています。
- さらに、低体重を追い求めるあまり、健康を害するリスクが高まっていることが懸念されています。女性であれば、低体重によるホルモンバランスの乱れや免疫力の低下、生理不順など、健康に対する悪影響が現れやすくなります。これらのことが懸念され、厚生省や医師会の中でも肥満治療薬の使用がより慎重になっています。
- 処方に関わる厳格な条件
- 現在、日本においては肥満は疾患としてみなされていません。したがって、ウゴービなどの肥満治療薬を処方するには、単にBMI25以上の基準を満たすだけでなく、さらに高いBMIもしくは肥満に関連する健康障害を合併しているなどの厳しい条件が必要になってきます。
- さらに、医師や医療機関側にも制限があります。たとえば、特定の学会に所属していたり、一定の治療経験を持つ医師が在籍する医療機関でなければ処方できないといった制約があり、医療アクセスの面でもハードルが高い状況です。
- 薬剤供給の逼迫と優先順位の問題
- GLP-1作動薬は、もともと糖尿病治療薬として開発使用されてきた経緯があり、現在も一部で供給不足が続いている状況です。
- 今後、肥満治療目的での需要がさらに高まれば、本来必要とする糖尿病患者に十分に行き渡らない可能性も懸念されています。適正使用と供給体制の整備が急務となっています。
- 社会的な偏見
- 肥満治療薬の使用に対する社会的な偏見や誤解が存在し、薬物療法に抵抗感を持つ患者も未だ多いです。
- 肥満自体へのスティグマが、治療を受けることへの障壁となることがある。
5. さいごに
ウゴービなどの肥満治療薬使用について、上記の通り現状さまざまな問題点があり、特に肥満治療薬の使用においては安全性の担保が最も重要であり、薬の副作用や使用方法を徹底的に確認することは大前提です。また、過度なダイエットや無理な体重減少を避けることも、健康維持には欠かせません。しかし、今回のWHOの見解を受け、私個人の意見としては推進の立場であることは変わりません。
肥満は単なる見た目の問題ではなく、糖尿病や心血管疾患といった多くの生活習慣病に直結するため、適切な治療が必要です。その意味でも、治療薬の適正使用は、肥満に悩む多くの人々にとって有益な手段となり得ます。
とはいえ、日本国内ではまだ慎重な立場が多く、医療現場でも生活習慣改善が最優先されています。このまま薬物治療の安全性が確認され、医師の指導のもとで使用される環境が整えば、今後より多くの患者にとって選択肢となる可能性が高いと考えています。
今後もWHOの動向や国内外での治療薬に関する情報を注視し、新たな情報が出た際には取り上げていきたいと考えています。引き続き、肥満治療に関する正確な情報を提供し、皆さんの健康管理に役立つ記事をお届けできるようにしたいと思っています。



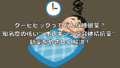
コメント