1. はじめに
2025年の百日咳患者数は、4月時点ですでに現行の感染症発生動向調査体制となった2018年以降で最多となっており、流行が全国に広がりつつあります。感染は全国的に広がっており、一部地域では警戒レベルに達していると報じられています。特に乳幼児に感染した場合、重篤化や入院管理が必要になることもあるため、注意が必要です。
百日咳は「子どもの病気」と思われがちですが、実は大人が感染源となって家庭内で広がるケースも多く、誰にとっても他人事ではありません。
本記事では、薬剤師の視点から、百日咳の基本知識や見分け方、対処法についてわかりやすく解説します。
2. 百日咳とは?
百日咳は、百日咳菌(Bordetella pertussis)によって引き起こされる急性の気道感染症で、けいれん性の激しい咳発作が特徴です。年齢を問わず感染する可能性がありますが、特に免疫が未熟な乳児では重症化しやすく、肺炎や脳症を併発して命に関わることもあります。
かつてはワクチン接種の普及により患者数が大きく減少しましたが、近年では、接種を受けていない人や、接種から年数が経ち免疫が低下した人を中心に、再び発生数が増加傾向にあります。世界的にも散発的な流行が報告されており、注意が必要な感染症の一つとなっています。
2-1. 主な症状
百日咳の症状は、一般的な風邪と区別がつきにくい初期段階から始まり、やがて特有の激しい咳へと進行します。病状は大きく3つの時期に分けられ、それぞれで特徴が異なります。
(1) カタル期(初期):感染後 1〜2週間程度
初期は、くしゃみ、鼻水、軽い咳など、いわゆる“風邪のような症状”が中心です。この段階では百日咳と診断するのが非常に難しく、見逃されやすいのが特徴です。しかし、この時期が最も感染力が強いため、注意が必要です。
(2) 痙咳期:カタル期後2〜3週間程度
次第に咳が激しくなり、連続する咳の後にヒューッという吸気音を伴う“けいれん性の咳発作”が現れます。
特に乳幼児では、咳によって顔が赤くなったり、呼吸が止まりそうになるほど強くなったりすることもあります。また、咳発作による嘔吐や睡眠障害、食欲不振などの全身症状も見られるようになります。
成人では典型的な発作が見られにくいことも多く、長引く咳(遷延性咳嗽)の原因として発見されることもあります。
(3) 回復期
咳の頻度や重症度は徐々に軽くなっていきますが、完治までには数週間から数カ月を要する場合もあり、体力を消耗しやすい点に注意が必要です。また、回復期でも咳がぶり返すことがあるため、油断せず体調管理を続けることが重要です。
2-2. 感染経路
百日咳は飛沫感染が主な感染経路ですが、咳やくしゃみで飛んだしぶきが直後に付着した物体に触れ、その手で鼻や口を触ることで感染が広がる可能性もあります。ただし、こうした接触感染のリスクは限定的で、日常的な手洗いによって十分に予防が可能です。
2-3. 治療法
2-3-1. 治療薬
百日咳の治療において、生後6ヶ月以上の方には抗菌薬が使用されることがあります。特に、マクロライド系抗菌薬(アジスロマイシンやクラリスロマイシン)は、効果が高く、最もよく用いられる薬剤です。咳の出現から通常は約3週間ほど病原菌の排出が続くとされていますが、適切な抗菌薬の投与を受けることで、5日ほどでほぼ菌の排出が止まることが多いです。そのため、早期に抗菌薬を投与することが、患者の回復にとってだけでなく、感染拡大を防ぐためにも非常に重要となります。
対症療法としては、鎮咳去痰薬や気管支拡張薬などの薬が用いられることがありますが、ひどい咳に対し通常の咳止めの効果は限定的となります。
2-3-2. 耐性菌の問題
抗菌薬による治療において、常に懸念されるのが薬剤耐性菌の出現です。百日咳も例外ではなく、マクロライド系抗菌薬に耐性を示す「マクロライド耐性百日咳菌(MRBP)」が報告されています。近年では世界的に徐々に拡大傾向にあり、日本国内でも2018年にすでに2例が確認されました。さらに、百日咳の再流行が見られた近年には、治療を行ったにもかかわらず死亡に至った症例も報告されています。
このような背景から、発症後に可能な限り早期に抗菌薬治療を開始することは選択肢の一つであるものの、そもそも感染しないためのワクチン接種の重要性があらためて注目されています。
2-4. 予防
百日咳は、病原菌の感染力が非常に強いことが特徴で、特に免疫を持たない人々に対しては高い確率で感染します。そのため、流行時には予防が非常に重要となります。
2-4-1. 日常生活における予防
百日咳の予防は、通常の他の感染症と同様であり、ワクチンおよび基本的な日常生活の衛生管理が重要となります。
- 手洗い・うがいを徹底し、外出後や食事前には必ず行いましょう。
- 咳エチケットを守り、咳やくしゃみをする際は、ティッシュやハンカチで口と鼻を覆い、飛沫感染を防ぎましょう。
- 感染者と接触を避け、特に乳幼児や高齢者との接触時には十分注意が必要です。
2-4-2. 予防ワクチン
百日咳に対しては、感染拡大を防ぐうえでワクチン接種が最も重要な予防策となります。有効なワクチンには、3種混合(DPT)、4種混合(DPT-IPV)、5種混合(DPT-IPV-Hib)があり、現在日本では主に5種混合ワクチンが用いられています。
定期接種の対象となる乳幼児には、生後2か月から接種が始まり、間隔をあけ計4回接種を受けます。さらに、日本小児科学会は、就学前での追加接種を推奨する提言しています。
なお、百日咳は乳幼児期のワクチン接種だけでは終わりません。近年では成人においても、希望者は任意接種としてワクチンを受けることが可能となっています。特に、乳幼児や高齢者などハイリスク者と接する機会が多い方は、追加接種を検討することが推奨されています。
3. 百日咳の再流行とその背景
百日咳は日本では定期接種の対象となっており、多くの子どもがワクチンを接種しています。それにもかかわらず、近年特に特に今年に入り再び報告数が増加し、再流行と呼ばれる状況が見られます。「なぜワクチンを打っているのに広がるのか」という疑問を持つ方も多いかもしれません。その背景には、以下のような複数の要因が関係しています。
- 乳幼児期以降の免疫の低下:百日咳ワクチンは時間の経過とともに抗体価が下がるため、就学前や思春期以降に再感染するリスクがあります。
- 成人の無症候性感染:咳が軽度で済む成人が気づかずに感染源となり、乳児など重症化リスクの高い世代に感染を広げるケースが報告されています。
- コロナ禍の影響:外出制限や感染対策により一時的に感染症全体が抑えられていた反動で、集団免疫が低下し、再流行しやすい土壌ができていると考えられています。
4. 百日咳に関するQ&A
Q1. 以前百日咳に感染したことがありますが、再度感染することはありますか?
百日咳に対する免疫は、感染やワクチン接種後も時間の経過とともに低下していくことが知られています。自然感染であってもワクチンにより得た免疫であっても同様です。よって、一度百日咳にかかっていたとしても、再び症状が出てしまう恐れもあります。そのため、就学前の5〜6歳における追加のワクチン摂取が推奨されています。
Q2. 流行しやすい季節はいつですか?
A2. 百日咳は年間を通じて発生しますが、例年春から夏にかけてやや増加傾向が見られると報告されています。ただし、季節にかかわらず流行することもあり、油断は禁物です。特に最近の再流行では、従来よりも発生時期が拡大している傾向も指摘されています。
Q3. 百日咳は喘息と似た症状が出るようですが、違いはありますか?
A3. 百日咳も喘息も、どちらも咳が長引くため、症状だけでは区別が難しい場合があります。特に百日咳では、発作的に激しい咳込みが続き、咳の合間に「ヒュー」という吸気音(笛声様吸気音)が特徴的にみられることがあります。一方で喘息は、気道の慢性的な炎症により、呼吸時に「ゼーゼー・ヒューヒュー」という呼吸音(喘鳴)が持続するのが一般的です。
また、百日咳は感染症であり、周囲への感染リスクがある点も大きな違いです。自己判断は難しいため、咳が長引く場合や特徴的な症状が出た場合には、早めに医療機関を受診しましょう。
Q4. 百日咳に対してどのような消毒が有効ですか?
A4. 百日咳の原因菌である百日咳菌(Bordetella pertussis)は、芽胞を形成しないため、アルコール、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウムなど、一般的な消毒剤で効果的に不活化できます。
流行時には手指衛生を徹底するのはもちろん、ドアノブや手すりなど、頻繁に触れる場所もこまめに消毒することが、感染拡大防止に役立ちます。
Q5. 子供が百日咳に感染してしまいましたが、登校してもいいのでしょうか?
A5. 百日咳は、学校保健安全法において「第2種感染症」に分類されています。
そのため、通常は「特有の咳が消失するまで」または「適正な抗菌薬治療を開始して5日間が経過するまで」の間、出席停止となります。
ただし、病状に応じて学校医や主治医が「感染のおそれがない」と判断した場合は、上記に限らず登校が認められることもあります。
5. おわりに
近年、コロナ禍による外出自粛や感染対策の影響で、私たちの免疫機能が低下していることが指摘されています。そのため、百日咳に限らず、さまざまな感染症が以前より広がりやすくなっている状況です。
流行期に限らず、手洗い・うがい・消毒などの基本的な感染対策は、日常的に継続して行うことが大切です。これにより、感染症の拡大を未然に防ぐ効果が期待できます。
また、百日咳は子どもだけでなく、大人にも発症する可能性がある感染症です。特に、今回ご紹介したような「特徴的な長引く咳」などの症状がみられた場合には、早めに医療機関を受診しましょう。自分自身の体を守ると同時に、周囲への感染拡大を防ぐことにもつながります。
日常生活の中でのちょっとした心がけが、自分と大切な人たちを守る大きな力になります。今後も感染症対策を怠らず、健やかな日々を送りましょう。


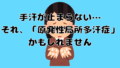
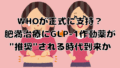
コメント