1. ゼップバウンドとは?
1-1. ゼップバウンドの特徴
ゼップバウンド®︎(成分名:チルバゼチド)は、2025年4月に日本で発売される新しい肥満治療薬です。この薬は、消化管ホルモンであるインクレチンに関与する受容体に働きかけ、血糖値の調節や食欲の抑制、体重減少および脂肪燃焼をサポートする効果があります。これまでの肥満治療薬と比較して、新たな治療選択肢として期待されています(ただし、同成分剤のチルバゼチドとしては、糖尿病治療薬マンジャロ®︎として2023年より使用されています)。
ゼップバウンドは、以前取り上げたGLP-1受容体作動薬である「ウゴービ®︎」と類似した作用がありますが、その決定的な違いは、デュアルアゴニストである点です。つまり、ゼップバウンドは、GLP-1だけでなく、GIP受容体にも作用することで、より高い効果が期待されます。
1-2. デュアルアゴニストとは
デュアルアゴニストは、2つの異なる受容体に同時に作用する薬のことを指します。ゼップバウンドの場合、GLP-1受容体とGIP受容体の両方に作用します。これにより、従来のGLP-1アゴニスト薬(例:ウゴービ)と比較して、より強力な効果が期待されます。
さらに、デュアルアゴニストの上をいく、GLP-1/GIPに加えてグルカゴン受容体アゴニストの働きも併せ持つトリプルアゴニストである「レタトルチド」も現在開発中であり、さらなる効果が期待されています。
1-3. デュアルアゴニストの相乗効果
1-3-1. GLP-1とGIP
GLP-1(グルカゴン様ペプチド-1)とGIP(グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド)は、どちらも血糖値を調節する小腸から分泌されるホルモンであり、インクレチンと言われています。それぞれの作用には特徴的な違いがあります。GLP-1は主にインスリン分泌を促進し、食欲抑制作用を持つことで知られています。一方、GIPはインスリン分泌の促進だけでなく、脂肪細胞での脂質合成作用もあり、より多様な生理的効果を示します。
- GLP-1受容体アゴニスト
食欲の抑制、満腹感の持続、報酬系(甘いものやジャンクフードなどの欲求)抑制します。詳細はウゴービ記事の4. ウゴービの減量メカニズムの項を参照してください。 - GIP受容体アゴニスト
- GIPは満腹ホルモンである、「レプチン」を介して食欲を抑制し、過食の抑制が期待されます。また、脂肪代謝の調整を通じて体重減少にも寄与する可能性があります。
- GLP同様に、胃内容物排泄を遅延させることで、満腹感を持続させます。
- さらに、単独では効果が得られない糖尿病患者に対し、GLP-1との相互関係で効果を上昇します。
1-3-2. GIP抵抗性
近年の研究では、糖尿病患者においてGIP抵抗性が見られることが確認されています。GIP抵抗性とは、通常、GIPが持つインスリン分泌促進や血糖調節作用が十分に発揮されない状態を指します。この現象は、高血糖が持続することによって起こることが多いです。興味深いことに、血糖値が低下すると、このGIP抵抗性が解消されることが分かっており、GLP-1の作用によってGIPの効果がさらに引き出される可能性があるのです。
そのため、GLP-1とGIPの組み合わせ治療は、相互作用を活かし、より強力な血糖コントロールと脂肪代謝の改善が期待できる新しいアプローチとして注目されています。このデュアルアゴニストの使用により、糖尿病治療や肥満治療の効果を高めることが可能となります。
2. ゼップバウンドとウゴービの比較
ゼップバウンド(チルゼパチド)は、2024年12月に米国イーライリリー社が発表した第3b相非盲検無作為化臨床試験であるSURMOUNT-5試験の結果において、注目すべき成果を挙げています。この試験では、ゼップバウンドが72週間の治療後に20.2%の平均体重減少を示し、ウゴービ(セマグルチド)の体重減少率13.7%を上回る優れた結果が確認されました。具体的には、ゼップバウンドはウゴービに比べて、相対的に47%多くの体重減少を実現したことが報告されています。
この試験は、糖尿病ではない肥満症のある成人、および体重に関連する健康障害を持つ過体重の成人を対象に実施され、ゼップバウンドは主要評価項目および5つの副次的評価項目すべてにおいてウゴービを上回る結果を示しました。
このデータは、ゼップバウンドがウゴービに対して、より高い効果を示す可能性があることを示唆しており、今後の肥満治療において新たな選択肢となることが期待されています。
3. ゼップバウンドの詳細
3-1. 効能効果
ゼップバウンドの適応症は、BMIなどの適応基準付きの「肥満症」に対してです。詳細な条件に関しては、ウゴービと全く同じであるため、そちらのブログ記事を参照してください。
3-2. 用法用量
通常、成人にはゼップバウンドを週1回皮下注射します。その後、4週間ごとに2.5mgずつ増量し、10mgまで増やします。スケジュールは以下の表を参照してください。
| 投与期間 | 投与量 |
|---|---|
| 1〜4週目 | 2.5mg |
| 5〜8週目 | 5mg |
| 9〜12週目 | 7.5mg |
| 13週目以降 | 10mg |
また、患者の状態により用量を調整できます。
- 減量する場合:週1回5mgまで減量可。
- 増量する場合:4週間以上の間隔で2.5mgずつ増やし、最大15mgまで増量可。
3-3. 副作用
3-3-1. 重大な副作用
重大な副作用としては、主に以下の3項目が挙げられます。
- 低血糖
脱力感・著しい空腹感・冷や汗・動悸・めまいなどの低血糖症状が現れることがあります。特に、2型糖尿病患者においては、インスリン製剤やスルホニル尿素剤を併用する際は重篤な症状を発現しやすくなります。
ただし、本剤はインクレチンに関与する効果であり、血糖値に応じてインスリン分泌を調節するため、低血糖の危険性はウゴービと同様に高いものではありません。 - 急性膵炎
嘔吐を伴う継続した腹痛があった場合は直ちに使用を中止し、適切な処置を受ける必要があります。 - 胆嚢炎、胆管炎、胆汁うっ帯性黄疸
胆嚢や胆管に関連する副作用を引き起こすことがあります。これには、腹痛や他の腹部症状が含まれる場合があります。こうした症状が継続的に現れた場合は、胆嚢炎や胆管炎、胆汁うっ帯性黄疸を疑い、必要に応じて検査を行い、適切な治療を受けることが推奨されます。
腹痛などの腹部症状が継続した場合は、必要に応じ検査や適切な処置を受ける必要があります。
3-3.2. その他の副作用
ゼップバウンドの使用により、比較的頻繁にみられる軽度の副作用として、以下の2つのカテゴリーが挙げられます。
- 消化器症状:ゼップバウンドは GLP-1およびGIP受容体作動薬の作用により、胃内容物の排出を遅らせ、満腹感を持続させることで体重減少効果を発揮します。しかし、この機序により 消化器系の副作用は避けられず、以下のような症状が比較的高頻度で発生します。
- 悪心・嘔吐
- 消化不良・食欲減退
- 便秘・下痢・腹痛
- こうした副作用は 特に治療開始初期や増量期に多く見られます。徐々に体が適応することで軽減することが多いですが、症状が強い場合は 一時的な減量 などが考慮されることもあります。
- 注射部反応:本剤はゼップバウンドは 週1回の皮下注射で投与されるため、注射部位に関連する副作用が発生する可能性があります。
- 紅斑・腫脹
- そう痒感・疼痛など
3-4. 基本的な注意事項
3-4-1. 用法上の注意事項
ゼップバウンドは 決められた曜日に毎週1回使用する必要があります。
- 使用を忘れた場合の対応
- 次回予定日まで72時間以上空いている場合:気づいた時点で速やかに使用してください。
- 次回予定日まで72時間未満の場合:使用は控え、その週の投与は飛ばしてください。
- 次回以降の使用について
- 前の週に投与を忘れたかどうかに関わらず、次回はあらかじめ決めた曜日に再開してください。
3-4-2. 重要な基本注意事項
ゼップバウンドは 肥満治療の補助療法 として位置づけられており、運動療法・食事療法の継続が必須 です。薬剤のみで十分な効果を得ることは至難であると言えます。
本剤による肥満改善効果は、あくまで補助的なものであると位置づけ、投与中も運動療法・食事療法を継続する必要があります。本剤を3〜4ヶ月投与しても改善が見られなかった場合、または改善傾向があった際もその後効果が不十分と医師が判断した場合は、使用を中止しなくてはいけません。
4. 保険適用時の患者負担
ゼップバウンドは、副作用の軽減と体の順応を考慮し、2.5mgから開始し、2.5mgずつ増量する4段階(最大用量の場合は6段階)を経て、最終的に有効治療用量の10mg(最大用量15mg)を維持するスケジュールで投与されます。
以下は 医療機関での窓口負担が3割の場合の薬剤費の目安であり、1ヶ月(4本分)あたりの負担額 を記載しています
| 用量 | 薬価(円) | 3割負担(円/本) | 1ヶ月負担(円) |
|---|---|---|---|
| 2.5mg | 3,067 | 920 | 3,680 |
| 5mg | 5,797 | 1,739 | 6,956 |
| 7.5mg | 7,721 | 2,163 | 9,265 |
| 10mg | 8,999 | 2,700 | 10,800 |
| 12.5mg | 10,180 | 3,054 | 12,216 |
| 15mg | 11,009 | 3,303 | 13,212 |
上記の目安は、あくまで薬のみの負担分であるため、本来は病院で診察料など、薬局では薬剤調整料他も上乗せされるため、さらにかかることになります。
さらに、2026年4月まで、新医薬品の処方日数制限 により、原則 2週間分(2本)ずつの処方となると思われます。よって、通常よりも医療機関の受診回数が増え、診察料・調剤料の負担が増加してしまいます。
5. ゼップバウンドを処方できる医療機関
5-1. 処方できる医療機関の条件
ゼップバウンドの処方可能な医療機関については、現時点での情報やウゴービの事例を踏まえると、ほぼ同様の厳しい条件が課される可能性が高いと考えられます。具体的には、以下のような条件を満たす医療機関でのみ処方が可能になると予想されます。
- 日本糖尿病学会、日本内分泌学会、日本循環器学会の教育研修施設であること
- 各学会のいずれかにより教育研修施設として認定された施設であること
- 専門資格を持つ医師が常勤していること
このため、ゼップバウンドを処方できる医療機関は、主に大学病院や大規模な基幹病院に限られると考えられます。
5-2. 自由診療での取り扱い
ゼップバウンドは、基本的に厳格な条件を満たした医療機関のみで処方可能な保険適用薬ですが、極一部では自由診療としての利用も想定されています。
しかしながら、厚生労働省はガイドラインを逸脱した使用については厳しく監視していく方針を明言しており、適正使用が確認できない施設には注意喚起が行われることになっています。あくまで医療機関側に対して制度に則った管理体制の徹底が求められている状況です。
一方で、日本医師会は「自由診療も含め、国民全体の薬に対するリテラシー向上が重要」と指摘しており、患者側にも正しい理解と判断力が必要であるという立場です。
つまり、ゼップバウンドは自由診療であっても“好きなように使える薬”ではないという点を理解することが大切です。効果が期待される一方で、適切な医療判断を欠いた使用は、健康被害や不適切な費用負担につながるリスクもあります。
6. さいごに 〜個人的見解
以下は、「ウゴービ」での記事でも同様の内容を記載しましたが、その考えは今も変わっていません。
ゼップバウンドの登場により、肥満症治療に新たな選択肢が加わったことは間違いありません。しかしその一方で、安全性の確保や適正使用の徹底、そして保険財政への影響といった課題も確かに存在します。
とはいえ、肥満は単なる「見た目」の問題ではなく、放置すれば糖尿病や心血管疾患、腎障害など多くの合併症を引き起こす疾患の引き金となります。特に透析に至った場合、その後の医療費負担は莫大であり、社会全体の医療費圧迫につながることも忘れてはなりません。
こうした背景を踏まえると、厳格な条件に基づいた運用が必要である一方で、早期介入や重症化予防という観点から、一定の柔軟性をもった使用方針があってもよいのではないかと、個人的には感じています。
もちろん、拙速な自由診療の拡大や誤用は避けるべきです。しかし、「保険を守るための制限」ばかりに目を向けるのではなく、長期的に見た社会的コストの削減という視点からも、慎重かつ前向きな議論が進むことを期待しています。

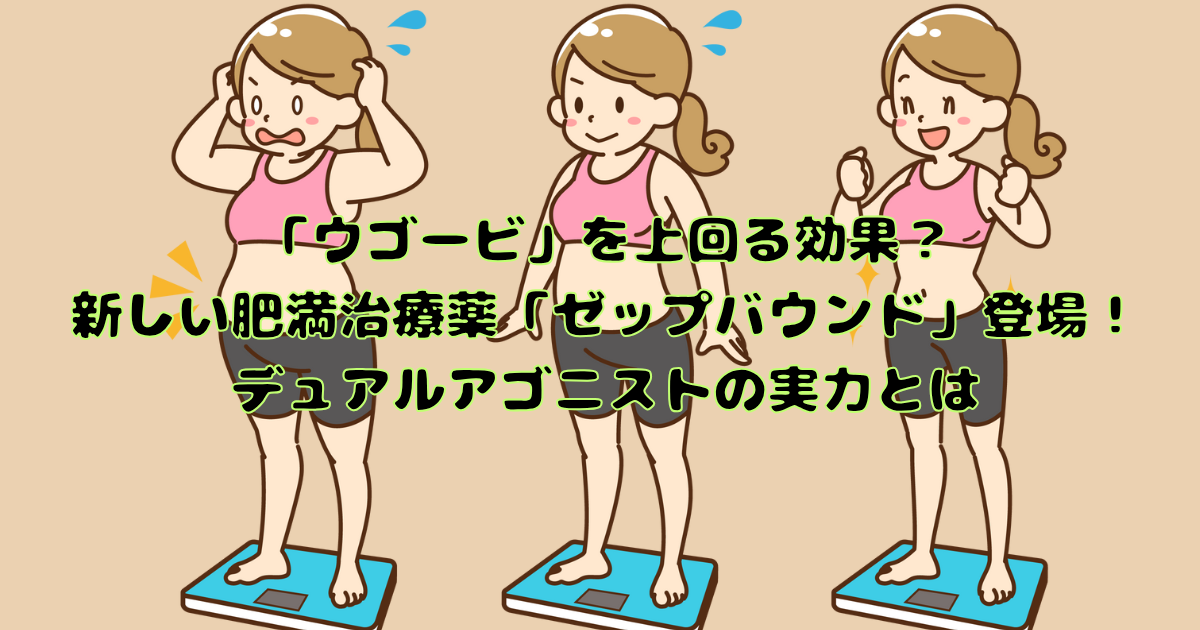


コメント