1. 増え続ける認知症患者
1-1. 認知症は誰にとっても身近な問題
日本では高齢化が進み、認知症は多くの家庭にとって避けられない課題となっています。認知症は、記憶や判断力の低下により日常生活に支障をきたす症状を指し、高齢者に多く見られます。
また、近年では65歳未満で発症する若年性アルツハイマー病も注目されています。厚生労働省の推計では、日本の若年性認知症の患者数は約3.7万人とされ、その中でもアルツハイマー型が最も多いと報告されています。働き盛りの世代での発症は、本人だけでなく家族や職場にも大きな影響を与えるため、早期の診断と適切な支援が重要です。
しかし、適切な知識と対処法を身につけることで、本人や家族の負担を軽減することが可能です。
1-2. 高齢化とともに増える認知症の患者数
厚生労働省のデータによれば、高齢者人口の増加に伴い、認知症の患者数も増加傾向にあります。2025年には65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症になると予測されています。このような状況を受け、政府は2024年1月に「認知症基本法」を施行し、認知症施策推進基本計画を策定しました。この計画では、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らせる社会の実現を目指しています。
2. 認知症とは?
2-1. 認知症の概要
認知症とは、さまざまな疾患や障害が原因で、記憶、思考、判断、言語理解、行動などの認知機能が持続的に低下し、日常生活に支障をきたす状態を指します。かつては「老化によるもの忘れ」と混同されがちでしたが、認知症は明確な疾患であり、加齢とは異なる病的な状態です。
認知症の要因としては大きく2つに分かれ、ある原因で徐々に脳の細胞が死んでいくことで起こる変性疾患と、脳梗塞などの脳の障害により、脳の神経細胞に酸素や栄養が行き渡らず脳の細胞が死んでいく脳血管性があります。
2-2. 主な認知症の種類
認知症にはいくつかのタイプがありますが、日本における三大認知症、それに前頭側頭型を加えた計4種類を紹介します。各々原因について推定はされていますが、いずれもまだ詳細なものはまだ判明していないのが現状です。
(1) アルツハイマー型認知症(約65〜70%)
日本で最も多い認知症で、高齢者に限らず、若年性認知症でも最多を占めます。
- 原因:アミロイドβの異常な蓄積による神経細胞の障害。後期にはタウ蛋白の蓄積も関与。
- 主な症状:記憶障害(特に新しいこと)、時間や場所の見当識障害、判断力の低下など。
- 特徴:緩やかに進行し、症状が少しずつ悪化。初期症状が「もの忘れ」であることが多い。
(2) 血管性認知症(約20%)
脳血管障害に起因する認知症の総称で、アルツハイマー型に次いで多くみられます。
- 原因:脳梗塞や脳出血などによる脳の血流障害。
- 主な症状:遂行機能障害(計画・段取り・判断などの困難)、抑うつ傾向、感情のコントロール困難。
- 特徴:症状が段階的に進行しやすく、発症した部位により症状が異なる。「まだら認知症」とも呼ばれることがある。記憶障害は比較的軽度。
(3) レビー小体型認知症(約5〜10%)
パーキンソン病との関連が深く、幻視などの精神症状が初期から現れやすい認知症です。
- 原因:レビー小体(α-シヌクレイン)という異常なたんぱく質が神経細胞内に蓄積。
- 主な症状:幻視、パーキンソン症状、注意力の変動、レム睡眠行動障害。
- 特徴:認知機能の変動が大きく、特に日内変動(時間帯によって症状が異なる)が顕著。男性に多い傾向があり。
(4) 前頭側頭型認知症(約1%)
日本では比較的稀なタイプの認知症ですが、若年発症が多く、行動や性格の変化が特徴的です。
- 原因:前頭葉や側頭葉における神経細胞の変性。
- 主な症状:共感性の欠如、反社会的行動、過食などの衝動行動。記憶障害は初期には目立たない。
- 特徴:人格の変化が著しく、家庭や職場での問題がきっかけで受診に至ることが多い。欧米では比較的多く報告されている。
認知症の種類によって症状や進行の仕方が異なるため、適切な診断と対応が重要です。
次のセクションでは、認知症の新たな治療法として注目される「ケサンラ」について詳しく解説していきます。
3. ケサンラの概要
ケサンラ®︎(成分名ドナネマブ)は、2024年9月に国内で製造販売承認を取得し、同年11月に発売された、レケンビ®︎(レカネマブ)と類似した作用機序を持つ早期アルツハイマー型認知症に対する点滴静注による抗アミロイドβ抗体薬です。
3-1. 作用機序
ケサンラは、脳内に蓄積された有害な物質「アミロイドβプラーク」に特異的に結びつきます。これにより、免疫細胞の一種である「ミクログリア」を活性化させ、アミロイドβプラークを排除する働きが促進されます。簡単に言うと、脳内に溜まった「ゴミ」が認知症の進行に関与1しているとされ、その除去を助けることで症状の進行を遅らせることが期待されます。
3-2. 効能効果
ケサンラの効能効果として、アルツハイマー型認知症による軽度認知障害(MCI)および軽度の認知症の進行抑制が挙げられます。これは、ドネペジルなどの従来の認知症治療薬と同様に、認知機能の低下を遅らせる効果を持つことを示しています。
ただし、ケサンラは従来の認知症治療薬同様、軽度の症状に対して効果を発揮し、中等度以上の進行した状態には適応外であることに注意が必要です。
それゆえに、早期発見と早期治療開始の重要性が強調される部分であり、症状が軽度な段階での介入が、治療効果を最大化するために重要です。
3-3. 用法用量
ドナネマブの投与は、以下のスケジュールで行われ、1回の静注には少なくても30分かける必要があります。
- 初回から3回目まで:700mgを4週間隔で点滴静注
- 4回目以降:1400mgを4週間隔で点滴静注
このように、最初の3回を半量の700mgで開始する理由は、抗体製剤の投与によって伴う有害反応(infusion reaction※)を軽減するためと考えられます。
※infusion reactionとは?
インフュージョンリアクションとは、点滴で投与される抗体製剤に対して体が過剰に反応し、一時的に発熱や血圧変動、悪寒などの症状を示す現象です。アレルギー反応に似ていますが、免疫系が関与するアレルギーとは異なり、投与初期に起こりやすいことが特徴です。薬剤の投与中から1時間以内に起きやすいですが、2回目以降の投与で起きやすいIgEを介さないタイプや、1週間後に発症する非即時型などがあるため、継続的な注意が必要になります。
3-4. 臨床効果
ケサンラを18ヶ月投与すると、以下の効果が得られることが示されています。
- 認知機能の低下を約29%抑制
- 病状の進行を約5.4ヶ月遅延
これにより、認知症の初期段階で治療を開始することで、軽度の認知障害の期間を延ばすことが可能であると考えられます。
3-5. 副作用
ケサンラには、以下の2つの主な重篤な副作用があります。これらは、特に治療初期に発生する可能性があり、適切なモニタリングが必要です。
- インフュージョンリアクション(Infusion Reaction)
投与時に発生する可能性があるアレルギー反応で、発疹、発熱、寒気、頭痛などが含まれます。これらは一般的に初回投与後に発生することが多いですが、2回目以降に起こるIgEを介さないタイプ、1週間ほどして起こる非即時型タイプなどもあるため、継続した注意が必要です。また、反応が軽度であれば投与の続行が可能です。ただし、重篤な反応が見られる場合は、治療を一時中断または調整することがあります。 - ARIA(アミロイド関連画像異常)
ケサンラによる治療中に、脳の画像で見られる異常であるARIAが発生することがあります。ARIAには、浮腫(ARIA-E)と微小出血(ARIA-H)の2タイプがあります。ARIAは、アミロイドβの除去過程で脳内の血管に影響を与えるため、特に治療初期にリスクが高いです。ARIAの発生が確認された場合、定期的なMRIでのモニタリングが推奨され、症状に応じて治療計画の調整が行われます。
重大な副作用として、アナフィラキシーショックや脳出血が報告されています。これらは一般的な薬剤と比較して発生率が高いとされており、特にARIAに伴う脳出血には注意が必要です。
また、軽度な副作用として胃腸障害(吐き気、下痢など)や頭痛が挙げられます。これらは一時的なものであることが多いものの、症状が持続または悪化する場合には医師に相談が必要です。
3-6. 併用を注意すべき薬
ケサンラには、併用してはいけない薬(併用禁忌薬)は特に設定されていません。
しかし、重大な副作用として脳出血のリスクがあるため、抗凝固薬や抗血小板薬の併用には注意が必要です。 具体的には、以下の薬剤と併用すると脳出血リスクが増加する可能性があります。
- 抗凝固薬(ワルファリン、ダビガトラン、リバーロキサバン、アピキサバン など)
- 抗血小板薬(低用量アスピリン、クロピドグレル、プラスグレル など)
3-7. その他注意事項
3-7-1. 用法用量における注意事項
(1) ケサンラの投与中に、原因物質とされるアミロイドβプラークの除去が確認された場合は、その時点で治療を終了します。
また、完全に除去されなかった場合でも、原則として投与期間は最長18ヶ月までとされています。アミロイドβプラークの除去状況の評価は、投与開始から12ヶ月後を目安に行われます。
(2) MRI検査にて重度のARIA-E(脳浮腫)やARIA-H(微小出血・表層血腫)、または脳出血が認められた場合は、投与を中断または中止する必要があります。
その後、症状が安定したことが確認されれば、投与を再開できる場合もあります。
3-7-2. 重要な基本的事項
ケサンラの投与に伴い、インフュージョンリアクション(infusion reaction)やアナフィラキシーショックなどの重篤な有害事象が発現することがあります。
これらは特に点滴投与直後から早期に発現する傾向があるため、投与後少なくとも30分間は、患者の状態を十分に観察する必要があります。
4. 類似薬レケンビ®︎(レカネマブ)との違い
アルツハイマー型認知症の原因の一つと推定されている「アミロイドβ」に関与する薬として、2023年12月にレカネマブが発売されています。
| ケサンラ | レケンビ | |
|---|---|---|
| 成分名 | ドナネマブ | レカネマブ |
| 作用機序 | アミロイドβの一種である『ピログルタミル化アミロイドβ』に結合し、主に既に蓄積したアミロイドβプラークを減らす | アミロイドβがプラークとして固まる前の『アミロイドβプロトフィブリル』に結合し、除去することで蓄積を防ぐ |
| 投与間隔 | 2週間に1回 | 4週間に1回 |
| 時間/回 | 1時間 | 少なくても30分間 |
| 投与期間 | 最長18ヶ月まで (12ヶ月の時点でアミロイドβプラークが除去されたと判断されれば終了) | 原則として18ヶ月 |
| 費用 | 308万円 | 298万円2 |
両者を比較すると、治療効果や副作用の頻度、自己負担額といった面では、大きな差はないと考えられます。
一方で、明確な違いが見られるのは「投与期間」と「1回あたりの点滴時間」です。ケサンラはレカネマブ(レケンビ®)と比べて、投与回数が半分程度で済み、最終的な治療期間も短縮される可能性があるため、患者さんの通院負担を大きく軽減できる点が注目されます。
特に、高齢患者や通院に制約のあるケースでは、ケサンラの利便性が強みになるかもしれません。
5. ケサンラの課題と展望
5-1. 費用の問題
ケサンラの薬価は1瓶あたり66,948円で、年間費用は約308万円に設定されています。これは既存のアルツハイマー型認知症治療薬と比較して非常に高額であり、患者やその家族にとって経済的負担となる可能性があります。加えて、健康保険制度への影響も懸念されており、今後の費用対効果の評価や公的助成の在り方が議論される可能性があります。
5-2. 投与できる施設の限られた状況
ケサンラの投与には、アミロイドPET、MRIなどの適切な検査及び管理が実施可能な医療施設での投与が求められます。また、これらの検査を実施できる施設または連携可能な施設での投与が必要です。そのため、アルツハイマー病の病態や治療に関する十分な知識と経験を持つ医師が、患者に適切な管理と説明を行える施設でのみ投与が行われるべきです。これにより、ケサンラのリスクを適切に管理し、安全に使用するための体制が整えられます。
投与に際しては、専門的な医療機関や体制の整備が必要となるため、施設や医師の確保が重要な課題となります。
5-3. 今後の研究や改良の可能性
ケサンラを含む抗アミロイドβ抗体は、アルツハイマー病の進行抑制を目的とした治療薬として注目されていますが、以下のような点が今後の研究課題となります。
- ARIAの発生リスクを低減する改良(副作用の軽減)
- より簡便な投与方法の開発(例:皮下注製剤)
- タウタンパク質を標的とする治療との併用(相乗効果の検討)
また、他の治療法との組み合わせによる相乗効果についても研究が進められており、今後の治療戦略の多様化が期待されます。
5-4. 現在の治療薬は“進行抑制”、根治はまだ先
現在、アルツハイマー型認知症などに使用されている薬剤には、アセチルコリンエステラーゼ阻害薬(ドネペジルなど)、NMDA受容体拮抗薬(メマンチン)、そして近年登場した抗アミロイドβ抗体薬(レカネマブ、ドナネマブ)があります。
これらはいずれも、軽度から中等度の認知症の進行をある程度遅らせることは期待されるものの、根本的な原因を取り除く“根治療法”ではありません。既存薬では、すでに始まっている神経変性や認知機能の低下を完全に停止または逆転させる治療法は、現時点では確立されていません。
したがって、まだ今後高齢者が増え続ける日本においては特に、原因物質をはっきり断定させ、発症予防あるいはより早期の段階での病態進行を根本から抑制する治療法の開発が待たれるところです。



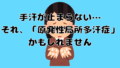
コメント