1. 過眠症とは?
1-1. 過眠症とは?
過眠症(Hypersomnia)は、適切な睡眠時間を確保しているにもかかわらず、日中に強い眠気を感じる疾患です。単なる「寝不足」や「疲れ」の問題ではなく、脳の覚醒システムや睡眠リズムの異常が関与していると考えられています。
過眠症は、単独で発症する「特発性過眠症」のほか、「ナルコレプシー」「クライネ・レビン症候群」などの特定の疾患群に分類されます。また、うつ病や睡眠時無呼吸症候群などの別の疾患に伴う「二次性過眠症」も存在し、診断には慎重な評価が必要です。
1-2. 過眠症を正しく理解する重要性
過眠症は、日常生活に影響を及ぼすだけでなく、放置すると精神的・身体的な健康問題を悪化させる可能性があります。しかし、一般には「怠け」や「自己管理の問題」と誤解されがちで、適切な診断や治療につながらないケースも少なくありません。
また、年代ごとに必要な睡眠時間が異なることを理解しないまま「睡眠不足の影響」と「過眠症」を混同することも問題です。特に小児・若年層では、理想的な睡眠時間を確保していないために日中の眠気を引き起こしている場合があり、治療の前に睡眠習慣の見直しが必要となるケースもあります。
本記事では、過眠症の種類、原因、診断、治療について科学的根拠に基づいて解説し、適切な理解と対応につなげることを目的としています。
2. 適正の睡眠時間とその重要性
2-1. 先進国中で特に不足している日本人の良質な睡眠
日本人の平均睡眠時間は先進国の中でも短いとされています。OECD(経済協力開発機構)の2021年の調査によると、日本の平均睡眠時間は7時間22分であり、加盟国の中で最も短い水準でした。特に、働き盛りの30〜50代では6時間未満の睡眠が一般的になっており、約3割の人が「睡眠による休養が十分に取れていない」と感じているというデータもあります(厚生労働省「健康日本21」より)。
その背景には、長時間労働・通勤時間の長さ・夜更かし習慣などが関係しており、多くの日本人が「慢性的な睡眠不足」に陥っています。結果として、知らず知らずのうちに睡眠負債を抱え、日中の強い眠気を感じるようになります。 こうした慢性的な睡眠負債の蓄積は、過眠症のリスクを高める要因の一つと考えられています。
2-2. 適正な睡眠時間
厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド2023」によると、年代によって理想的な睡眠時間は異なります。特に成長期の子どもは長めの睡眠が推奨されており、成人以降は6時間以上の睡眠が推奨されています。
| 年齢層 | 適正な睡眠時間 |
|---|---|
| 1~2歳 | 11~14時間 |
| 3~5歳 | 10~13時間 |
| 6~12歳 | 9~12時間 |
| 13~18歳 | 8~10時間 |
| 18歳以上 | 6時間以上 |
| 65歳以上 | 床上時間が8時間以上にならないことが推奨 |
年齢ごとの推奨睡眠時間は目安であり、実際には個人差があるとされています。必要な睡眠時間は遺伝や生活習慣、健康状態によって異なり、同じ年齢でも最適な睡眠時間は人それぞれです。そのため、「〇時間眠れば十分」と一律に考えるのではなく、自分にとって最適な睡眠時間を見つけ、質の良い睡眠を確保することが大切です。
2-3. 睡眠負債のリスク
一時的な睡眠不足であれば、多少の集中力低下や倦怠感を感じる程度で済むことが多いですが、それが慢性的に続くと、心身に深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。このように、睡眠不足が蓄積し、健康や生活の質に影響を与える状態を「睡眠負債」と呼びます。これは借金と同様に、蓄積すればするほど返済(=回復)が難しくなり、簡単に取り戻せるものではありません。以下代表的な悪影響の例を挙げていきます。
- 認知機能の低下:集中力・記憶力が低下し、学業や仕事のパフォーマンスが悪化。
- 免疫力の低下:風邪やインフルエンザにかかりやすくなる。
- 精神的な影響:不安や抑うつのリスクが上昇。
- 生活習慣病のリスク増加:糖尿病・高血圧・心疾患の発症率が上がる
特に、休日の「寝だめ」によって睡眠負債を解消しようとする人が多いですが、睡眠リズムを乱し、かえって体内時計のバランスを崩す原因となることがあります。そのため、睡眠負債は計画的な改善が必要であり、長期的に適切な睡眠習慣を確立することが重要です。
また、過眠症の診断前に、そもそも理想的な睡眠時間を確保できているかを確認することが重要です。例えば、「過眠症だと思っていたが、実際には慢性的な睡眠不足だった」というケースも多く、適切な睡眠習慣の見直しが先決となることがあります。
3. 過眠症の種類と特徴
過眠症には、脳内の覚醒機能の異常が関与するものや、他の疾患が原因となるものなど、複数のタイプが存在します。それぞれの過眠症を正しく理解し、適切な対策を講じることが重要です。本章では、代表的な過眠症の種類について解説します。
まず、その前に代表的な過眠症における検査を2つ紹介します。
- 終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG):検査睡眠中の脳波、筋肉の動き、眼球運動、呼吸パターンを記録し、睡眠の質や異常を評価します。さらに、反復睡眠潜時検査と組み合わせることでより正確な診断が可能になります。
- 反復睡眠潜時検査(MSLT):この検査は、特別な刺激がない静かな環境で、どのくらい簡単に眠れるか、レム睡眠にどれだけ早く入るかを客観的に評価するものです[1]。通常は、PSGを前夜に行い、続けてMSLTが実施されます。ガイドラインでも広く使われており、現在もナルコレプシーの診断に利用されています。
3-1. ナルコレプシー
3-1-1. ナルコレプシーとは
ナルコレプシーは、発作的に強い眠気や居眠りが繰り返し生じる疾患であり、少なくとも3ヶ月以上継続したものを指します。この眠気は非常に強く、通常では考えられない状況でも耐えがたい眠気に襲われることが特徴です。たとえば、危険な作業中や重要なプレゼンの最中であっても、本人の自覚がなく急に眠り込んでしまうことがあります。
代表的な症状として、情動脱力発作(カタプレキシー)があります。この発作は、笑いや怒り、喜びなどの感情によって誘発され、一時的に体の筋緊張が低下します。場合によっては転倒し、大きな怪我につながる恐れもあるため、対策が必要です。
また、付随症状として、レム睡眠に関連した金縛りのような状態に陥る「睡眠麻痺」や、就寝直後に恐ろしい幻覚を体験する「入眠時幻覚」などがみられることがあります。
また、ナルコレプシーには以下の2種類があります。
- 1型:オレキシンの値が低く、情動脱力発作が伴う場合
- 2型:オレキシンはほぼ正常であり、情動脱力発作が伴わない場合
3-1-2. ナルコレプシーの原因
ナルコレプシーの主な原因は、オレキシンという覚醒を促す神経伝達物質の欠乏です。オレキシンは、脳の視床下部で分泌され、睡眠と覚醒を調整する役割を担っています。この物質の欠乏により、覚醒と睡眠の調整が乱れ、日中に強い眠気を感じるようになります。また、現在の研究では遺伝的要因や環境因子も関与している可能性が示唆されています。
3-1-3. ナルコレプシーの診断
臨床的には、日中の強い眠気に加え、睡眠発作と情動脱力発作が確認されれば、1型ナルコレプシーと診断します。
一方、情動脱力発作を伴わない2型ナルコレプシーの診断には、反復睡眠潜時検査(MSLT)が必要です。MSLTにおいて平均睡眠潜時が8分以下であり、かつ2回以上のSOREMP(入眠後15分以内にレム睡眠へ移行する現象)が確認されることが診断基準となります。
また、1型ナルコレプシーでは、脳脊髄液中のオレキシン濃度が著しく低下しているため、この所見のみで診断可能です。しかし、オレキシン測定を実施できる医療機関が限られているため、現時点では標準的な診断法として普及していません。
3-2. 特発性過眠症
3-2-1. 特発性過眠症とは
特発性過眠症は、代表的な過眠症の一つであり、慢性的な過眠や日中の眠気が持続することが特徴です。ナルコレプシーと比較すると、眠気の強さはやや穏やかであり、突然の睡眠発作は少ないとされています。しかし、一度眠りにつくと長時間の睡眠を必要とする傾向があり、無理に目覚めさせようとすると、一時的に時間や場所、人物の認識が曖昧になる『見当識障害』が生じることがあります。
また、日中に仮眠をとっても眠気が十分に解消されないことが特徴です。ナルコレプシーと異なり、ほとんどカタプレキシー(情動脱力発作)を伴なわず、夜間の睡眠が長時間になることが多くなります。
3-2-2. 特発性過眠症の原因
特発性過眠症は、その名称の通り、現時点では明確な原因が解明されていません。しかし、近年の研究により、睡眠・覚醒の調節に関与するオレキシン系の異常が示唆されており、特定の発症リスク遺伝子も発見されています。そのため、ナルコレプシーと同様に、オレキシン作動薬が治療に有効である可能性があるとされています。
3-2-3. 特発性過眠症の診断
若年層において発症し、日中の強い眠気がある患者において、ナルコレプシーや閉塞性睡眠時無呼吸症候群などの他の睡眠障害を除外することが重要です。ナルコレプシーとの区別にはよくMSLTが用いられ、SOREMPが2回未満であることが基準となります。さらに、カタプレキシーの有無や、激しいいびきがみられないことを確認することが診断のポイントとなります。
3-3. クライネ・レビン症候群
クライネ・レビン症候群は、非常に稀な過眠症の一種で、有病率は100万人に数人とされています。典型的には、昼夜問わず過眠症状が反復し、その間に正常な状態が長期間続くことが特徴です。このような症状の変動を繰り返すため、反復性過眠症とも呼ばれています。
クライネ・レビン症候群の症状は、過眠状態が多くは1~2週間続き、その際に認知機能の異常や鬱を伴う場合もあり、その後は数ヶ月にわたり症状が解消される正常な期間が訪れます。このサイクルが、患者によっては10数年以上にわたって繰り返されることがあります。症状の出現には突発的な発症やストレスが関与する場合もありますが、原因は依然として不明とされています。
4. 過眠の要因と鑑別
以下のフローチャートでは、それぞれの項目に該当しない場合は次のステップ(下方向)へ進み、該当する場合は適切な評価やその疾病に対する診断や治療を行います。
- 薬物使用の影響(睡眠導入剤、抗ヒスタミン薬、向精神薬など)
⇨代替薬や薬の減量、中止をし睡眠を再評価
↓ - 精神疾患
⇨抑うつ、季節性感情障害
↓ - 夜間の睡眠が十分取れず、適切な睡眠を取ると日中の眠気が排除
⇨睡眠不足症候群、ロングスリーパー
↓ - いびき、不規則な呼吸、肥満など
⇨睡眠関連呼吸障害(睡眠時無呼吸症候群など)
↓ - 情動脱力発作、睡眠麻痺、入眠時幻覚
⇨ナルコレプシー(情動脱力発作が伴えば1型、なければ2型)
↓ - 入眠時や睡眠中の下肢不随意運動
⇨レストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)、周期性四肢運動障害
↓ - 月経周期との関連性
⇨月経随伴睡眠障害
↓ - 周期的な過眠
⇨クライネ・レビン症候群(反復性過眠症)
↓ - 適切な時間帯の眠気、睡眠時間帯の後退
⇨概日リズム睡眠・覚醒障害
↓ - 特発性過眠症や原因不明の過眠症
上記のフローチャートは睡眠障害の治療ガイドライン[2]を参照しています。これらを参照すれば、かなりおおまかに原因(疾病)を把握しやすくなるでしょう。
5. 過眠症の原因と多面的なアプローチ
過眠症の原因は単一ではなく、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。睡眠時無呼吸症候群(SAS)や内分泌異常、精神疾患、生活習慣など、多くの因子が日中の過剰な眠気(EDS: excessive daytime sleepiness)を引き起こします。そのため、過眠症の診断と治療においては、多面的なアプローチが不可欠です。
本章では、過眠症の主な原因となる疾患や生活習慣について解説し、どのようにして原因を特定し、適切な対応を取るべきかについて説明します。
5-1. 睡眠時無呼吸症候群(SAS)と過眠症の関係
睡眠時無呼吸症候群(SAS: Sleep Apnea Syndrome) は、睡眠中に呼吸が一時的に停止または低下することで、頻繁に睡眠が中断される疾患です。最も一般的なタイプである閉塞性睡眠時無呼吸症(OSAS: Obstructive Sleep Apnea Syndrome) では、気道の閉塞により換気が妨げられます。もう一つのタイプである中枢性睡眠時無呼吸(CSA: Central Sleep Apnea) は、脳の呼吸中枢の異常により無呼吸が生じます。
SASでは、一晩の睡眠中に何度も呼吸が止まり、そのたびに脳が覚醒を繰り返すため、深い睡眠が妨げられ、結果として日中の強い眠気が生じます。そのため、過眠の原因を評価する際には、SASの可能性を常に考慮する必要があります。
5-2. その他の身体的要因と過眠症
過眠症の原因は多岐にわたり、SAS以外にもさまざまな身体的要因が関与します。これらの要因を適切に評価し、過眠の根本的な原因を特定することが重要です。
5-2-1. 神経・脳の疾患
- 頭部外傷・脳損傷:頭部外傷後に日中の過度な眠気(EDS)が持続することがあります。特に、外傷性脳損傷(TBI)は、睡眠リズムの乱れやナルコレプシー様の症状を引き起こすことがあります。
- 脳血管障害(脳卒中など):脳の睡眠中枢にダメージが及ぶことで、睡眠覚醒リズムが崩れることがあります。また、脳卒中などがOSASを引き起こし、間接的に日中の過度を引き起こしやすくします。
- 神経変性疾患:パーキンソン病、多発性硬化症(MS)、アルツハイマー病などでは、睡眠・覚醒リズムの異常が見られ、過眠を伴うことがあります。
- 筋強直性ジストロフィー:難治性疾患であり、筋強直や筋萎縮を主徴とする神経筋疾患です。さらに、中枢神経系の障害や認知機能の低下がみられることがあり、これらが過眠を引き起こす要因となることも報告されています。
5-2-2. 内分泌・代謝疾患
- 甲状腺機能低下症:甲状腺ホルモンの不足により、全身の代謝が低下し、強い倦怠感や日中の眠気が現れることがあります。
- 糖尿病・インスリン抵抗性:血糖コントロールの異常により、日中の眠気や疲労感が増すことがあります。
- 副腎皮質機能低下症(アジソン病):副腎皮質ホルモンの不足により、低血圧や倦怠感とともに過眠症状が現れることがあります。アジソン病は、斑点などの色素沈着が特徴的です。
5-2-3. その他の身体的要因
- 慢性疼痛疾患:線維筋痛症などの慢性的な痛みを伴う疾患では、睡眠の質が低下し、日中の眠気が強くなることがあります。
- 貧血:酸素供給が低下することにより、全身の倦怠感や眠気を引き起こすことがあります。
6. 過眠症の治療法
過眠症には現在のところ根本的な治療法は確立されていません。しかし、適切な治療によって症状を軽減し、社会生活への影響を最小限に抑えることは可能です。治療は、薬物療法・生活習慣の改善・認知行動療法などを組み合わせ、個々の患者に最適なアプローチを選択することが重要となります。
6-1. 非薬物療法
6-1-1. 疾病の受容
過眠症の治療は、まず疾患を正しく理解し、受け入れることから始まります。過眠症の患者は、周囲から「怠けている」「だらしない」と誤解されやすく、それが自己否定的な感情につながることもあります。しかし、眠気は疾患によるものであり、本人の努力では制御しきれないものです。
そのため、患者自身が過眠症を受け入れ、かつ周囲の理解を得ることで、無理なく症状と向き合いやすくなります。眠気をコントロールする方法を学び、前向きな姿勢で治療に取り組むことが、社会生活を維持するうえでの鍵となります。
6-1-2. 睡眠日誌
入眠や起床時間、睡眠の質などを記録することは、「自分の睡眠を管理できている」という意識を高めるうえで重要です。睡眠日誌をつけることで、睡眠不足が続いているのか、無意識のうちに夜更かししているのかを客観的に把握でき、治療の指標として役立ちます。また、医師との診察時に具体的な睡眠パターンを共有できるため、より適切な治療計画を立てることが可能になります。
6-1-3. 生活習慣の改善
過眠症の治療において、まず適切な睡眠習慣を確立することが基本となります。睡眠不足による過眠と鑑別するためにも、生活習慣の見直しは診断の前提として不可欠です。
- 夜間睡眠と生活リズムの確立
夜間に十分な睡眠を確保し、規則正しい睡眠リズムを維持することで、概日リズム(体内時計)の調整を促します。特に就寝・起床時間を一定に保つことが重要です。 - 計画的仮眠の活用
特にナルコレプシー患者においては、昼休みなどに短時間(10〜15分程度)の仮眠をとることで、午後の眠気の軽減に有効とされています。また可能であるのであれば、数時間ごとの計画的な仮眠も推奨される場合があります。 - カフェイン摂取の調整
カフェインは覚醒作用があり、適切に利用すれば日中の眠気対策に役立ちます。特にカフェイン不耐性や感受性が高くない限りは、日中の適量摂取が可能です。ただし、夕方以降の摂取は夜間の睡眠に影響を及ぼす可能性があるため、控えることが推奨されます。
6-2. 薬物療法
過眠症の治療では、まず原因を特定し、それに対処することが最優先となります。加えて、睡眠環境の改善や生活習慣の見直しを行うことが基本です。しかし、それでもなお日中の過度な眠気により日常生活に支障をきたす場合には、薬物療法が必要となることがあります。
6-2-1. 中枢性過眠症関連の薬物治療
(1) モダフィニル(モディオダール®︎)
モダフィニルは、日本において2007年に販売が開始され、現在、過眠症治療の第一選択薬とされています。従来の中枢神経刺激薬と比較して、効果の持続時間が長く、覚醒作用が比較的穏やかでありながら依存性が少ないことが特徴です。適応症にはナルコレプシー、特発性過眠症、条件付きで閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)が含まれます。主な副作用としては、頭痛、不眠、口渇などが報告されています。
(2) メチルフェニデート(リタリン®︎)
メチルフェニデートは、日本において古くからナルコレプシーの治療に用いられてきた中枢神経刺激薬ですが、長期使用による依存性や乱用の問題が指摘されてきました。近年では、安全性の観点からモダフィニルが第一選択薬とされており、メチルフェニデートの使用は制限されています。本剤を処方できるのはリタリン登録医に限られ、調剤も登録薬局のみで行われるなど、不正使用防止の対策が講じられています。さらに処方に関しては、以下のような厳しい条件も付加されます。
- モダフィニルを耐えうる最大量投与しても、十分な効果が得られない場合
- すでに長期間メチルフェニデートを服用し、他治療薬への切り替えが困難な場合
- 副作用などの問題で、他治療薬を用いることができない場合
(3) ペモリン(ベタナミン®︎)
ペモリン(ベタナミン®)は、メチルフェニデート同様に中枢神経刺激薬であり、ナルコレプシーやその近縁の傾眠疾患に対して使用されます。通常、朝食後と昼食後の2回に分けて経口投与しますが、半減期が長いため、朝1回の投与も可能とされています。
副作用としては、頭痛、ほてり、動悸などの中枢神経刺激による症状が報告されています。特に、肝障害のリスクが指摘されており、重篤な肝障害による死亡例も報告されています。そのため、ペモリンを使用する際は、定期的な肝機能検査が推奨されています。
6-2-2. 情動脱力発作関連の薬物治療
抗うつ薬は、レム睡眠に対して大きな作用を示すとされており、カタプレキシーや入眠時幻覚などの、レム睡眠関連症状に対して用いられることがあります。これらの薬剤の中では、クロミプラミンのみ保険適用が認められています。また連用後に急に薬を中止すると、症状が悪化する可能性もあります。
(1) 三環系抗うつ薬(TCA)
クロミプラミン(アナフラニール®)、イミプラミン(トフラニール®)などが少量で用いられます。長年の臨床経験から、三環系抗うつ薬は最も安定した効果を示すとされていますが、便秘や口渇、起立性低血圧などの副作用が比較的高頻度にみられるため注意が必要です。また、長期間使用すると効果に耐性が生じる可能性があるとも報告されています。
(2) セロトニンなどを介する抗うつ薬
セロトニンを介する抗うつ薬は、三環系抗うつ薬ほど安定した効果は期待しにくいものの、副作用の発現頻度が比較的少なく、使用しやすい薬剤とされています。主に以下の2種類が用いられます。
- セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI):パロキセチン(パキシル®︎)、フルボキサミン(ルボックス®︎・デプロメール®︎)
- セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI):ミルナシプラン(トレドミン®︎)
6-2-3. ナルコレプシーにおける睡眠の分割に対する薬物治療
ナルコレプシー患者においては、夜間の睡眠における問題は入眠障害よりも、睡眠分割すなわち頻繁な途中覚醒の方が関連性が高いとされています。これは、睡眠が断続的に中断されることにより、ノンレム睡眠が少ないことで睡眠の質が低下し、日中の過度な眠気や疲労感を引き起こす原因となります。
そのため、中途覚醒を減少させる目的で、ベンゾジアゼピン系薬剤やその作動薬が使用されることがあります。ただし、超短時間作用型の薬剤は、睡眠維持に不十分であり、逆に長時間作用型薬剤は、翌日の眠気や過度な鎮静作用を引き起こし、日中の眠気や注意力低下の原因となりえます。したがって、短時間型または中間型作用薬(フルニトラゼパムなど)の方が適しているとされています。
【参考資料・文献】

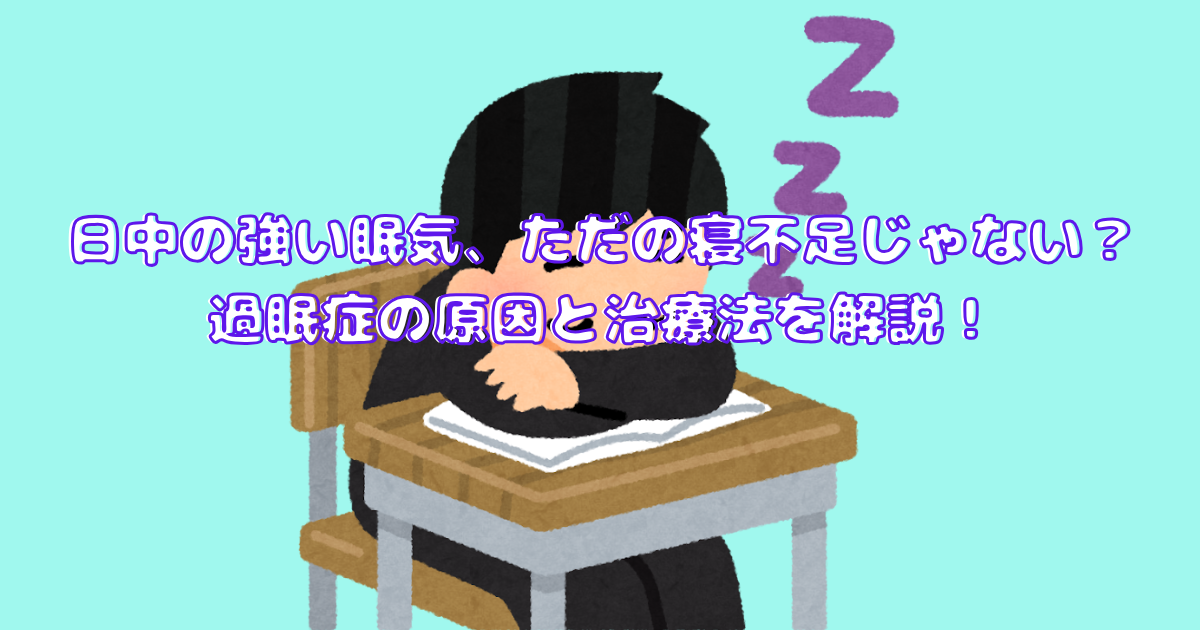


コメント