※当記事にはアフィリエイト広告を含みます。商品リンクを経由して購入された場合、当サイトに収益が発生することがあります。
1. はじめに
寒さが増す季節になると、「風邪の引き始めには葛根湯」というフレーズを耳にすることが多いでしょう。 葛根湯は漢方薬の中でも広く知られており、実際に効果を感じる方も少なくありません。
しかし、葛根湯は“誰にでも効く万能薬”ではありません。 風邪の初期といっても、人によって体力の状態、汗のかき方、冷えやすさなどは異なり、そこに漢方独自の「向き・不向き」が生じます。
多くの人の風邪初期は葛根湯と相性が良いことが多いのも事実ですが、条件から外れると効果が弱まることもあり、場合によっては別の処方が理にかなう場面もあります。
つまり「風邪の引き始め=葛根湯」は、半分は正解であり、半分は誤解だと言えるのです。
本記事では、葛根湯が力を発揮しやすい状況とそうでない状況を整理し、さらに風邪の経過に合わせた“自分に合う漢方風邪薬の選び方”を薬剤師の視点からわかりやすく解説します。
2. 葛根湯とは?
葛根湯は、漢方医学でいう「太陽病1」の初期に用いられる代表的な処方で、風邪を発症してから2〜3日以内の段階で特に効果を発揮します。
一般的には、
- 熱感や悪寒がある
- 頭痛や肩こりを伴う
- 体力はまだ十分にある
- 汗がまだ出ていない
- 発熱に伴い脈がよく触れる(浮脈)状態
といった、風邪の“入口”に最もよく合う処方です。
これらの状態は多くの人が風邪の初期に経験しやすいため、「風邪のひき始め=葛根湯」というイメージが広まっています。ただし、これは“相対的に合う人が多い”というだけで、全員に当てはまるわけではありません。その点については後述します。
2-1. 葛根湯の構成生薬
葛根湯は7つの生薬で構成されており、それぞれが風邪初期の症状に対して明確な役割を担っています。
- 葛根(カッコン):首・肩の緊張をゆるめ、血流を改善。肩こりや後頭部の重さを和らげる中心生薬。
- 麻黄(マオウ):交感神経を刺激し、発汗を促す。悪寒や筋肉の強張りを改善し、処方にスピード感を与える。
- 桂皮(ケイヒ):体を温め、血流を促進。麻黄と協力して寒邪を外へ押し出す。
- 芍薬(シャクヤク):筋肉の緊張を和らげ、痛みを鎮める。頭痛や体のだるさを軽減。
- 生姜(ショウキョウ):胃腸を温め、悪寒や吐き気を改善。主要生薬を裏側から支える補佐役。
- 大棗(タイソウ):胃腸を整え、体力消耗を防ぐ。処方全体のバランスを取る。
- 甘草(カンゾウ):消炎・鎮痛作用を持ち、生薬同士を調和させる。麻黄の刺激性を緩和する調整役
2-2. 葛根湯の感冒に対するメカニズム
葛根湯は、風邪の「ごく初期」に現れる不快な症状──悪寒、肩こり、頭痛、筋肉の強張り──を素早く取り除くことを目的とした処方です。その働きは、漢方的な体表調整作用と、現代医学的に確認されている免疫調節作用の両面から理解できます。
- 体表の緊張をほぐし、血流を回復させる:葛根・麻黄・桂皮が体表のひきつれを緩め、首肩のこわばりや後頭部の重さを改善し、風邪が抜けやすい状態をつくります。
- 発汗を促し、悪寒や寒気を取り除く:麻黄と桂皮が血流を改善し、軽い発汗を促すことで悪寒や筋肉の強張りを和らげます。発汗による体温調整は、風邪の初期に重要な働きです。
- 炎症性メディエーターの過剰産生を抑える:葛根湯の代謝産物は、TNF-αやIL-6など炎症性サイトカインの過剰産生を抑え、免疫反応の暴走を穏やかに鎮めます。これにより、風邪の進行を緩やかにし、回復を早める可能性があります。
- 体力のある人ほど反応が出やすい:葛根湯は基礎代謝が高く、発汗する余力のある人に適しています。体力が落ちている場合は十分な効果が得られにくく、別の処方が望ましいこともあります。
- 麻黄と桂皮の割合が効き目を左右する:麻黄(動かす力)と桂皮(温めて巡らせる力)の比率が高いことが、葛根湯の特徴です。この組み合わせが発汗・血流改善・免疫活性を強く後押しし、結果として、葛根湯 > 小青竜湯 > 麻黄附子細辛湯 > 香蘇散 の順に“外邪を払う力”が強いと理解されます。
2-3. 葛根湯の応用処方
(1)肩こりや頭痛、関節痛、五十肩などの疼痛疾患
主として麻黄が作用によるものです。また芍薬や大棗が協力して痛みを取ります。
(2)気管支喘息、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患
アトピーに対しては、体の内部には水が溜まっているが体の表面は乾燥しているという場合が多いです。それに対し発表作用を利用します。
(3)その他
中耳炎、扁桃炎などの耳鼻科疾患や結膜炎などの眼科疾患等の炎症性疾患、子供の夜尿症や乳汁分泌作用などにも用いられることがあります。
2-4. 葛根湯の服用ポイント
- 対象者で特に重要な点は、自汗がなく軽く触れて分かるほどの脈がある方です。
- なるべく体を温めることが重要なため、水ではなく白湯でゆっくり服用すると効果的です。
- いつまで飲むべきかは、自汗がなかったものがじんわりと汗をかき始めるまで、がポイントとなります。
- 麻黄の主成分は交感神経の働きを高めるエフェドリンです。そのため、心臓に持病がある方や高血圧など一部適さない方がいます。このような方は必ずかかりつけ医や薬剤師と相談してからの服用にしましょう。
3. 漢方薬の簡易フローチャート
感冒時における漢方薬の選び方を、簡単に区分けしてご紹介します。本来、漢方薬の選択は非常に複雑であり、特に急性期では症状の経過や体調の変化に応じて薬を変更する必要がありますが、ここでは基本的な目安を示します。また、症状に応じて、その他漢方薬や解熱鎮痛剤、咳止めなどを併用することも可能です。
※この内容は、日本東洋医学会特別ワーキンググループの資料を基に作成しています。
3-1. 急性期かつ体力のある方(実証タイプ)
風邪の発症から3日以内を目安に、悪寒や熱感があり、自汗(自然な汗)がない状態で用いられる漢方薬をご紹介します。
- 高熱があり、関節痛や筋肉痛がひどい場合
- 麻黄湯:体を温め、発汗を促すことで、体内の寒邪(冷えによる不調)を追い払います。特に体力がある方に適しています。本剤もしくは麻黄附子細辛湯は、インフルエンザや新型コロナの初期にも用いられることもあります。
- 麻黄湯:体を温め、発汗を促すことで、体内の寒邪(冷えによる不調)を追い払います。特に体力がある方に適しています。本剤もしくは麻黄附子細辛湯は、インフルエンザや新型コロナの初期にも用いられることもあります。
- 悪寒や頭痛があり、特に肩や背中のこりを伴う場合
- 葛根湯:血流を促進し、寒邪を取り除きます。肩や首の筋肉の緊張を和らげる効果があります。
👉Amazonでの購入はこちら↗️
👉楽天市場での購入はこちら↗️ - 葛根湯加川芎辛夷(鼻閉がある場合):葛根湯に鼻の通りを良くする効果を加えた処方です。鼻づまりや頭重感が強い方に適しています。
- 葛根湯:血流を促進し、寒邪を取り除きます。肩や首の筋肉の緊張を和らげる効果があります。
- 鼻水、鼻づまり、くしゃみがひどい場合
- 小青竜湯:水分代謝を整え、過剰な鼻水や鼻づまりを改善します。アレルギー性の症状がある場合にも用いられることがあります。
- 小青竜湯:水分代謝を整え、過剰な鼻水や鼻づまりを改善します。アレルギー性の症状がある場合にも用いられることがあります。
- 吐き気や胃の不快感がある場合
- 平胃散:胃腸の働きを整え、消化不良による不快感を軽減します。食欲不振を伴う場合に適しています。
- 平胃散:胃腸の働きを整え、消化不良による不快感を軽減します。食欲不振を伴う場合に適しています。
- 嘔吐や下痢がある場合
- 五苓散:体内の余分な水分を排出し、消化器系のトラブルを改善します。脱水症状の予防にも役立つ処方です。
【注意点】1〜3のような漢方薬は、強く発汗を促すことになり、体力の消耗を加速させ、状態を悪化させる可能性があります。よって、基本的には少しでも汗ばむ程度の自汗であっても、1〜3は適応とはなりません。また、作用を強く出さないように、1〜3内での併用は基本的に行いません。
3-2. 急性期かつ体力のない方(虚証タイプ)
風邪の発症から3日以内を目安に、悪寒や熱感があり、自汗がある状態で用いられる漢方薬をご紹介します。
- 頭痛や発汗が特に気になる場合
- 桂枝湯:発汗を調節し、寒気や頭痛を和らげる効果があります。葛根湯のベースとなっているのが桂枝湯で、麻黄を除いたもので体力のないに用いられます。
- 桂枝湯:発汗を調節し、寒気や頭痛を和らげる効果があります。葛根湯のベースとなっているのが桂枝湯で、麻黄を除いたもので体力のないに用いられます。
- 寒気が強く倦怠感があり、自汗がない場合
- 麻黄附子細辛湯:麻黄と附子で強い寒気や倦怠感をとり、体力がない方に用いられます。
- 麻黄附子細辛湯:麻黄と附子で強い寒気や倦怠感をとり、体力がない方に用いられます。
- 軽度の悪寒があり胃腸が弱い体質の場合
- 香蘇散:胃腸の不調を改善し、寒気を和らげる効果があります。胃腸が弱い方に適しています。
- 香蘇散:胃腸の不調を改善し、寒気を和らげる効果があります。胃腸が弱い方に適しています。
- 吐き気や胃の不快感がある場合
- 平胃散:(同上)
- 平胃散:(同上)
- 嘔吐や下痢がある場合
- 五苓散:(同上)
3-3. 急性期後
発症から4〜5日経過すると、ある程度初期症状が治まり様々な症状が出てきます。その症状の違いにより漢方薬を使い分けます。
- 口内が苦くなったり食欲不振があり、胸脇苦満を伴っている場合
- 小柴胡湯:体の中に残った熱や炎症を鎮め、消化器症状を改善します。
- 柴胡桂枝湯:小柴胡湯の作用に加え、頭痛や寒気を取る作用もあります。
- 咳が残り喉の違和感がある場合
・柴朴湯:咳や喉の不快感を和らげ、気管支の炎症を抑えます。 - 痰が伴い強い咳がある場合
- 麻杏甘石湯:気道を広げて痰を排出しやすくし、咳を鎮めます。
- 五虎湯(咳がより強い場合):麻杏甘石湯に桑白皮(クワ)を加えたもので、より咳や炎症を抑える作用があります。
- 咳や痰がある場合
- 参蘇飲:風邪が長引くことによる、胃腸症状、咳や痰を改善します。
- 竹茹温胆湯:参蘇飲の症状に加え、特に夜間の咳が強く不眠や不安が伴う際に用います。
- 吐き気を伴う咳、下痢がある場合
- 柴苓湯:消化器症状や咳を抑えるとともに、水様性の下痢などにも用いられます。
- 柴苓湯:消化器症状や咳を抑えるとともに、水様性の下痢などにも用いられます。
- 胸痛を伴う咳がある場
- 柴陥湯:痰が切れにくく咳をすると胸が痛むような時に用います。
3-4. 回復期
風邪が発症してから一定の期間が経過すると、感冒自体は治まりつつありますが、特定の症状が残るケースがあります。この段階では、残った症状に対応する漢方薬を使用することで、体調の回復を促します。
- 空咳が残った場合
- 麦門冬湯:喉や気道を潤し、乾いた咳を改善します。沈脈2である時に用います。
- 麦門冬湯:喉や気道を潤し、乾いた咳を改善します。沈脈2である時に用います。
- 微熱が伴った空咳が残っている場合
- 滋陰降火湯:体内の熱を冷まし、喉の渇きや乾いた咳を和らげます。
- 滋陰降火湯:体内の熱を冷まし、喉の渇きや乾いた咳を和らげます。
- 切れにくい痰が残っている場合
- 清肺湯:気道の炎症を抑え、特に粘り気の強い痰の際に用います。
- 清肺湯:気道の炎症を抑え、特に粘り気の強い痰の際に用います。
- 全身倦怠感が残っている場合
- 補中益気湯:やる気がなかったり倦怠感を伴い、食欲不振や味気がないなど時によく用いられます。
- 十全大補湯:体力が落ちている状態で、特に貧血や皮膚が乾燥しているなど血虚の状態を改善します。免疫を活性化する作用もあると言われています。
- 人参養栄湯:十全大補湯の作用に加え、不安や不眠など精神症状を伴う時に用います。
3-4. その他不定期
特に感冒の時期に関係なく、その症状がある時に服用する漢方薬を示します。
- 桔梗湯:のどの痛みや腫れが痛い時に飲むことで有名な漢方薬です。服用法にも特徴があり、お湯に溶かして、ガラガラ患部をうがいしながら服用するとさらに効果的です。
- 桔梗石膏:さらに喉の痛みや炎症がひどく、化膿を伴う場合は効果的です。
4. 漢方薬に含まれる生薬の副作用
「漢方薬には副作用がほとんどない」と考える方もいますが、決してそうではありません。特定の生薬が含まれている場合、その主成分が予期せぬ症状を引き起こすことがあります。以下に、注意が必要な代表的な生薬とその副作用について説明します。
4-1. 麻黄剤(葛根湯、麻黄湯、小青竜湯など)
2-4の葛根湯の項にも記載しましたが、麻黄に含まれる主成分「エフェドリン」は、交感神経を活性化させる作用があります。そのため、次のような注意が必要です。
- 高齢者や心疾患・高血圧の持病がある方
心拍数の増加や血圧上昇を引き起こす可能性があるため、服用前に主治医に相談する必要があります。 - 高用量での副作用
過剰な服用により、不眠、排尿障害、動悸、頭痛などの症状を引き起こすことがあります。
4-2. 柴胡剤(小柴胡湯、柴胡桂枝湯など)
柴胡を含む漢方薬は一般的に安全とされていますが、稀に重篤な副作用が報告されることがあります。その中でも代表的なものは以下の通りです。
- 間質性肺炎
発症頻度は非常に低いものの、発熱、空咳、呼吸困難などの症状を伴う間質性肺炎を引き起こす可能性があります。この副作用は、黄芩も関与していると考えられ、機序としてはアレルギー反応が疑われています。漢方の証(適応)が合致していても、これらの初期症状が現れた場合はただちに服用を中止し、医療機関を受診してください。 - 膀胱炎様症状
膀胱炎のような排尿時の痛みや頻尿が出る場合がありますが、この症状は服用を中止することで軽快します。
4-3. 甘草(葛根湯、桔梗湯他多数)
甘草に含まれる主成分「グリチルリチン」は、体内でアルドステロンというホルモンに似た作用を示します。アルドステロンは水分やナトリウムを体内に保持し、血圧を上昇させる働きを持つため、甘草を過剰に摂取すると次のような副作用が現れる可能性があります。
- 血圧上昇
ナトリウム保持作用による高血圧のリスクがあります。 - ミオパチー(四肢の脱力感や筋肉痛)
低カリウム血症が引き起こされ、筋力低下や筋肉痛が生じることがあります。高血圧や心疾患などに対し、フロセミドなどのループ利尿薬を始めとした低カリウムをきたす薬剤を飲んでいる方はより注意を払わないといけません。 - 意識障害や呼吸困難など
偽アルドステロン症が進行すると、意識障害や呼吸困難を引き起こす可能性もあります。
この症状は、体内のアルドステロンが増加していないにもかかわらず、アルドステロン症の症状をきたすため「偽アルドステロン症」と呼ばれています。また、現在では偽アルドステロン症の発症は用量依存的であると考えられています。ただし、少用量でも報告されてはいます。
4-4. 附子剤(麻黄附子細辛湯)
附子に含まれる主成分アコニチンは、強い神経毒として知られており、過剰摂取による中毒の初期症状として動悸、悪心、舌のしびれなどが報告されています。ただし、漢方薬として使用される附子は、修治3が施されているため、適切な用量であれば中毒を引き起こすことはありません。よって、附子剤を服用する際は、必ず医師や薬剤師の指示に従い、用量を守ることが重要です。
5. さいごに
漢方の風邪薬を選択する際には、以下の点を特に重要視してください。
漢方薬は通常の総合感冒薬とは異なり、個々の体質、発症からの経過時間、その時の症状や状態によって選び方が大きく変わります。正しく使用すれば、風邪の回復を早める効果が期待できますが、誤った選択や服用方法では逆に体に負担をかける可能性もあります。
理想的には、事前に風邪の症状に応じた漢方薬を準備しておくことをおすすめします。たとえば、「3. 漢方薬の簡易フローチャート」を参考に、風邪の時に出やすい症状や状態を想定し、自分に合った漢方薬を選んでおくと良いでしょう。そして、風邪の進行状況や症状の変化に応じて、最適な漢方薬を適切なタイミングで服用することが重要です。
正しい知識を持って漢方薬を活用することで、風邪の回復を助け、体への負担を軽減することができます。自身の体調に合った漢方薬を見つけるためにも、医師や薬剤師に相談することを忘れずに!



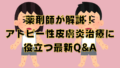
コメント