※本記事にはアフィリエイト広告を利用しています。商品リンクを経由して購入された場合、当サイトに収益が発生することがあります。
1. はじめに
2025年9月28日、厚生労働省の承認を受け、これまで要指導医薬品として扱われていた小林製薬の胃腸薬「イトプリド(製品名:イラクナ)」が、ついに第1類医薬品へと移行しました。これにより、購入方法にも大きな変化が生まれ、より手軽に入手できるようになります。
イトプリドを配合した「イラクナ」は、胃のもたれや食後の重たい感じを改善するタイプの胃薬であり、市販薬としてはこれまでにない作用機序を持ちます。従来の「胃酸を抑えるタイプの薬」とは異なり、胃腸の運動機能を活発化することで症状を改善するのが特徴です。
そのため、「効き方の選択肢が広がった」という点でも注目されており、今後のセルフメディケーションにおいて新たな選択肢となることが期待されています。
2. 消化管の動きと神経の関係
イトプリドの仕組みを理解するには、まず胃や腸がどのように動いているのか、そしてその動きを支える神経の働きについて知っておく必要があります。ここでは、消化管の基本的な動きと、それを調節する神経伝達の仕組みを簡単におさらいしてみましょう。
2-1. 消化管は“ベルトコンベア”のように動いている
私たちが食べたものは、胃から腸へと順番に送られていきます。この流れをスムーズに進めているのが、消化管の筋肉(平滑筋)です。
もし体の中に「ベルトコンベア」があるとしたら、それを動かすモーターにあたるのが副交感神経です。この神経が活発に働くと、ベルトコンベア(=胃腸の動き)がしっかり稼働し、食べたものが滞りなく運ばれていきます。
逆に副交感神経の働きが弱まると、モーターの力が落ちてベルトの動きが鈍くなり、食べ物が胃にとどまりやすくなります。これがいわゆる「胃もたれ」や「食後の重たい感じ」の原因となるのです。
2-2. アセチルコリンと呼ばれるスイッチ
副交感神経が「動け!」と命令を出すときに使うのが、アセチルコリン(以下ACh)という神経伝達物質です。これはいわば“エンジンの点火スイッチ”のようなもので、AChが筋肉の受け皿であるムスカリンM3受容体に結びつくことで、胃腸の筋肉が「よし、動こう!」と収縮を始めます。
ただし、スイッチが入りっぱなしでは動きすぎてしまうため、体内ではアセチルコリンエステラーゼ(以下AChE)という“ブレーキ役”が働き、余分なAChを素早く分解します。
この「オン(ACh)」と「オフ(AChE)」のバランスによって、胃腸の動きはちょうどよく保たれているのです。
2-3. ドパミンやセロトニンによる“遠隔操作”
さらに興味深いのは、このAChのバランスを“遠隔操作”している存在があるという点です。それがドパミンやセロトニンといった神経伝達物質です。
たとえばドパミンは、AChの働きを抑えることで「ちょっと落ち着け」とブレーキをかける役割を持っています。ドパミンの抑制が強く働きすぎると、AChの量が減り、結果として胃腸の動きが鈍くなってしまいます。
一方、セロトニンはその逆で、消化管の運動を促進する方向に働くことがあります。これらの神経伝達物質が複雑に絡み合いながら、私たちの消化管の動きを微調整しているのです。
このような神経の仕組みを理解すると、イトプリドが「ドパミンのブレーキを外し、AChの働きを高めることで胃腸の動きを促す薬」であることが、より納得できるはずです。次章では、イトプリドがこの仕組みにどう関与するかを詳しく見ていきましょう。
3. イトプリド(イラクナ)の概要
3-1. イトプリドとはどんな胃薬
イトプリドは、胃の動きを活発にするタイプの胃薬です。食べたものをスムーズに胃から腸へ送り出すよう促し、「胃もたれ」「食後の重たい感じ」「おなかの張り」などの不快な症状をやわらげます。
これまで市販されてきた多くの胃薬は、「胃酸を抑える」ことを目的としたものでした。たとえば、胸やけや胃痛に使われる制酸薬(胃酸を中和する)や、H₂ブロッカー/PPI(胃酸の分泌を抑える)などが代表的です。
それに対し、イトプリドは“胃酸”ではなく“胃の動き”そのものに働きかける、まったく異なるアプローチの薬です。市販薬としてはこれまでにないメカニズムを持ち、胃腸の運動機能を直接整えることで、食後の不快感を改善します。
3-2. ダブルの作用機序 ―「ブレーキを緩め、動きを整える」
前の章で見たように、胃腸の動きは「アクセル(ACh)」と「ブレーキ(AChE)」、そしてそれらを調整する「司令塔(ドパミン)」のバランスで保たれています。
ここでイトプリドが優れているのは、そのバランスを“両側から整える”点です。
- 胃の動きを妨げるブレーキをゆるめる
ドパミンが強く働くと、AChの放出が抑えられ、胃腸の動きが鈍くなります。イトプリドはこのドパミンの信号をやわらげることで、必要以上のブレーキを解除します。 - 動きを支えるエネルギーを保つ
さらに、AChを分解してしまう酵素(AChE)も穏やかに抑えるため、胃腸を動かす力を長く保つことができます。
つまりイトプリドは、
「ブレーキをゆるめながら、エンジンの回転を少しだけ上げる」
そんな精密な調整を行う薬といえます。また、イトプリドは胃の中が空のときには消化管の動きにほとんど影響を与えず、食後など必要なときにだけ作用するという特徴があります。
そのため、体に余計な負担をかけにくく、この“ダブルの働き”によって、単に「無理やり動かす」のではなく、本来のリズムを取り戻すように胃の動きを整えることができるのです。
また、イトプリドは胃の中が空のときには消化管の動きにほとんど影響を与えず、食後など必要なときにだけ作用するという特徴があります。
そのため、体に余計な負担をかけにくい、生理的で穏やかな作用特性を持っています。
3-3. 制吐作用 ―「吐き気を抑える」しくみ
胃腸の不調といえば、吐き気もつらい症状のひとつです。イトプリド(イラクナ)には、胃の動きを整えるだけでなく、吐き気をやわらげる作用もあります。では、それはどのような仕組みで働くのでしょうか?
実は、吐き気を抑える(制吐)作用には、大きく分けて2つのルートがあります。
3-3-1. 中枢性の制吐作用 ―「脳の吐き気スイッチを止める」
脳の中には「化学受容器引金帯(CTZ)」という、吐き気を感じ取るセンサーのような場所があります。ここが刺激されると、嘔吐中枢が反応し、異物などを「吐き出せ」という指令を出します。
メトクロプラミド(プリンペラン)やドンペリドン(ナウゼリン)などの薬は、このCTZにあるドパミンD₂受容体をブロックすることで、吐き気の信号を遮断します。これが「中枢性の制吐作用」です。
3-3-2. 末梢性の制吐作用 ―「胃腸の動きを整えて吐き気を減らす」
一方、イトプリドは消化管(末梢)に存在するD₂受容体を遮断し、AChの分泌を促して胃腸の動きを活発にすることで作用します。
胃の動きが停滞すると、内容物が胃にたまり、腸が膨らんで迷走神経を刺激します。この刺激が脳の嘔吐中枢に伝わることで、吐き気が起こるのです。
イトプリドはこの「胃の停滞(胃内容うっ滞)」を改善し、吐き気の原因そのものを減らすことで症状をやわらげます。
3-4. 正反対に働く胃薬もある ―「動かす薬」と「休ませる薬」
ここまで見てきたように、イトプリド(商品名:イラクナ)はAChの作用を助け、胃腸の運動を促すタイプの薬です。いわば「胃にエンジンをかける」ような働きで、停滞した消化管を再び動かす役割を担います。
ところが、同じ“胃薬”でも、まったく逆の方向に働くものもあります。代表的なのが、ブチルスコポラミン(商品名:ブスコパン)などの抗コリン薬です。
3-4-1. 抗コリン薬は胃を「休ませる」タイプ
抗コリン薬は、AChが受容体(ムスカリン受容体)に結びつくのをブロックすることで、消化管の動きを抑える薬です。胃や腸の筋肉が過剰に収縮して起こるけいれん性の痛みや差し込みをやわらげる効果があり、「動きを鎮めて痛みを取る」タイプの胃薬といえます。
さらに、抗コリン薬には胃液分泌抑制作用もあります。胃酸やペプシン(タンパク質分解酵素)の分泌を抑えることで、胃の粘膜への刺激を減らし、痛みや不快感を軽減します。
つまり、胃腸を「休ませて落ち着かせる」タイプの薬といえるでしょう。
3-4-2. 症状のタイプで変わる胃薬の選択
このように、同じ「胃薬」といっても、
- 胃の動きを抑える薬:けいれんや胃炎などによる痛み→抗コリン薬
- 胃の動きを高める薬:胃の停滞やもたれ感→D₂受容体拮抗薬
といったように、原因と症状に応じて使い分けることが大切なのです。
同じ「胃薬」でも、まるでアクセルとブレーキのように働き方が違う――。 そんな薬の多様性こそ、体の仕組みを理解して選ぶ面白さだといえるでしょう。
4. 第一類医薬品への移行で何が変わる?
イトプリド(イラクナ)が医療用医薬品から市販薬と売り出されてから、しばらくは要指導医薬品として取り扱われてきました。3年もの月日を経て第一類医薬品に移行されることになったわけですが、それにより何が変わり私たちにはどのような影響があるのでしょうか?
4-1. 要指導医薬品とは?
まずは、「要指導医薬品」について簡単におさらいしておきましょう。
要指導医薬品とは、もともと医療用医薬品として医師の処方が必要だった薬が、安全性や有効性の評価を経て、一般用医薬品(OTC医薬品)として販売が認められたものです。こうした薬は「スイッチOTC」と呼ばれ、処方箋なしでも購入できるようになります。
ただし、スイッチ直後の段階では、個人の選択による使用経験が限られており、安全性などが把握されていない可能性があるため、慎重な取り扱いが求められます。
そのため、要指導医薬品には以下のような特性があります:
- スイッチOTC直後の品目であること
- 効果は比較的穏やかだが、誤った使い方をすると健康に影響を及ぼすおそれがある
- 薬剤師が対面で説明・指導した上でしか販売できない
つまり、「薬剤師が直接説明し、正しく使えるようにサポートすること」が前提の薬――それが要指導医薬品です。
なお、こうしたスイッチOTCの薬は、発売からおおむね3年ほどで「第一類医薬品」に移行するのが通例です。
4-2. 要指導医薬品から第1類医薬品へ
イラクナ(一般名:イトプリド)は、2022年9月28日にスイッチOTCとして市販化され、発売当初は「要指導医薬品」として取り扱われてきました。これは、新たに一般用医薬品として承認されたばかりで、安全性や使用実績のデータがまだ十分でなかったためです。
その後、市販後の使用を通じて副作用や相互作用に関する情報が蓄積され、一定の安全性が確認されたことから、ちょうど3年後の2025年9月28日に「第1類医薬品」へと移行しました。この流れは、スイッチOTCでは一般的なステップといえます。
そして今回の変更で最も大きいのは、薬剤師による「対面での説明」が必須ではなくなったという点です。
要指導医薬品では、薬剤師が店頭で直接説明しなければ販売できませんでしたが、第1類医薬品になると、薬剤師による情報提供は必要であるものの、対面でなくてもよくなります。その結果、インターネット販売が可能となり、イラクナは今後、薬局のカウンターだけでなくオンラインでも購入できるようになりました。
これにより、これまで薬局に足を運ばなければ入手できなかった薬が、より多くの人にとって身近で手に取りやすい存在となったのです。
4-3. ネットでの購入
2025年10月現在では、第1類医薬品への移行から間もないこともあり、ネット通販最大手のAmazonではまだ販売が開始されていないようです。一方で、楽天市場やYahoo!ショッピングなどの大手通販サイトでは、すでにいくつかの店舗から購入できるようになっています。
ここでは、現時点で購入可能な楽天市場での販売ページを紹介します。
(※販売状況は今後変動する可能性があります。購入の際は、最新の情報を必ずご確認ください。)
5. イトプリド(イラクナ)の基本情報
5-1. 効能または効果
イラクナ(イトプリド塩酸塩)は、消化管の運動を促進することで、胃の状態を改善し、吐き気などの不快な症状を和らげる薬です。主な効能・効果は以下のとおりです。
- 胃もたれ
- 胃部膨満感(おなかの張り)
- 食欲不振
- 胸やけ
- 吐き気
これらの症状は、胃の動きが鈍くなり、食べたものが胃に長く留まってしまうことで起こることがあります。イラクナは、こうした胃の運動機能低下に伴う症状の改善に用いられます。
なお、「3-3-2. 症状のタイプで変わる胃薬の選択」で説明したように、胃酸の分泌過多や痙攣による胃痛など、原因が異なる場合には、制酸薬や抗コリン薬など、別のタイプの胃薬を選択することが適切です。
5-2. 用法および用量
通常、成人には1回1錠を1日3回、食前に服用します。
なお、15歳未満の方については、有効性および安全性が確認されていないため、服用はできません。
イトプリドは、食後に起こりやすい胃もたれや膨満感などの不快症状を予防するため、食前に服用するのが基本です。これは、薬が体内に吸収されて効果を発揮するタイミングが、ちょうど食後の消化活動が始まる頃と重なるためです。
なお、インタビューフォームには食前投与の明確な根拠は記載されていませんが、薬理作用(胃運動促進作用や吸収速度)および生理的な消化リズムを踏まえると、食前投与が理にかなっているといえるでしょう。
5-3. 相互作用
抗コリン作用をもつ薬――たとえば、ブチルスコポラミン(ブスコパン®︎)やチキジウム(チアトン®︎)など――との併用には注意が必要です。
「3-4. 正反対に働く胃薬もある ―『動かす薬』と『休ませる薬』」でも説明したように、イトプリドはAChを優位にして胃腸の動きを活発にする薬です。一方、抗コリン薬はAChを阻害し胃腸の動きを鎮める薬です。
そのため、両者を同時に使用すると、お互いの作用を打ち消し合ってしまうおそれがあるためです。
5-4. 副作用
5-4-1. 重大な副作用
- ショック、アナフィラキシーショック(頻度不明)
頻度はまれですが、発疹、息苦しさ、めまい、意識の低下などがあらわれることがあります。 - 肝機能障害、黄疸(頻度不明)
同じくまれですが、発熱、皮膚のかゆみ、全身のだるさ、皮膚や白目が黄色くなるなどの症状がみられることがあります。
これらの症状が現れた場合は、服用を中止し、直ちに医師または薬剤師に相談してください
5-4-2. 比較的頻度の高い副作用
- 便秘または下痢
- 腹痛
- 唾液増加
これらの副作用は、AChの作用が優位になることによって起こると考えられています。
イトプリドはAChの分解を抑制する薬であるため、ムスカリン受容体を介したコリン作動性の反応が強まることで、消化管の動きが活発になり、腹部症状や唾液分泌の変化が生じることがあります。
5-4-3. 他特徴的な副作用
イトプリドはドパミンD₂受容体拮抗作用を持つため、ドパミンの働きを抑えることにより、以下のような特徴的な副作用が報告されています。
- プロラクチン上昇
乳腺刺激により、乳房の腫れ(女性化乳房)や乳汁分泌がみられることがあります。 - 錐体外路症状
まれに、手指の震え(振戦)などの症状があらわれることがあります。
ただし、イトプリドは同様の作用をもつドンペリドン(ナウゼリン)などとは異なり、血液脳関門をほとんど通過しにくい構造をしています。そのため、脳内でのドパミン遮断作用は非常に弱く、実際の脳内濃度は血中濃度の約1/7程度と報告されています[1]。
このため、上記のような中枢性副作用は理論上起こりにくいとされており、イトプリドは同系統薬の中でも比較的安全性の高い設計となっています。
5-5. 使用上の注意
イトプリド(イラクナ)は、一時的な胃もたれや胃の重さなど、胃の運動機能低下に伴う症状を改善するための薬です。そのため、漫然と長期間にわたって服用し続けることは避けるべきです。
また、2週間ほど使用しても症状が改善しない場合は、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。これは、胃もたれなどの症状の原因が、単なる胃の働きの低下以外にある可能性を見逃さないためです。
たとえば、以下のような疾患や要因が隠れているケースもあります。
- 胃潰瘍
- 逆流性食道炎
- 肝・胆道系の疾患
- ストレスや服薬の影響
このような場合、自己判断で薬を飲み続けても根本的な改善にはつながらず、かえって診断が遅れる可能性もあります。症状が長引く場合は、原因を正しく見極めるためにも、専門医の診察を受けることが重要です。
6. まとめ
以上、要指導医薬品から第1類医薬品へと移行した イトプリド(商品名イラクナ) について解説しました。
イトプリドは、従来の「胃酸を抑えるタイプの胃薬」とは異なり、胃腸の運動機能を整えることで、胃もたれや膨満感などの不快な症状を改善するという新しいアプローチの薬です。必要なときに穏やかに作用するため、体への負担も少なく、今後はインターネットでも購入できるようになった点は、患者にとって大きな利便性の向上といえるでしょう。
ただし、2週間使用しても症状の改善がみられない場合や、同じ症状が繰り返し起こる場合には、自己判断で服用を続けるのではなく、医師や薬剤師に相談することが重要です。
胃の不調にはさまざまな原因があり、すべてが胃の運動機能低下によるものとは限りません。イトプリドは、その中でも「胃の動きが鈍いタイプの胃もたれ」に対する新しい選択肢として、今後さらに注目される薬といえるでしょう。
【参考資料】
- ガナトン錠50mg インタビューフォーム(アステラス製薬株式会社)
Ⅶ. 薬物動態に関する項目参照 5. 臨床試験の項参照 ↩︎

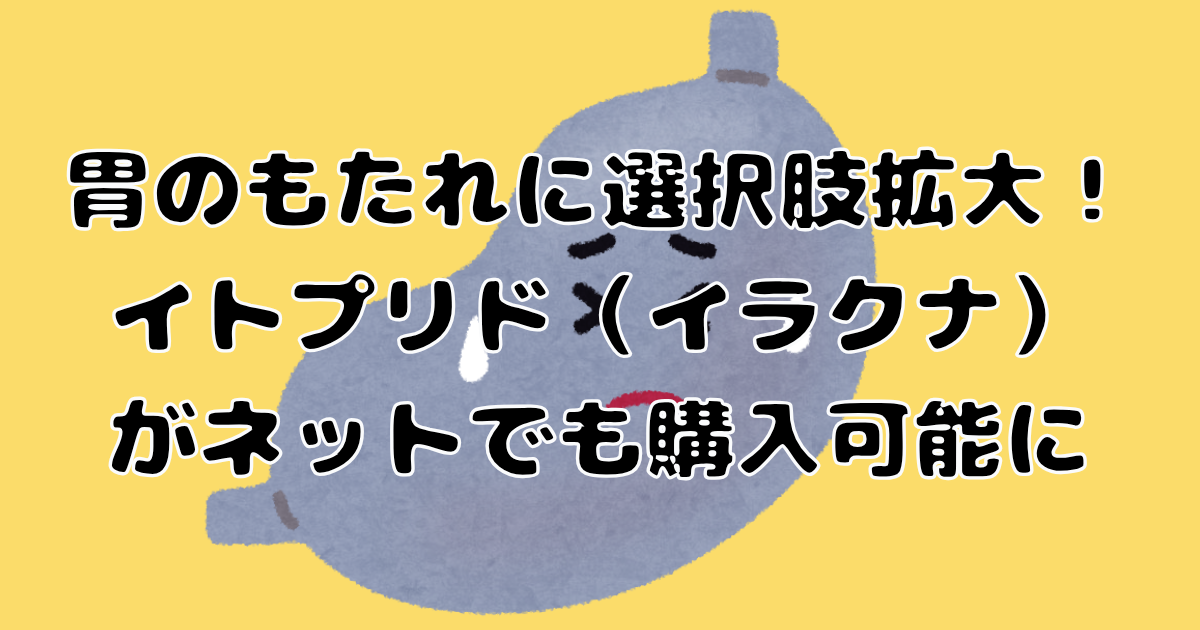
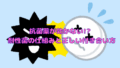
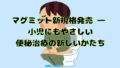
コメント